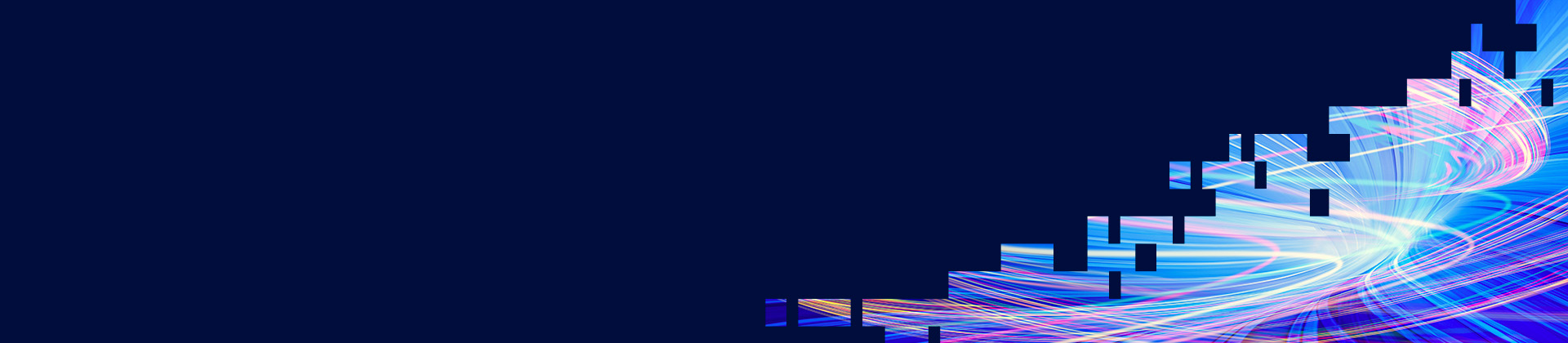故郷釧路の魅力
- 2024.09.10
- いい話・格言・理念, プライベート・その他
2023年、釧路港が1991年以来32年ぶりに水揚げ量日本一になったらしいです。釧路は昔は9年間も続けて水揚げ量日本一だったりしました。出身者としては嬉しいニュースです。
そんな釧路を含めた道東の魅力はなかなか伝わりにくいのですが、ここまで猛暑が続くとここの涼しさが魅力的です。
釧路が30度なんてめったにないので、この日本全国猛暑の時代、大自然がたくさん残る涼しい釧路の人気がもっと高まるよう、微力ながら応援したいと思っています。鶴もご飯も最高なんです!一度行かれた方は好きになって頂けるはず…。
一方で、日本一生活保護割合が多いとも言われる私の地元釧路では貧困の連鎖があると感じます。
父は生前に親族が釧根地方唯一の児童養護施設に住み込みで子供たちのお世話をしていたんだよと話していました。無論若い時はそんなことなんて気にもとめず…でしたが途中からわずかばかりのサポートをしています。この歳になりもっと何かできるはずと思う日々。
生まれ育った地元への恩返しも微力ながら続けていきたいと思います。

低価格戦略への警鐘
大好きな稲盛さんの言葉に「値決めは経営」というのがあり創業時は常に心がけていました。
職員が増えると低い報酬でも、受注することを優先して低利益で数だけ増えていきました。
その時は辛かったかもしれません。でもあの時期があったから今があるかもしれず。やはり値決めは難しいと感じます。
しかし本来、士業事務所では価格が理由でコンペで勝ってもそれは喜ばしい事ではありません。安価で良いサービスをすると職員に負荷がかかります。にも関わらず職員に還元できず、結果サービス品質が悪化します。誰も幸せになりませんので、受注率自体にはあまりこだわらず常にベストプライスを提示していきます。
また「上下の関係」を度外視して事務所経営をしています。報酬と労働は等価交換であり、お金を払っている方が偉い事はありません。我々が顧問先にサービスを提供する際も同じ考え方です。等価交換の原則が崩れると関係も崩れます。
昨今少しずつインフレが浸透してきた世の中においても、士業の世界では安価にプロフェッショナルサービスを提供する事務所がまだとても多いように感じています。
これは所長1人で自宅などでやると決めた場合にはいい方法だと思います。自分の見きれる範囲で直接対応し、高クオリティのサービスをリーズナブルに提供し、顧客と信頼関係を築き追加の仕事を受注する。受けきれなくなったら職員を採用するのではなく、値上げをお願いしたりお断りする。
ですが職員を1人でも採用する場合、一気にいい方法ではなくなってしまいます。所長と比較して生産性や品質が低いメンバーが入ることにより、当初の所長の目論見が崩れてきます。十分ではない待遇や教育や福利厚生も相まっての職員の離職、そして新規採用活動により非常にストレスフルな状況になります。
ただし、もっと視座を上げるなら、果てしなく高い志、あるいは、大きな資本力がありスケールメリットを出すまでやり遂げるならば、これはまたいい方法だと思います。例えば1000人の事務所を作るまでとことんやる、最初から5億円以上投資できるetc. 顧客が増えて一斉に値上げやクロスセルで追加サービスの提案など攻め手が増えます。
テクノロジーを利用して低価格で高品質なサービスを…という世界は非常に理想的なのですが、個人的な経験ではそこにビジネスチャンスと成長するマーケットがあれば、巨人が参入してくると感じています。
最近ではBPaas(BPOとクラウドコンピューティングを組み合わせ)に関しても巨大資本の参入が始まっているので、舵取りは極めて重要だなと感じる日々です。
一方で「ここ2年値上げがなかったので」値上げさせてという理由は日系企業では簡単には受け入れられないかもしれませんが、経済成長やインフレを感じ経営している国の会社であれば十分に受け入れ可能。日本企業が企業努力で解決するのだという精神が、世界競争において裏目に出てしまっていることを強く感じます。
海外の会議に参加すると、皆人手不足とは言いつつも、高単価の案件をいかに大量に獲得するかという視点が相当強いです。つまり、それが昇格や昇給のために重要な要素になっているということなのでしょう。

資格は「武器」ではなく「防具」
弊社には働きながら資格取得を目指しているメンバーが多くいます。資格を目指すなら、せっかくなので集中的に勉強してなるべく早く取得してほしいと思っています。取得後にはぜひ一緒に新しいこと(IT、英語、経営etc.)に取り組みましょうという思いで待っています。
そのためにRSM汐留パートナーズには資格取得を応援するさまざまな制度を用意しています。その一つとして試験休暇があり、税理士試験や社労士試験などの試験を受ける場合、5日間休むことができます。時期や条件は資格によって異なりますが、多くのメンバーが活用しています。
税理士の統計データを見てみると、「60歳以上の比率は54%超、20代の税理士は0.6%」となっており、平均年齢が60歳以上と特殊な業界です。さまざまな意見があると思いますが、若い方々が税理士になることは本当に希少であり、私は税理士を志している方々を心から応援しています。
また社労士の試験勉強も応援しています。これからより一層人が大切な時代であり、税理士と社会保険労務士の相性は抜群です。IPO、M&A、組織再編の局面でも大活躍できます。国際的な事務所/ワンストップの事務所で仕事をしてみたいという方に魅力を感じていただける社労士法人にしたいと思います。
次に資格を取るメリットについて触れたいと思います。このメリットは「年収が上がる」というよりも、「年収が下振れしない」という意味の方が大きいかもしれません。もし年収を上げていきたいのであれば、テクニカルスキルに加え、さまざまなソフトスキルを一つ一つ身に着ける必要があると感じます。
資格を取り、それで十分なご飯を食べていく時代は終わりを迎えているのかもしれません。固定観念を捨て、資格を「防具」と考えたいです。どんなに打たれても撃たれても簡単には死なない(食いっぱぐれない)素晴らしい鎧です。
最後に資格のコスパについて触れますと、関係してくるのは投下時間とお金だけです。自分が成し遂げたいことや思いがあって、その資格に関する勉強をして仕事を頑張りたいという場合にはあまり関係がないものです。自分の心の声に従い、その資格が必要であればやる、思いがなければやめるということで、周りは気にせずにいいと思っています。

共創と縁
士業の業界において、これからの時代は「競争」ではなく「共創」が重要であると考えています。資格や組織を超えての連携。
先日行ったプロジェクトで、異なる士業や事務所の方々と連携することで、自社単独では得られなかった成果を上げることができました。共に価値を創造することの大切さを強く感じました。
企業の事業活動が多岐にわたり、カバーする領域も広がっているため、1つの士業や事務所だけでは対応できる範囲が限られてきます。一昔前であればライバルという表現を使ったかもしれませんが、今後はより一層連携して価値を創造していきたいと思います。
私もRSM汐留パートナーズも自身もまだまだ成長の途中ですので、これからも多くの方々と協力し合いながら、共創を大切にし皆様とともに成長していきたいです。
4年前に札幌に事務所を出したいとずっと言っていたら素晴らしいご縁をいただき、昨年無事事務所を開設することができました。現在は2名のメンバーが在籍しています。次は西へ…同じく言霊とすべく積極的に発信していきたいと思います。

「謙虚であること」
「謙虚であること」はすごく大切だと思っています。もっというと「すごいのに謙虚」だと無敵だと思っています。
世の中には素性を隠していますがすごい人たちがたくさん潜んでいます。
そんな人達の前で偉そうに語ると後ですごく恥ずかしいことになります。
常に謙虚に過ごすことのほうがはるかにメリットが多いと感じます。
反対に過分な要求はその人の評価を貶めます。謙虚な方ほどまだまだ学ぶ意欲があり伸び代があります。
“謙虚=自信がない”ということではなく、情熱的だったりハングリー精神があったり高みを目指す謙虚さが好きです。
自分より若い方に会う時や評価に立ち合う際はそんな視点を持って見るようにしています。
弊社にはありがたいことに私より優秀なメンバーがたくさん。でもできればそんなメンバーにまだ一目おいてもらいたい…
自己研鑽をする人生にしてほしいという意味を込め「吾を研く」ということで親が名前をつけてくれました。
皆に愛想を尽かされないように、これからも精進していきたいと思います。

「言霊」
- 2024.05.20
- いい話・格言・理念
「言霊」という言葉があるように、発せられた言葉は魂を形成し続けます。
文章をしばらく読んでいるとその方がどんな思いで生きているのかわかってきます。心の内側を覗き見できるような…
SNSによって素敵な出会いがたくさんありますが、一方で避けるべき出会いを見極める助けになっている気もします。自分の知らない所で間接的にでも意図してか攻撃や反論をされるとフラグが立つのではと思います。
また、時々オンラインではすごく尖っていても会うととてもいい人でお調子者で憎めない人もいます。キャラ作りしていると感じます。そのためオフラインの出会いも大切にしていきたいです。
時々生じる乱戦に入っていき思いの丈をぶつけてしまうと、逆に良くも悪くも自分を世に強く印象付けることになりますので、深入りは禁物です。
今後も燃えている場所や紛争地帯を避け心穏やかに過ごしていきたいと思います。人生後半にいたずらに新たな人脈を広げても意味はありません。皆様引き続き仲良くしてください。

「競争社会において勝つためには競争しない」
- 2024.05.10
- 公認会計士・税理士, いい話・格言・理念, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話
年々参加者が減る流れですが、今年も合同就職説明会にブースを出したいと思います。 国内と国際の両方をバランスよく経験できる事務所としてアピールしていきたいなと思います。最近は国際業務で頑張りますという若手が志望してくれるのもまた嬉しいです。
弊法人はそもそも税理士試験科目合格者や会計事務所経験者は年間通じて採用しています。どうしても入りたい事務所があった場合、あえて試験前の5月のこの時期に就職活動するという方法も良いのではと。
つまり、皆様は試験後の夏に就職活動するので一定の競争環境におかれますが、今の時期の就職活動はそこまでの競争にはならないので、入りたい所を回ることができ採用される確率がとても高くなります。さらにはエージェント経由ではなく直接応募することにより、採用側のエージェント手数料がかからず期待値を下げて臨むことができ、採用される確率を上げることも重要です。
これは「競争社会において勝つためには競争しない」というドラッカーの教えそのもので、私はいつもどうしたら競争しないで勝てるのか考えています。
ここまで、採用される側の戦略はわかったのですが、採用する側からすると就職説明会にブースを出すこと自体が競争環境に身を置くことなので堂々巡りです。

お互いのリスペクトから始まる会社組織
- 2024.05.01
- 公認会計士・税理士, いい話・格言・理念, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話
飲み会に心から喜んで参加し仕事を取ってこれる社交的な人と、来た仕事をなんでも調べてしっかりミスなくこなせる専門性の高い人。
お互いタイプは全然違っても、非難しあうのではなく尊敬しあい、同じ志のもと手を組むと最強のチームになります。リスペクトから会社組織が始まります。
ただ、残念なことにこのような二人組の創業はなかなかうまくいきません。三人組だとなおうまくいきません。「俺が仕事を取ってきているんだ」、「俺が仕事をこなしているんだ」、「そういえばあいつは何もやっていないよな!?」というような感じです。分裂をたくさん見てきました。
私の経験上前者の人がマジョリティを持ち経営する場合、業務をしっかりこなすメンバーに最大限のリスペクトがあれば組織拡大できます。一方後者の人がマジョリティを持ち経営する場合、比較的似たタイプのメンバーを集めることで人数はそこまで増えずとも強い組織を作ることができるように感じます。
もちろんこれにあてはまらない例外もあって、日本においてこの数十年間で、本当に凄いカリスマ経営者が真似をできないような方法で、最短で巨大な組織を作った事例もいくつかあります。
自分と同種同類の人たちの限られたコミュニティにいると気持ちよくて確かにすごく快適ですが、勇気をもって外の世界へ飛び出し寛容な気持ちで仕事をするのもありです。どちらが正解とかはなく自分の大切にする価値観にあうかどうかですね。
これからも自分にない感性やスキルや経験を持つ方々に心から敬意をもって過ごしたいと思います。

RSM汐留パートナーズ株式会社創業16周年
本日4月1日はRSM汐留パートナーズ株式会社の設立日です。今年で設立16周年です。16年前の2008年4月1日、私が27歳2か月の時に東京法務局港出張所に会社設立登記の申請を自分で出しに行きました。
実はその時にはすでに現在の汐留フィロソフィの3つの経営理念と3つの行動理念はすでに完成していました。このような素晴らしい未来があることまでは考えられてはいませんでしたが、とにかく寝る暇も惜しんで仕事と自己研鑽をしていましたら、1人、また1人と、応援団が集まってきました。
毎年この日は会社の誕生日であり大変嬉しく思います。こうして長きに渡り成長を続けてこられているのも、過去から現在において貢献して下さっているアラムナイを含むすべてのメンバーのお陰です。この場を借りて御礼申し上げます。
本日入社式がありますが、未来の汐留を担う若い世代を共に大切にしていき、ますます成長・発展していきます。リニューアルしたRSMブランドとともに17年目もどうぞよろしくお願いいたします。
部下のモチベーションアップは上司の仕事なのか?
『部下のモチベーションアップは上司の仕事なのか?』
チームメンバーのモチベーション管理で悩む管理職と食事したときのお話。どうやって部下のモチベーションを上げたら良いか?
持論ですが私の回答としては「モチベーションを下げないように維持はした方がいいが、そもそも上げることまではしなくていい」というものです。
そこまでは管理職には求められないですし、あとは本人によるところも大きいと思っています。これを管理職のメンバーに対して明らかにすることで救われる部分もあるのではと思っています。
例えば資格試験を1つの例にするならば、難易度の高い資格を取って活躍した方がいいとしても、本人がそう思わなければ絶対に受かりません。上司によるモチベーションアップ施策で資格を取得できるなんてことはまずありません。
あるいは離職率が低いほうがよい、離職が多いと上司の責任が…という話も世の中では聞きますが、弊社ではそこはマネジメントに関与するメンバーの評価項目でもなく、伸びるメンバーをより伸ばすということも重要ではないかと思います。
プロフェッショナル・サービス・ファームは事業会社とは異なる独特のカルチャーがあり、一人一人が商品でもあり会社の顔となり、資格や語学やテクノロジーに関する自己研鑽をして、マルチタスクしつつ売上を上げていくというモデル。どうも合わないという人がいても全く不思議ではありません。
若い世代では上席になりたくないという人が増えているかもしれませんが、そのポジションになって見える世界もありますし、そのポジョンの役割が誤解されず明確になれば、マネジメントというお仕事も魅力的になっていくのでは思います。