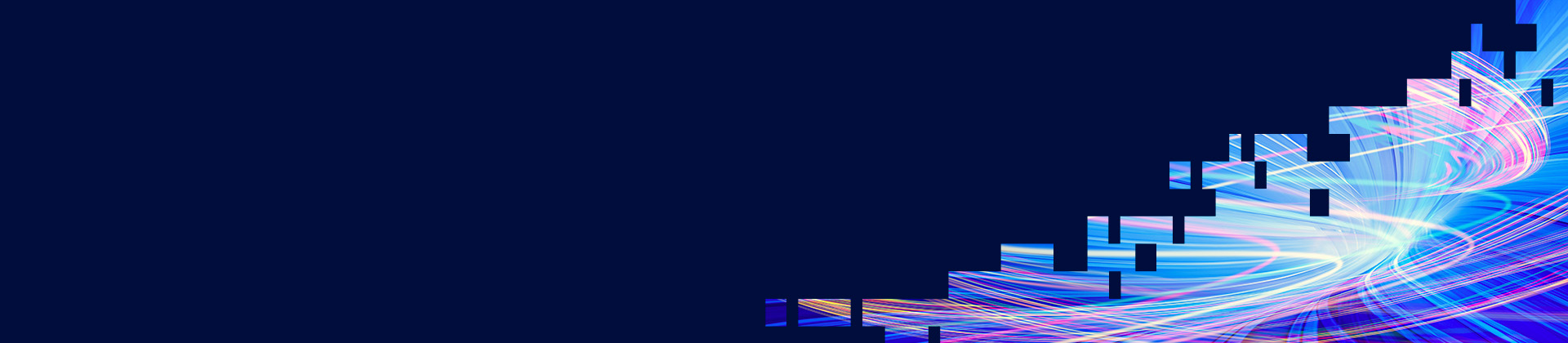従業員数3桁以下の会社の昇格のリアルな仕組み
- 2025.09.20
- ビジネスの話
RSM汐留パートナーズでは年2回昇格のタイミングがあります。会社と個人の成長スピードが速い中で、年1回の昇格では機会が限られると考えているためです。そのため、年齢や社歴に関係なく、人によっては驚くほど速いペースで駆け上がっていきます。
経験上、私が以前所属していた大手監査法人のように、従業員が数千人の企業や社歴の長い企業では、ある程度システマティックに規定通りあがっていきます。予定より早い昇格や飛び級などもほとんどなく、トップマネジメント以外でサプライズ人事は稀です。
一方で、従業員数が3桁以下、すなわち1000人未満の会社では、もちろん評価や昇進のルールはしっかり整備されていても、やはり会社のトップマネジメントに自分のことを認知してもらうことが不可欠だと感じます。最終的に決めるのはシステムではなく「人」だからです。現実的な話になりますが、避けては通れない要素です。
弊社はもうすぐ役職員250名になろうとしているのですが、実際私もすべての昇格推薦に目を通しコメントをしています。推薦対象者についてよく知らない場合や、良い評判が私の耳に入ってこない場合は、周囲に積極的にヒアリングしています。もちろん、事業部所属であれば個人の担当売上目標金額の達成なども大切なのですが、それだけではありません。間接業務を含め会社の運営にどの程度貢献しているか、今後も貢献できるポテンシャルがあるか、他事業部にも興味を持っているか、時間外に自己研鑽の習慣があるか(資格や語学の習得に限らず)といった点も重視しています。
最近は昇格よりもワークライフバランスを重視する方も増えているように感じますが、社員数1000人未満の会社で昇格・昇進を目指す成長意欲や挑戦心を持った方にとっては、その挑戦を後押しする場であり続けることが大切だと考えます。
労働分配率から考える経営の姿
- 2025.09.10
- 公認会計士・税理士, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話
税理士法人の経営者同士の勉強会では、労働分配率が話題にのぼることが多くあります。その際、税理士法人によって代表者の報酬の多寡が大きく異なるため、労働分配率(社会保険料・賞与を含み、代表者報酬は含まない)がよく話題になります。
規模にもよりますが、100人以上の事務所で考えると、理想は50〜60%程度とされているように感じるのですが、弊社の連結ベースでは代表者報酬も含め65%ほどという感覚です。それでも高すぎるとは感じていませんが、税理士法人全体で見ればどうも高い方に位置されるように感じます(私の代表者報酬が高いということはございません笑)。
この点について実はずっともやもやしていました。このもやもやについて、Big4監査法人の損益計算書(P/L)を眺めて電卓を叩き労働分配率を計算し、遅ればせながら自分の中で整理がついてきまして、霧が晴れてきました。日本のBig4監査法人の労働分配率(2023/24期、パートナー役員報酬含む)は62〜74%ほどです。この差は、パートナーの取り分が役員報酬とされてP/Lの販管費に含めているのか、税引後当期純利益からの配当とするかの違いだと理解しています。これはP/Lに表れる利益の厚薄の差からも読み取れます。
私は、役職員を「会社に人生の時間を投資しているオーナー」と捉え、配当的な意味合いも含めて賞与で還元しています。その結果として労働分配率は高めなのですが、ワンストップファームとして規模が拡大する中ではむしろ自然な形かなと思っています。高すぎても未来への投資余力や強固な財務基盤を確保できないので、バランスを取りながら経営を行うことが重要であるのは言うまでもありません。明確な指標がないものの極めて大切なこのポイントについて、経営者としての感度を常に研ぎ澄ましていきたいと思います。
社内アピールのすすめ
- 2025.09.01
- ビジネスの話
社内アピールは個人的に組織で活躍するためには結構大事だなと昔から思っていることの1つです。日本人は一般的に自己アピールが得意ではないと言われます。
まず、欧米の企業ではリストラが当たり前の環境であり、もちろん業務で成果を上げてリストラ対象にならないよう努力することは大前提ですが、もう一つ重要な点があると聞きます。それは「上席に覚えてもらうために自分を売り込むこと」です。外部に営業するように、内部でも営業する…そうした発想です。 仮に会社がどうしても一人だけリストラをせざるを得ない状況で、能力が同程度のメンバーが並んでいた場合、日頃の印象や記憶に残っているかどうかで判断が分かれる…というのが人間の性とも言えます。もちろん全ての欧米企業に当てはまるわけではありません。
一方で、日本企業ではリストラはめったにありませんのでこの点が軽視されがちだと感じます。ただリストラに限らずで、どんなに公平な人事制度を取り入れたとしても、最後評価するのはAIではなく人ですので、昇格という観点でも重要なことのように思います。
私自身も監査法人時代に特別なことをしていたわけではありません。強いて挙げるなら、日々遅くまで働いたり事務所で残って勉強して、上司や先輩、時には代表社員から夕食に誘われれば必ず参加していた程度でしょうか。もっとも、今の時代は「飲みに行こう」と気軽に声を掛けにくくなっているので、そういう風景も見られないのかもしれません。最近になってちょっとしたきっかけではあるのですか、若手を含む何人かから、声を掛けてもらったりチャットで連絡をもらったりすることがあり、やはりとても嬉しいです…人間ですもの。そうしたやり取りは、やはり記憶に残るものだと実感します。だからこそ、何気ないやり取りや小さなつながりが、思っている以上に後々のかたちに影響していくのかもしれません。