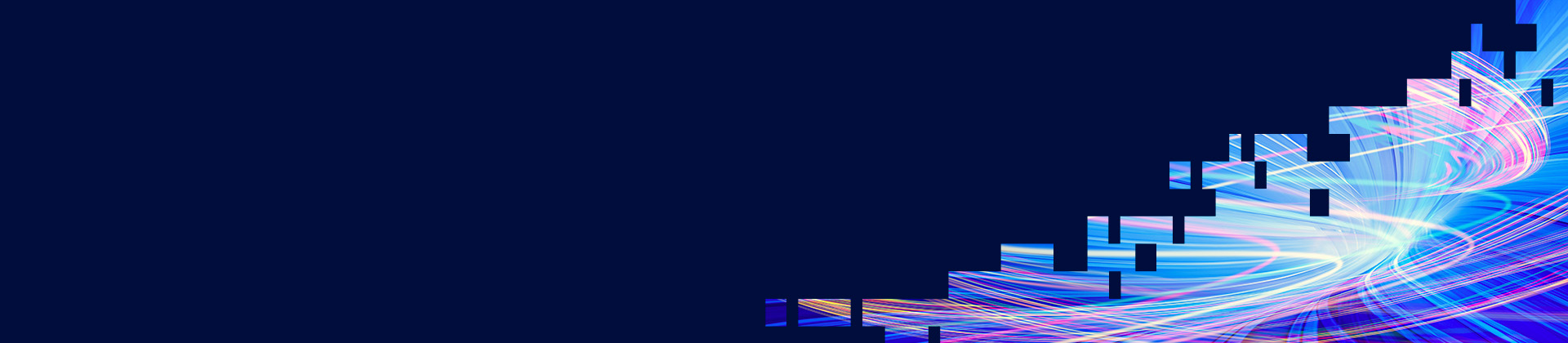就職氷河期の監査法人、内定の記憶
- 2025.12.22
- ビジネスの話
Big4監査法人の内定に関する投稿が話題になる季節になりましたね。内定を得た方々の喜びのニュースを目にするたび、昔を思い出します。
私の場合は、合格発表日と内定日がまさかの同じ日。人生でとてつもなく大きな出来事が重なった一日でした。とにかく嬉しくて、今思えばずいぶん浮かれていた気がします。当時SNSがなくてよかったかもしれません(笑)。
2003年は、監査法人の就職氷河期でした。年齢が少し上、就職活動のスタートが少し遅い、ただそれだけで全体の約2割が大手監査法人に進めなかった、そんな時代です。そんな中で私は本当に幸運だったと思います。
履歴書を2枚書き、SとCの監査法人に持って行くつもりで朝一番で面接会場に向かいました。Sの面接会場に滑り込み、列に並び、面接までたどり着きました。最後に面接官のパートナーからこう聞かれました。
「他は受けるの?」
「このあとC監査法人に行きます」と、田舎から出てきた私が正直に答えた瞬間、返ってきた言葉は衝撃的でした。
「じゃあ、ここで内定を出すから、そっちは行かなくていいかな?」
私は「はい、もちろんです!」と、反射的に答えていました。
記憶の片隅にあるのは、やけに仰々しいぶ厚い紙の内定通知書です。そこに書かれていた月額給与は305,000円(大都市手当込)。社会に出る前の自分には、現実味のない数字でしたが、ただただ幸せの絶頂でした。
そんな経験があるからでしょうか。私は今でも「内定は、できるだけ早く出してあげたい」と思ってしまいます。あのときの安堵や高揚感は、22年経った今もどこかに残っているのかもしれません。
あまりにも内定を急いで出すと、「この事務所は大丈夫なのか?」「深く検討していないのではないか?」「相当人手不足なのか?」と思われるかもしれないので、最近は弊社もしっかり対応しているようです(笑)。
だからこそ、候補者の安心と納得を何より大切にしつつ、「早く伝えるべきことは早く伝える」採用で、出会ったご縁を丁寧につないでいきたいと思います。

活躍する人に共通する、感覚のバランス
一定規模以上の事務所の代表と話すと、皆さん本当に、人望や人間力、信義則、そして何よりバランス感覚を備えていると感じます。最近ご一緒させていただいている先生方も例外なく魅力的で、学ぶことが多く、できることならずっとご一緒したいと思うほどです。
その延長で思うのが、会計士CEOや会計士CFOの皆さまが活躍されている理由です。並外れた士業としての能力というより、ビジネスマンとしての総合力と感覚のバランスが際立っている。ここが大きな差を生んでいるように見えます。
何事にも両方の側面があります。10点取っても11点取られれば試合に負ける。勝ちにいくとは、どこか一つを突出させるだけでなく、全体の最適を見て配分できることでもあります。そうしたバランス感覚は、組織においても個人においても重要な要素だと思います。
同じことは、対人関係やビジネスの現場でも当てはまります。権利主張が強すぎると、長期的な信頼関係を築くうえでは不利に働くことがある。二者間において、それが個人同士であっても、法人と個人であっても、良好な関係を長続きさせるには、ギブ・アンド・テイクの精神とバランス感覚が欠かせません。
監査法人の世界でも、この傾向はよりはっきりしてきたように思います。昔は一芸に秀でた人でもパートナーになれましたが、今は総合力が求められ、優れた感覚バランスを持っている人でないと昇進が難しい時代です。加えて英語力や人格まで求められる。だからこそ、仕事でBig4の若いパートナーに会うと、自然と尊敬の眼差しになります。
一芸の鋭さにバランス感覚が加わることで、ビジネスマンとしての総合力が増し、信頼が長続きしていくのだと思います。

日本国籍取得を選んだアレックス・ラミレス氏とのご縁
- 2025.12.03
- IR・メディア・お知らせ
RSM汐留パートナーズ行政書士法人(当時:行政書士法人中井イミグレーションサービス)は、2018年に、元プロ野球選手・監督として日本で広く知られるアレックス・ラミレス氏の日本国籍取得(帰化)手続きに関わるご縁をいただきました。
ラミレス氏はベネズエラ出身で、日本プロ野球(NPB)で長年プレーし、日本通算2,000本安打を達成した唯一の外国人選手として名球会入りしたほか、2度のMVP受賞や多数のタイトル獲得、8年連続シーズン100打点超えという記録を残すなど、NPBの歴史に名を刻んできた方です。2023年には野球殿堂入りも果たされ、日本野球史に残る実績を持つ人物です。
選手・監督として日本のファンに長く親しまれ、日本をこれからも活動の中心としたいという強い想いから、同氏は日本国籍の取得を選択され、当社が帰化許可申請のサポートを行いました。
RSM汐留パートナーズ行政書士法人では、これまでもプロスポーツやエンターテインメントの世界で活躍される方、専門職や企業経営に携わる方、留学生や難民の方々など、多様な背景を持つ方々の在留資格・永住・帰化に関わってきました。
その中でも、ラミレス氏の日本国籍取得は、「日本で新たな人生のステージを築きたい」という願いに法的・行政手続きの側面から寄り添う過程を通じて、私たち自身も多くの学びを得た印象深い事例の一つです。
こうしたご縁をきっかけに、今後も、国籍取得(帰化)、在留資格(ビザ)、永住許可といった選択を前にした方々に対し、必要な情報をわかりやすくお伝えしながら、不安を少しでも和らげられる存在でありたいと考えています。
参考リンク: https://shiodome.co.jp/news/47333/

大企業だけの課題ではないESG
- 2025.11.20
- ビジネスの話
海外の会議に参加しているとつくづく痛感しますが、ESGはもう大企業だけの宿題ではありません。2050年のネットゼロに向けた規制強化、AASB S1/S2の施行などを背景に、静かに、しかし確実に中堅・中小企業にもその波が来ています。
国際会議でも必ず出てくるキーワードが Scope 3です。サプライヤーを含むバリューチェーン全体の排出量のことであり、大企業が削減を進めるとき、取引先の環境データが必須情報になりつつある、という状況を各国で見聞きします。結局Scope1・2だけでは削減効果には限界があるという認識が広がっているのです。
ESG対応が遅れると、世界ではすでにこんなことが起きているようです。
- 大手クライアントから声がかからなくなる
- 入札で、ESGの一項目だけで落ちる
- 環境配慮型の取引先に選択が偏る
こうした話を、RSMファームのパートナーが口をそろえて語っていました。まだ日本ではそこまで実感はないのですが、確実にその兆しは見え始めています。
世界の潮流を見ると、早い段階でESGに着手した企業ほど選ばれるとのこと。難しく考え過ぎず小さく始めるだけで大きな差がつく分野となっています。私たちはESG・サステナビリティ支援を行っていますが、これから自社の情報開示にも努めてまいります。

プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE 所属「レバンガ北海道」とコーポレートサポートパートナー契約締結のお知らせ
- 2025.11.10
- 公認会計士・税理士, いい話・格言・理念, ビジネスの話, IR・メディア・お知らせ
2025年11月10日、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「レバンガ北海道」と、RSM汐留パートナーズ株式会社は、コーポレートサポートパートナー契約を締結しました。
昨日は札幌でホームゲームを観戦し、現場の熱量を肌で感じることができました。
RSM汐留パートナーズは“専門性で支えるスポンサー”という新しいモデルの確立を目指します。単なる協賛にとどまらず、バックオフィス面からクラブ運営の土台に寄り添います。会計・税務、人事・労務、法務、内部統制、ESGなど、当社の強みを生かした支援により、選手・スタッフが競技に専念できる環境づくりを後押しします。
これらの取り組みを通じて、運営効率の向上とクラブの持続的成長を実現し、「経営×人(選手・スタッフ)」を起点とするパートナーシップを推進してまいります。
Webサイト:https://shiodome.co.jp/news/46977/

資格がなくても士業事務所で輝ける
- 2025.11.01
- ビジネスの話
資格がなくても士業事務所で輝ける。私は、すでにそういう時代になったと考えています。かつて税理士事務所では「税理士以外は修行の身」といった時代もありましたが、いまは当時の何十倍も活躍のチャンスがあります。つまり、士業だから安泰という考えはもはや通用しなくなりつつもあります。
これからの時代に求められるのは、資格だけではなく「考える力」と「巻き込む力」だと感じます。最近は「ホワイトワーカーがAIに代替され、ブルーカラーの時代に…」といったニュースも目にしますが、個人的にはテスラのヒト型ロボットOptimus(オプティマス)を見ると、どちらも同じくらい危ういとも思います笑
士業事務所が組織として成長すれば、もはやそれは一つの事業会社として社会に貢献できる存在になりますし、実際その動きはすでに広がっています。問われているのは、資格の有無に関わらず、自分の得意分野をどう生かすか、どんな形で価値を生み出せるかです。
私は士業ではない方々にも積極的にこの業界に入ってきていただきたいと考えています。士業が持つ国家資格や社会的信頼を、より高い価値のビジネスとして社会に提供していく。そうした新しい挑戦を共に進めていけたら嬉しいです。
士業の独占業務等にとらわれず、枠を超えて多様な仲間とともに成長していく…そんな魅力ある世界を一緒につくっていきたいです。

立場が上がるほどに求められる自律と責任
組織においては、上に立つ人ほど厳しい言葉を受け止め、自らを律し、お手本にならなければなりません。立場が上がるというのは自由になることではなく、むしろ制約が増え、自己管理がより求められることを意味します。
独立した当初は一人で本当に自由でしたが、今はある意味で不自由です。色々な制約がありますし、Xもいつかはやめなければならない日が来るかもしれません(笑)。パートナーや取締役、執行役員に対して「ここは改善すべきだ」と愛を持って伝え続ける日々は、楽なものではありません。もちろん私自身ができていないことも多々あるのですが。
一方で、新しく入ったメンバーは大切に育てられるべき存在です。入社して間もない数年間は、ある意味守られる立場にあります。ただ、その状況に甘えるのではなく、できるだけ早く自立し、成長していくことが求められます。信頼関係がまだ十分にできていないうちは、当たり障りのない会話が中心になります。そのためか、私もその頃は仏のように優しいと自分で感じることすらあります。しかし関係が深まるにつれて、愛を持って厳しい指摘をせざるを得ない場面が増えます。たとえば知識や準備の不足を指摘したり、努力の必要性を伝えたりすることです。時に耳の痛い言葉になるかもしれませんが、成長を願っているからこそです。
ここを取り違えて、上席には甘く、下のメンバーには厳しい組織をつくってしまうと、不満が溜まりやすくなり長続きしません。「あの人は可愛がられて出世している」といった声が出てくるのは、健全な組織ではありません。どうしてもそう見えてしまうことはありがちですが。少なくとも弊社の場合、上席の立場は決して楽ではありません。無数の期限なき(常にASAPな)課題に追われ、体力的にもハードな出張や会食をこなしながら、それでもなお自己研鑽を求められ続ける…そんな毎日です。知識・経験・ノウハウを、体力と精神力を伴って提供し続けるのは容易なことではありません。それでも、この挑戦こそが仕事の醍醐味であり、私にとってはワクワクを感じる瞬間でもあります。
最近は「若い人が上を目指さなくなった」「競争に負けても悔しさを感じにくくなった」といった話を耳にすることもあります。多様な価値観や働き方が尊重される時代なので、それ自体は別に良いことだと思います。ですが、その中でもなお「上を目指したい」と本気で思う若手がいれば、きっと会社にとってダイヤの原石です。そういう方々はおこがましいですが、全力で育てていきたいと思います。

場所に縛られない時代に、どう信頼と成果を築くか
- 2025.10.10
- ビジネスの話
もし自分がリモートワーク中心で管理職を目指すとしたら――そんなことを考えてみました。一般の企業では上席ほど仕事の責任は重いですがお給料も上がります。
私たちの会社でも、全国でリモートワーク中心に働くメンバーが増えつつあります。テクノロジーの進化により場所を問わず仕事ができる時代になりました。実際、担当として自分の職務を遂行し、数字を上げるという点では、リモートでも十分に成果を出すことが可能です。
しかし一方で、営業をしたり、提案をまとめたり、チームを率いたり、時にはクライアントに謝罪に行くといった「前に立つ仕事」を担うことは、やはりリモートだけでは難しい部分があるのも事実です。弊社でもそのような職責を担う者はまだおりません。
そうした中で「リモートだから仕方ない」と言われないためには、自ら積極的に動くことが欠かせません。そのために必要なことは、例えば次のようなことではないでしょうか。
- 社内の情報を自分から取りに行く
- 役員など上席や他部署メンバーとの接点を増やす
- 社内共通業務などの担当に立候補する
- オンラインでもカメラをオンにし表情を見せて会話する
- 雑談や非公式なコミュニケーションを大事にする
- 出張や食事会などリアルな機会を積極的に活用する
- 自分の取り組みや成果を発信して見える化する
- 上司やチームへの報連相を密に行う
- 他のメンバーのサポートや相談にも積極的に乗る
- 「呼ばれる人」ではなく「誘う人」になる
- 会社や部門の理念や方向性に自ら関心を持つ
- 成果だけでなく信頼残高を積み上げる意識を持つ
- とにかく自分を覚えてもらう!
個別に見ていくと、一見すると時代に逆行しているように思われるものもあるかもしれません。しかし、リモートだからこそ、意識して人との距離を縮める努力がより一層求められるのだと思います。ある意味では、リアルにすぐ会える環境よりも何倍も大変だと言えるでしょう。
これからは、「リモートで働けるかどうか」ではなく、「リモートでどこまで活躍できるか」が問われる時代です。そして、場所に関係なく信頼を築き、成果を出せる人こそ、次の時代において強いプロフェッショナルになるのだと感じています。

税理士法人東京クロスボーダーズとの合併についてのご報告
- 2025.10.01
- IR・メディア・お知らせ
このたび、RSM汐留パートナーズ税理士法人は、2025年10月1日付で、25年以上にわたり外資系企業をはじめとする多数のクライアントに国際税務を中心とした会計・税務サービスを提供してきた税理士法人東京クロスボーダーズと合併いたしましたので、ご報告申し上げます。そしてRSM汐留パートナーズグループは250名体制となりました。
今回の合併により、税理士法人東京クロスボーダーズが長年培ってきた経験・専門性、国際税務の確かな実績および国際ネットワークと、RSM汐留パートナーズ税理士法人の革新的ソリューションが融合し、クライアントの皆様には、より高い付加価値を備えたサービスをご提供いたします。今後もクロスボーダーで事業を展開するクライアントの皆様への支援を一層拡充し、唯一無二のワンストップサービスを提供するプロフェッショナル集団として、変化の激しい事業環境に柔軟に対応してまいる所存です。
そしてこのたび、私がRSM Japanのノンアシュアランス部門の日本代表/Managing Partnerを拝命することとなりました。私が管掌するのは被監査部門、すなわち税務・労務・法務・コンサルティング等の領域です。
RSM汐留パートナーズの250名、 RSM清和監査法人の180名、合わせて430名の仲間と共にRSM Japanのプレゼンスをさらに高め、日本のすばらしさを世界へ発信していきたいと考えています。引き続き、皆さまの温かいご支援のほどよろしくお願いいたします。

従業員数3桁以下の会社の昇格のリアルな仕組み
- 2025.09.20
- ビジネスの話
RSM汐留パートナーズでは年2回昇格のタイミングがあります。会社と個人の成長スピードが速い中で、年1回の昇格では機会が限られると考えているためです。そのため、年齢や社歴に関係なく、人によっては驚くほど速いペースで駆け上がっていきます。
経験上、私が以前所属していた大手監査法人のように、従業員が数千人の企業や社歴の長い企業では、ある程度システマティックに規定通りあがっていきます。予定より早い昇格や飛び級などもほとんどなく、トップマネジメント以外でサプライズ人事は稀です。
一方で、従業員数が3桁以下、すなわち1000人未満の会社では、もちろん評価や昇進のルールはしっかり整備されていても、やはり会社のトップマネジメントに自分のことを認知してもらうことが不可欠だと感じます。最終的に決めるのはシステムではなく「人」だからです。現実的な話になりますが、避けては通れない要素です。
弊社はもうすぐ役職員250名になろうとしているのですが、実際私もすべての昇格推薦に目を通しコメントをしています。推薦対象者についてよく知らない場合や、良い評判が私の耳に入ってこない場合は、周囲に積極的にヒアリングしています。もちろん、事業部所属であれば個人の担当売上目標金額の達成なども大切なのですが、それだけではありません。間接業務を含め会社の運営にどの程度貢献しているか、今後も貢献できるポテンシャルがあるか、他事業部にも興味を持っているか、時間外に自己研鑽の習慣があるか(資格や語学の習得に限らず)といった点も重視しています。
最近は昇格よりもワークライフバランスを重視する方も増えているように感じますが、社員数1000人未満の会社で昇格・昇進を目指す成長意欲や挑戦心を持った方にとっては、その挑戦を後押しする場であり続けることが大切だと考えます。