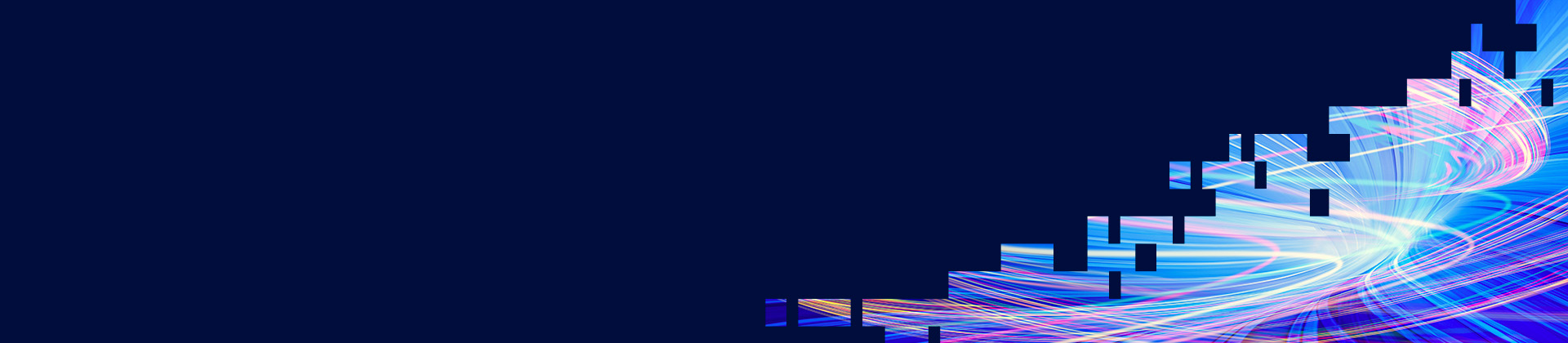活躍する人に共通する、感覚のバランス
一定規模以上の事務所の代表と話すと、皆さん本当に、人望や人間力、信義則、そして何よりバランス感覚を備えていると感じます。最近ご一緒させていただいている先生方も例外なく魅力的で、学ぶことが多く、できることならずっとご一緒したいと思うほどです。
その延長で思うのが、会計士CEOや会計士CFOの皆さまが活躍されている理由です。並外れた士業としての能力というより、ビジネスマンとしての総合力と感覚のバランスが際立っている。ここが大きな差を生んでいるように見えます。
何事にも両方の側面があります。10点取っても11点取られれば試合に負ける。勝ちにいくとは、どこか一つを突出させるだけでなく、全体の最適を見て配分できることでもあります。そうしたバランス感覚は、組織においても個人においても重要な要素だと思います。
同じことは、対人関係やビジネスの現場でも当てはまります。権利主張が強すぎると、長期的な信頼関係を築くうえでは不利に働くことがある。二者間において、それが個人同士であっても、法人と個人であっても、良好な関係を長続きさせるには、ギブ・アンド・テイクの精神とバランス感覚が欠かせません。
監査法人の世界でも、この傾向はよりはっきりしてきたように思います。昔は一芸に秀でた人でもパートナーになれましたが、今は総合力が求められ、優れた感覚バランスを持っている人でないと昇進が難しい時代です。加えて英語力や人格まで求められる。だからこそ、仕事でBig4の若いパートナーに会うと、自然と尊敬の眼差しになります。
一芸の鋭さにバランス感覚が加わることで、ビジネスマンとしての総合力が増し、信頼が長続きしていくのだと思います。

プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE 所属「レバンガ北海道」とコーポレートサポートパートナー契約締結のお知らせ
- 2025.11.10
- 公認会計士・税理士, いい話・格言・理念, ビジネスの話, IR・メディア・お知らせ
2025年11月10日、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「レバンガ北海道」と、RSM汐留パートナーズ株式会社は、コーポレートサポートパートナー契約を締結しました。
昨日は札幌でホームゲームを観戦し、現場の熱量を肌で感じることができました。
RSM汐留パートナーズは“専門性で支えるスポンサー”という新しいモデルの確立を目指します。単なる協賛にとどまらず、バックオフィス面からクラブ運営の土台に寄り添います。会計・税務、人事・労務、法務、内部統制、ESGなど、当社の強みを生かした支援により、選手・スタッフが競技に専念できる環境づくりを後押しします。
これらの取り組みを通じて、運営効率の向上とクラブの持続的成長を実現し、「経営×人(選手・スタッフ)」を起点とするパートナーシップを推進してまいります。
Webサイト:https://shiodome.co.jp/news/46977/

労働分配率から考える経営の姿
- 2025.09.10
- 公認会計士・税理士, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話
税理士法人の経営者同士の勉強会では、労働分配率が話題にのぼることが多くあります。その際、税理士法人によって代表者の報酬の多寡が大きく異なるため、労働分配率(社会保険料・賞与を含み、代表者報酬は含まない)がよく話題になります。
規模にもよりますが、100人以上の事務所で考えると、理想は50〜60%程度とされているように感じるのですが、弊社の連結ベースでは代表者報酬も含め65%ほどという感覚です。それでも高すぎるとは感じていませんが、税理士法人全体で見ればどうも高い方に位置されるように感じます(私の代表者報酬が高いということはございません笑)。
この点について実はずっともやもやしていました。このもやもやについて、Big4監査法人の損益計算書(P/L)を眺めて電卓を叩き労働分配率を計算し、遅ればせながら自分の中で整理がついてきまして、霧が晴れてきました。日本のBig4監査法人の労働分配率(2023/24期、パートナー役員報酬含む)は62〜74%ほどです。この差は、パートナーの取り分が役員報酬とされてP/Lの販管費に含めているのか、税引後当期純利益からの配当とするかの違いだと理解しています。これはP/Lに表れる利益の厚薄の差からも読み取れます。
私は、役職員を「会社に人生の時間を投資しているオーナー」と捉え、配当的な意味合いも含めて賞与で還元しています。その結果として労働分配率は高めなのですが、ワンストップファームとして規模が拡大する中ではむしろ自然な形かなと思っています。高すぎても未来への投資余力や強固な財務基盤を確保できないので、バランスを取りながら経営を行うことが重要であるのは言うまでもありません。明確な指標がないものの極めて大切なこのポイントについて、経営者としての感度を常に研ぎ澄ましていきたいと思います。
小さな時間の積み重ねが大きな成果を生む
小さな時間の積み重ねが大きな成果を生みます。そして時間の使い方を見直すだけで驚くほどの変化が起こります。「忙しい」は理由になりません。「成果を上げる人は重要なことに集中する。本質的な課題に力を注ぐことで結果を出す」というドラッカーの言葉もあります。
また、何か成し遂げるためには一定のハードワークが必要だと考えています。この「ハードワーク」の意味ですが、ただ長い時間働くということではなさそうです。仕事や関係する趣味等も含め楽しむことができたなら、疲れも軽減されるとともに、情報収集や人脈形成も相まって大きな成果に結びつきます。
さらに、仕事の熱量が高いほど生活満足度向上に繋がったり、幸福度が高いほど様々な事柄の成果が出ると言うのには納得感があります。日本でもこれまで以上に幸福経営を取り入れていくことが求められると感じます。
そして、もっとDEI(Diversity, Equity & Inclusion)が進んでいく会社にしたいなと思っています。そのために”自己開示する力”が重要だし一方周りにもそれを受け入れる”寛容さ”が必要だと思います。お互いを”理解”することって大切で、例え”理解”できなくても”認識”し合うことだけでも一歩前進します。心理的安全性が高いコミュニティでは1人1人が大きな力を発揮でき、結果として組織の成果も非常に大きくなります。
一人ひとりが自分らしさと情熱を持って行動し、互いを尊重し合える環境を築くことが、持続的な成長と真の成果への最短ルートになるのだと思います。

課外活動のすすめ
Big4の監査法人にいると、自分次第ですが課外活動のチャンスはたくさんあります。最近は皆忙しすぎてそれどころではないのよと言われてしまいそうですが…。
その監査法人にずっと勤めるかどうかはさておき、公認会計士として30-40年以上の長いキャリアを歩む中で、先輩・同期・後輩・顧客との関係を良好に保つことは本当に重要です。
なぜなら、思っている以上にこの業界は狭いからです。公認会計士は間に1人入るとほぼ皆繋がっているとよく言われます。もちろん、海外にまで目を向ければ広い世界ですから、多少国内でこじらせても海外に出ちゃえば大丈夫かもしれませんが。
大手監査法人の名刺を持っているうちは絶好のチャンスです。たとえ準会員であっても名刺一つで軽んじられることはないでしょうし、銀行・証券会社・VC・PEファンド・弁護士・税理士・医師など、さまざまな分野のプロフェッショナルと接点を持てる可能性が一気に広がります。
いずれにせよ、皆が求めているのは長く信頼できる付き合いだと思います。だからこそこの環境を最大限に活かして、良い関係性を構築していくことが、将来の成功に繋がります。監査法人の最初の5年10年の努力でその後も楽にいけるとまでは言いませんが、必ず役に立つと思います。
本業だけでなく、人脈づくりや異業種との交流など、名刺一枚で広がる世界があります。飲み会の幹事を努めるなどもおすすめです。この業界はシャイな人も多いかもしれませんが、どなたかの参考になれば幸いです。

【AI→AGI時代と士業事務所の生き残り】
AIは既に会計・監査・税務・人事・労務・法務などの領域でとても浸透してきていますが、今後数年で登場するかもしれないAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)は、我々士業、例えば公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの仕事を根底から変える存在になりそうです。
今のAIは、データ分析、帳簿記帳、税額計算、給与計算、社会保険手続きなど、定型業務を高速で処理する特化型AIです。これでもインパクトは大きいのですが、これから海外で台頭してきそうなAGIというものは
- 法改正を自動ですべてリアルタイムでキャッチアップし
- 顧問先の過去の決算や業種特性を踏まえて
- 最適な組織体系、節税対策、人事制度設計などをどんどん提案し
- 状況に応じて説明のトーンや言語まで自由自在に調整できる…
つまり、士業事務所の中堅からベテラン職員レベルの判断や提案までもを、当然ながら24時間365日休まず行う存在になります。
これにより、例えば
- 会計帳簿・決算書・申告書のレビュー
- 雇用契約書や就業規則をはじめとする規程のドラフト作成
- 日本進出企業や海外進出企業への多言語支援
- 世界中の法制度を理解した上で最適な各種提案
- グループ内組織再編の設計など
従来専門家がやるべきとされてきた領域もますますAGIがカバーしていきます。業法とライセンスの問題はありますが。AGIについて引き続きものすごい脅威を感じながらも、ビジネスにうまく活用できればチャンスになりそうです。
その先にはASI(Artificial Super Intelligence:超人工知能)もあるようで、個人的にはとてもワクワクしています。こういう情報について海外から早めに得られるようになっているのは私にとって大きいです。
結局のところAI台頭時代においても言われますが、柔軟にこれらを使いこなせるスキル、創造力やコミュニケーション能力、体力や精神力(やりきる力)など、人間力・人間的な魅力のある者以外は活躍が難しくなるということだと理解しています。
AIの進化を脅威として恐れるのではなく、柔軟に受け入れ活用し、人間ならではの力を磨き続けることこそが、これからの士業に求められる姿勢だと強く感じています。

ESG・サステナビリティサービスのローンチのお知らせ
- 2025.05.20
- 公認会計士・税理士, ビジネスの話, IR・メディア・お知らせ
英国をはじめとしたヨーロッパや米国では、持続可能性やESGに関連し、大学院でMBAを取得する人が増加しているようです。また、会計業界からESG・サステナビリティの分野へ転向する専門家が増えている気がします。
ESGやサステナビリティを学ぶことは、短期的な利益や報酬には直結しないかもしれません。でも、視野を広げ、長期的な成長につながる大切な学びだと感じています。自分自身もまだ学びの途中ですが、そして米国は混沌としていますが…これからの時代のビジネスで引き続き必要な視点だと思います。
ESG領域はもはや公認会計士の専門とする領域とはかなり異なるのですが、数値集計のプロセス構築や妥当性の保証に関しては公認会計士が得意とします。日本では圧倒的に人材不足ですがグローバル化の流れもあり、5年後には大きなマーケットになっていると感じます。
このような経緯から、弊社ではESG・サステナビリティサービスの提供を開始しました。2050年のカーボンニュートラルと次世代のウェルビーイングの実現に向け、温室効果ガスの蓄積による気温上昇や生物多様性の喪失などで低下したレジリエンスを、クライアントとともに取り戻すことができればと思います。
ESG・サステナビリティサービス | RSM汐留パートナーズ

仙台事務所開設
- 2025.05.01
- 公認会計士・税理士, IR・メディア・お知らせ
このたび、RSM汐留パートナーズ株式会社は2025年5月1日付で仙台事務所を開設いたしました。新拠点はアクセス性や利便性に優れた仙台駅近くのエリアに構えており、今後の業務拡大に向けた重要な第一歩となります。
当面は大阪や福岡と同様、コワーキングスペースを拠点とした柔軟な運営形態でのスタートとなりますが、東北エリアでの採用状況や業務ニーズを踏まえ、必要に応じてオフィス形態の見直しも検討してまいります。
仙台事務所の立ち上げを機に、東北地域の皆さまとともに、首都圏および海外クライアントへの支援体制をさらに強化していく所存です。今後は会計税務・コンサルティング分野の人材採用にも注力し、仙台からグローバルに挑戦したい方の応募も歓迎いたします。
引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
https://shiodome.co.jp/sendai/

DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン )
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の理解が進む中で”寛容”である事はとても大切。日本は島国で長らく多様性に乏しかったですが寛容さはずっと有してきたのではと思います。私も自分とは異なる意見や価値観を拒まず理解していきたいなと思っています。一方で、日本では人種という視点はほとんどなく、DE&Iにおいてはジェンダーや障がい者に関するテーマが多いです。
目から入る情報はとても多いですが必ずしもそれが正しいとは限らず、バイアスを作り出したり考えを固めてしまうこともあります。色々なものに触れて無知を減らしていくことがDE&Iへの取り組みの第一歩かなと思います。
人はつい似たような仲間と集まりがちですが、バックグラウンドや所属が異なる仲間と話すことで新たな気付きが得られます。それがダイバーシティであり、ワンストップファームの強みだと感じるので、横の連携や交流を楽しみたいと思います。確かに同質性の高い人達といると心地よいのですが、それが良い結果に繋がるとは限らないと認識しています。異なるバックグラウンドや考え方を持つ方といると、衝突したり議論する事も多いかもしれませんが、良い結果に結び付く可能性に期待したいと思います。
弊社には中国圏出身の社員も在籍しており、大阪オフィスでは日本人、中国人、ベルギー人がともに働いています。標準語、関西弁、英語が飛び交う多様な環境です。また、女性の有資格者も少しずつ増えており、さまざまな部署で女性が主導する企画や、女性が中心となってまとめるプロジェクトが目覚ましい成果を上げています。会社全体が着実に変化していることを実感しています。
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)にもっと取り組むことで、何かイノベーションが起こるなど、素晴らしい結果につながると確信しています。

EQ(感情知能)
「IQ」の他に「EQ(心の知能指数)」という概念があります。ビジネスにおいては両方とも重要であることを認識しておく必要があります。RSMに入りネットワーク内で情報収集していると、同じようにEQを大切にしている様子が伺えます。人間のIQが高くてもAIにはかなわない部分があることに加え、自らが商品でありサービス業でもあるので、私達の業界はEQの高さが勝敗を分けるのかもしれません。IQが高そうですごく頭が良い人がビジネスで成功するとは限りません。「理と情」という表現もありますが、両方が必要だからこそ皆にチャンスがあり面白いですね。
このように、EQ(感情知能) やソフトスキルというものがとても重要な時代になっていると感じています。そしてそれらは決して先天的なものではなく、学ぶことにより高めていけるものと確信しています。世の中にそのような学びの機会は溢れているかもしれませんが、より良いものを選び皆で学んでいきたいと思います。
一方で、EQ(感情知能)が低い人を組織の上席に据えるのは危険です。マネジメントやリーダーシップにおいて、EQは非常に重要な要素です。人との信頼関係を築き、チームを導くためには、共感力や自己開示が欠かせません。もしそのような役割を目指したいのであれば、EQを高めることは避けて通れないと感じます。
心理学者のダニエル・ゴールマンがEQ(感情知能)を構成する5要素を提唱しています。
- 自己認識
- 自己抑制
- 動機付け
- 共感性
- ソーシャル・スキル
管理者の能力差のほぼ9割はIQではなくEQにあるとか。組織のリーダーが上記を有していないとチームは良い成果を出せません。
さらに、IQ(知能指数)やEQ(感情指数) だけでなく、SQ(社会的指数)やCQ(好奇心指数)、TQ(テクノロジー指数)やAQ(逆境指数) なども求められることが多くなっています。1つ言えることは、IQだけ高く頭がよい人が活躍する訳ではないということ。人間らしくいることが大切ですね。特に士業では、スペシャリストでありながらゼネラリストを目指すというのも1つの生き方かなと思います。