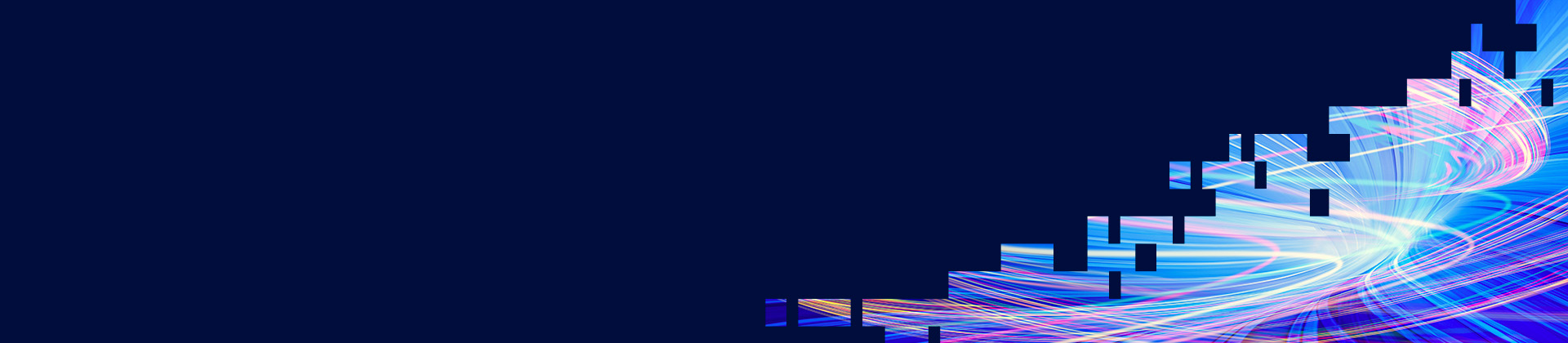「自由と責任」を両立させる、自律型組織のためのハイブリッドワーク
- 2026.02.01
- ビジネスの話
「リモートワーク」という言葉が世に出て久しい昨今、私は「ハイブリッドワーク」には多大なメリットがあると考え、一貫してその体制を推進しています。
具体的には、ハイブリッドワークには以下の8つの利点があると考えています。
①自宅とオフィスの利点を状況に応じて選択できる
②通勤時間を削減し、集中しやすい環境を確保することで業務効率を高める
③対面が必要な局面でチームが集まり、密なコミュニケーションを図る
④仕事と私生活の調和を図りやすい
⑤居住地に縛られず、広範な地域から優秀な人材を確保できる
⑥高い自己管理能力が求められ、主体的な働き方が促進される
⑦オフィス維持費を抑制し、成長分野への投資に充当できる
⑧地方創生に寄与し、多様な地域との繋がりを強化できる
現在は東京のほかに、札幌、釧路、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄と拠点があり、フルリモートのメンバーも多く在籍しています。ハイブリッドワークの良さをさらに引き出すため、今後もさらに全国に拠点を拡充していく計画です。
ただし、この働き方において「自由と責任」は表裏一体です。メンバー一人一人が数値を含む成果に対して明確な責任を持つこと、そして行動指針(フィロソフィ)が組織に深く浸透していることが不可欠です。決して楽な道ではありません。
私自身、創業から今に至るまでずっと役員としてこのハイブリッドな働き方を実践し続けてきました。タフな制度ではありますが、自走できる人材にとってはこれ以上ない環境であり、今後もこの体制をさらに磨き上げ、推進していく所存です。

進む会計事務所の二極化。生き残るための「規模」と「責任」の再定義
- 2026.01.30
- ビジネスの話
会計事務所業界の変化は凄まじく、正直なところ先行きは不透明です。この不確実性の高い時代においては、「雇用を最小限に抑えた個人事務所」か「規模を徹底的に拡大する大規模事務所」か、その二極化が加速していくように感じます。
PEファンドや上場企業などの資本参入を肌で感じる今、小規模な事務所が職員の雇用を守り続けるのは、もはや容易なことではありません。「もし私がもう一度独立するなら、雇用を限りなくゼロに近づけた少数精鋭でやる」と公言している理由は、まさにそこにあります。
ただ、これはあくまで私の「来世」の話。現実の私は、しっかりと規模拡大を図り、大切な仲間たちの雇用を守る責務を負っています。しばらく忘れていたようなプレッシャーを再び感じ始めていますが、これは自分自身でかけている期待の裏返しかもしれません。
AIに仕事が奪われるといった短絡的な懸念はしていません。しかし、外部環境が激変することだけは確実です。監査法人、税理士法人、そして全ての士業事務所。この不確実極まる5年間で、経営者としての真価が問われることになるでしょう。
変化は望むところ。不確実な未来を、最高の仲間たちと切り拓いていくことに、これ以上の喜びはありません。

女性が「組織の顔」として輝く会計の世界へ
- 2026.01.20
- ビジネスの話
国際会議に足を運ぶと、大手組織のパートナーや代表が女性であることは、今や世界では珍しいことではありません。日本初の女性首相が誕生し、社会のあり方が大きく変わろうとしている今、会計士(JCPA/USCPA)のキャリアについて改めて考えてみました。
日本では依然として男性比率の高い会計業界ですが、世界に目を向ければ女性が第一線で活躍している国は数多く存在します。特に英語を武器にできる女性会計士は、キャリアの選択肢を劇的に広げることが可能です。
1.「英語×専門性」が生む高い付加価値
国際税務、海外進出支援、国際監査といった英語を要する案件は、専門性が高く、それに比例して報酬水準も上がります。特にスピーキングやリスニングのスキルがあれば、国内案件では出会えないようなグローバルなプロジェクトに携わることができます。
2.「公私のバランス」を尊重するグローバルな職場文化
欧米の会計業界では、ワークライフバランスを重視する文化が根付いています。リモートワークでも成果で正当に評価されるため、ライフステージの変化に柔軟に対応しながらキャリアを継続できます。英語ができれば、日本にいながらにしてこうしたグローバル基準の働き方を享受できるチャンスが広がります。
3.語学への適応力という強み
言語学の研究によれば、音声や語彙の記憶といった言語習得において、女性は高い適応力を示す傾向があると言われています(例:英国ケンブリッジ大学言語学部の研究では、言語習得における「音声・語彙記憶」の面で女性が優位という結果)。この潜在的な強みは、グローバルに活躍する上で大きなアドバンテージとなります。
4.リーダーとして輝く世界の女性会計士たち
米国公認会計士協会(AICPA)の統計では、女性のパートナー・ディレクター比率は約30%に達します。英国勅許会計士協会(ICAEW)でもメンバーの半数近くが女性であり、管理職登用も一般的です。「専門性×英語」という両輪を持てば、日本においても同様のキャリアパスは確実に拓けるはずです。
英語は、女性会計士にとって可能性を最大化させる最強の味方です。働く場所、関わる人、そして報酬。それらを自分の意志で選択し、自由な生き方を手にする。世界で活躍するリーダーたちのように、日本でも「会計×英語」を武器に輝く女性がますます増えていくことを確信しています。
日本の会計業界が、多様な個性がより自由に、より力強く羽ばたける場となることを願ってやみません。

2026年仕事始め:プロフェッショナルサービスファームとしての生存戦略
- 2026.01.05
- ビジネスの話
本日が仕事始めです。政治やビジネス環境の不確実性が加速する中、「いかに生き残るか」は経営者にとって避けて通れない命題です。2026年のスタートにあたり、改めて私たちの在り方について整理してみました。
私なりに考え得る生存戦略の方向性は、大きく分けて以下の3つに集約されます。
①政治の世界に参入し、ルール形成に関与する
②大資本の企業グループ傘下に入り、庇護を受ける
③社会の変化に左右されない「不変の構造」を構築する
①と②は、自らが「ルールを作る側」に回るか「強者のルールに適応する側」に回るかの選択であり、有力な手段ではあります。しかし、中堅企業の経営者である私にとって、現時点で最も追求すべきは③であると考えます。この「構造による耐性」を学ぶべく、この2年間はMBAで集中的にインプットを続けてきました。
重要なのは、単なる保守的な「守り」ではなく、株価、為替、地政学リスク、技術革新といったあらゆる変数がどう動いても揺るがない設計です。
- 影響を極力受けない仕組み(リスクの極小化)
- 影響を受けても他要素で相殺できる仕組み(ポートフォリオの分散)
- 変化をむしろ追い風に変える仕組み(レジリエンスの強化)
例えば、1ドル=250円という極端な円安下でも外貨収入で中立化を図る、あるいは特定の地域に依存せず地政学リスクを分散するといった「事業上の多角化」です。これは単なる経営戦略ではなく、従業員の雇用を守るという経営者としての「責務」であると考えています。
短期的な合理性だけを追うのではなく、環境が激変しても「この会社は生き残る」と言い切れる状態をつくること。人材流動化が進む現代において、こうした「大家族経営」的な発想は古く見えるかもしれません。しかし、長期で人を預かる覚悟なしに、持続可能な組織は成り立たないと信じています。
プロフェッショナルサービスファームとして変化し続ける世界に必要とされ続けるために、2026年も広い視野を持ち、思考を止めることなく邁進してまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

就職氷河期の監査法人、内定の記憶
- 2025.12.22
- ビジネスの話
Big4監査法人の内定に関する投稿が話題になる季節になりましたね。内定を得た方々の喜びのニュースを目にするたび、昔を思い出します。
私の場合は、合格発表日と内定日がまさかの同じ日。人生でとてつもなく大きな出来事が重なった一日でした。とにかく嬉しくて、今思えばずいぶん浮かれていた気がします。当時SNSがなくてよかったかもしれません(笑)。
2003年は、監査法人の就職氷河期でした。年齢が少し上、就職活動のスタートが少し遅い、ただそれだけで全体の約2割が大手監査法人に進めなかった、そんな時代です。そんな中で私は本当に幸運だったと思います。
履歴書を2枚書き、SとCの監査法人に持って行くつもりで朝一番で面接会場に向かいました。Sの面接会場に滑り込み、列に並び、面接までたどり着きました。最後に面接官のパートナーからこう聞かれました。
「他は受けるの?」
「このあとC監査法人に行きます」と、田舎から出てきた私が正直に答えた瞬間、返ってきた言葉は衝撃的でした。
「じゃあ、ここで内定を出すから、そっちは行かなくていいかな?」
私は「はい、もちろんです!」と、反射的に答えていました。
記憶の片隅にあるのは、やけに仰々しいぶ厚い紙の内定通知書です。そこに書かれていた月額給与は305,000円(大都市手当込)。社会に出る前の自分には、現実味のない数字でしたが、ただただ幸せの絶頂でした。
そんな経験があるからでしょうか。私は今でも「内定は、できるだけ早く出してあげたい」と思ってしまいます。あのときの安堵や高揚感は、22年経った今もどこかに残っているのかもしれません。
あまりにも内定を急いで出すと、「この事務所は大丈夫なのか?」「深く検討していないのではないか?」「相当人手不足なのか?」と思われるかもしれないので、最近は弊社もしっかり対応しているようです(笑)。
だからこそ、候補者の安心と納得を何より大切にしつつ、「早く伝えるべきことは早く伝える」採用で、出会ったご縁を丁寧につないでいきたいと思います。

活躍する人に共通する、感覚のバランス
一定規模以上の事務所の代表と話すと、皆さん本当に、人望や人間力、信義則、そして何よりバランス感覚を備えていると感じます。最近ご一緒させていただいている先生方も例外なく魅力的で、学ぶことが多く、できることならずっとご一緒したいと思うほどです。
その延長で思うのが、会計士CEOや会計士CFOの皆さまが活躍されている理由です。並外れた士業としての能力というより、ビジネスマンとしての総合力と感覚のバランスが際立っている。ここが大きな差を生んでいるように見えます。
何事にも両方の側面があります。10点取っても11点取られれば試合に負ける。勝ちにいくとは、どこか一つを突出させるだけでなく、全体の最適を見て配分できることでもあります。そうしたバランス感覚は、組織においても個人においても重要な要素だと思います。
同じことは、対人関係やビジネスの現場でも当てはまります。権利主張が強すぎると、長期的な信頼関係を築くうえでは不利に働くことがある。二者間において、それが個人同士であっても、法人と個人であっても、良好な関係を長続きさせるには、ギブ・アンド・テイクの精神とバランス感覚が欠かせません。
監査法人の世界でも、この傾向はよりはっきりしてきたように思います。昔は一芸に秀でた人でもパートナーになれましたが、今は総合力が求められ、優れた感覚バランスを持っている人でないと昇進が難しい時代です。加えて英語力や人格まで求められる。だからこそ、仕事でBig4の若いパートナーに会うと、自然と尊敬の眼差しになります。
一芸の鋭さにバランス感覚が加わることで、ビジネスマンとしての総合力が増し、信頼が長続きしていくのだと思います。

大企業だけの課題ではないESG
- 2025.11.20
- ビジネスの話
海外の会議に参加しているとつくづく痛感しますが、ESGはもう大企業だけの宿題ではありません。2050年のネットゼロに向けた規制強化、AASB S1/S2の施行などを背景に、静かに、しかし確実に中堅・中小企業にもその波が来ています。
国際会議でも必ず出てくるキーワードが Scope 3です。サプライヤーを含むバリューチェーン全体の排出量のことであり、大企業が削減を進めるとき、取引先の環境データが必須情報になりつつある、という状況を各国で見聞きします。結局Scope1・2だけでは削減効果には限界があるという認識が広がっているのです。
ESG対応が遅れると、世界ではすでにこんなことが起きているようです。
- 大手クライアントから声がかからなくなる
- 入札で、ESGの一項目だけで落ちる
- 環境配慮型の取引先に選択が偏る
こうした話を、RSMファームのパートナーが口をそろえて語っていました。まだ日本ではそこまで実感はないのですが、確実にその兆しは見え始めています。
世界の潮流を見ると、早い段階でESGに着手した企業ほど選ばれるとのこと。難しく考え過ぎず小さく始めるだけで大きな差がつく分野となっています。私たちはESG・サステナビリティ支援を行っていますが、これから自社の情報開示にも努めてまいります。

プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE 所属「レバンガ北海道」とコーポレートサポートパートナー契約締結のお知らせ
- 2025.11.10
- 公認会計士・税理士, いい話・格言・理念, ビジネスの話, IR・メディア・お知らせ
2025年11月10日、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールクラブ「レバンガ北海道」と、RSM汐留パートナーズ株式会社は、コーポレートサポートパートナー契約を締結しました。
昨日は札幌でホームゲームを観戦し、現場の熱量を肌で感じることができました。
RSM汐留パートナーズは“専門性で支えるスポンサー”という新しいモデルの確立を目指します。単なる協賛にとどまらず、バックオフィス面からクラブ運営の土台に寄り添います。会計・税務、人事・労務、法務、内部統制、ESGなど、当社の強みを生かした支援により、選手・スタッフが競技に専念できる環境づくりを後押しします。
これらの取り組みを通じて、運営効率の向上とクラブの持続的成長を実現し、「経営×人(選手・スタッフ)」を起点とするパートナーシップを推進してまいります。
Webサイト:https://shiodome.co.jp/news/46977/

資格がなくても士業事務所で輝ける
- 2025.11.01
- ビジネスの話
資格がなくても士業事務所で輝ける。私は、すでにそういう時代になったと考えています。かつて税理士事務所では「税理士以外は修行の身」といった時代もありましたが、いまは当時の何十倍も活躍のチャンスがあります。つまり、士業だから安泰という考えはもはや通用しなくなりつつもあります。
これからの時代に求められるのは、資格だけではなく「考える力」と「巻き込む力」だと感じます。最近は「ホワイトワーカーがAIに代替され、ブルーカラーの時代に…」といったニュースも目にしますが、個人的にはテスラのヒト型ロボットOptimus(オプティマス)を見ると、どちらも同じくらい危ういとも思います笑
士業事務所が組織として成長すれば、もはやそれは一つの事業会社として社会に貢献できる存在になりますし、実際その動きはすでに広がっています。問われているのは、資格の有無に関わらず、自分の得意分野をどう生かすか、どんな形で価値を生み出せるかです。
私は士業ではない方々にも積極的にこの業界に入ってきていただきたいと考えています。士業が持つ国家資格や社会的信頼を、より高い価値のビジネスとして社会に提供していく。そうした新しい挑戦を共に進めていけたら嬉しいです。
士業の独占業務等にとらわれず、枠を超えて多様な仲間とともに成長していく…そんな魅力ある世界を一緒につくっていきたいです。

立場が上がるほどに求められる自律と責任
組織においては、上に立つ人ほど厳しい言葉を受け止め、自らを律し、お手本にならなければなりません。立場が上がるというのは自由になることではなく、むしろ制約が増え、自己管理がより求められることを意味します。
独立した当初は一人で本当に自由でしたが、今はある意味で不自由です。色々な制約がありますし、Xもいつかはやめなければならない日が来るかもしれません(笑)。パートナーや取締役、執行役員に対して「ここは改善すべきだ」と愛を持って伝え続ける日々は、楽なものではありません。もちろん私自身ができていないことも多々あるのですが。
一方で、新しく入ったメンバーは大切に育てられるべき存在です。入社して間もない数年間は、ある意味守られる立場にあります。ただ、その状況に甘えるのではなく、できるだけ早く自立し、成長していくことが求められます。信頼関係がまだ十分にできていないうちは、当たり障りのない会話が中心になります。そのためか、私もその頃は仏のように優しいと自分で感じることすらあります。しかし関係が深まるにつれて、愛を持って厳しい指摘をせざるを得ない場面が増えます。たとえば知識や準備の不足を指摘したり、努力の必要性を伝えたりすることです。時に耳の痛い言葉になるかもしれませんが、成長を願っているからこそです。
ここを取り違えて、上席には甘く、下のメンバーには厳しい組織をつくってしまうと、不満が溜まりやすくなり長続きしません。「あの人は可愛がられて出世している」といった声が出てくるのは、健全な組織ではありません。どうしてもそう見えてしまうことはありがちですが。少なくとも弊社の場合、上席の立場は決して楽ではありません。無数の期限なき(常にASAPな)課題に追われ、体力的にもハードな出張や会食をこなしながら、それでもなお自己研鑽を求められ続ける…そんな毎日です。知識・経験・ノウハウを、体力と精神力を伴って提供し続けるのは容易なことではありません。それでも、この挑戦こそが仕事の醍醐味であり、私にとってはワクワクを感じる瞬間でもあります。
最近は「若い人が上を目指さなくなった」「競争に負けても悔しさを感じにくくなった」といった話を耳にすることもあります。多様な価値観や働き方が尊重される時代なので、それ自体は別に良いことだと思います。ですが、その中でもなお「上を目指したい」と本気で思う若手がいれば、きっと会社にとってダイヤの原石です。そういう方々はおこがましいですが、全力で育てていきたいと思います。