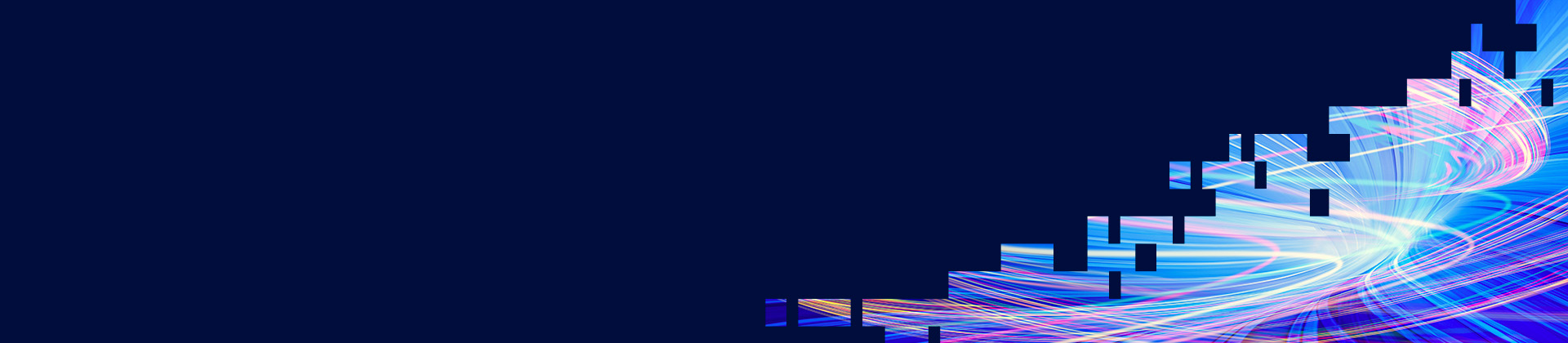場所に縛られない時代に、どう信頼と成果を築くか
- 2025.10.10
- ビジネスの話
もし自分がリモートワーク中心で管理職を目指すとしたら――そんなことを考えてみました。一般の企業では上席ほど仕事の責任は重いですがお給料も上がります。
私たちの会社でも、全国でリモートワーク中心に働くメンバーが増えつつあります。テクノロジーの進化により場所を問わず仕事ができる時代になりました。実際、担当として自分の職務を遂行し、数字を上げるという点では、リモートでも十分に成果を出すことが可能です。
しかし一方で、営業をしたり、提案をまとめたり、チームを率いたり、時にはクライアントに謝罪に行くといった「前に立つ仕事」を担うことは、やはりリモートだけでは難しい部分があるのも事実です。弊社でもそのような職責を担う者はまだおりません。
そうした中で「リモートだから仕方ない」と言われないためには、自ら積極的に動くことが欠かせません。そのために必要なことは、例えば次のようなことではないでしょうか。
- 社内の情報を自分から取りに行く
- 役員など上席や他部署メンバーとの接点を増やす
- 社内共通業務などの担当に立候補する
- オンラインでもカメラをオンにし表情を見せて会話する
- 雑談や非公式なコミュニケーションを大事にする
- 出張や食事会などリアルな機会を積極的に活用する
- 自分の取り組みや成果を発信して見える化する
- 上司やチームへの報連相を密に行う
- 他のメンバーのサポートや相談にも積極的に乗る
- 「呼ばれる人」ではなく「誘う人」になる
- 会社や部門の理念や方向性に自ら関心を持つ
- 成果だけでなく信頼残高を積み上げる意識を持つ
- とにかく自分を覚えてもらう!
個別に見ていくと、一見すると時代に逆行しているように思われるものもあるかもしれません。しかし、リモートだからこそ、意識して人との距離を縮める努力がより一層求められるのだと思います。ある意味では、リアルにすぐ会える環境よりも何倍も大変だと言えるでしょう。
これからは、「リモートで働けるかどうか」ではなく、「リモートでどこまで活躍できるか」が問われる時代です。そして、場所に関係なく信頼を築き、成果を出せる人こそ、次の時代において強いプロフェッショナルになるのだと感じています。

従業員数3桁以下の会社の昇格のリアルな仕組み
- 2025.09.20
- ビジネスの話
RSM汐留パートナーズでは年2回昇格のタイミングがあります。会社と個人の成長スピードが速い中で、年1回の昇格では機会が限られると考えているためです。そのため、年齢や社歴に関係なく、人によっては驚くほど速いペースで駆け上がっていきます。
経験上、私が以前所属していた大手監査法人のように、従業員が数千人の企業や社歴の長い企業では、ある程度システマティックに規定通りあがっていきます。予定より早い昇格や飛び級などもほとんどなく、トップマネジメント以外でサプライズ人事は稀です。
一方で、従業員数が3桁以下、すなわち1000人未満の会社では、もちろん評価や昇進のルールはしっかり整備されていても、やはり会社のトップマネジメントに自分のことを認知してもらうことが不可欠だと感じます。最終的に決めるのはシステムではなく「人」だからです。現実的な話になりますが、避けては通れない要素です。
弊社はもうすぐ役職員250名になろうとしているのですが、実際私もすべての昇格推薦に目を通しコメントをしています。推薦対象者についてよく知らない場合や、良い評判が私の耳に入ってこない場合は、周囲に積極的にヒアリングしています。もちろん、事業部所属であれば個人の担当売上目標金額の達成なども大切なのですが、それだけではありません。間接業務を含め会社の運営にどの程度貢献しているか、今後も貢献できるポテンシャルがあるか、他事業部にも興味を持っているか、時間外に自己研鑽の習慣があるか(資格や語学の習得に限らず)といった点も重視しています。
最近は昇格よりもワークライフバランスを重視する方も増えているように感じますが、社員数1000人未満の会社で昇格・昇進を目指す成長意欲や挑戦心を持った方にとっては、その挑戦を後押しする場であり続けることが大切だと考えます。
労働分配率から考える経営の姿
- 2025.09.10
- 公認会計士・税理士, 会食・交流会・セミナー, ビジネスの話
税理士法人の経営者同士の勉強会では、労働分配率が話題にのぼることが多くあります。その際、税理士法人によって代表者の報酬の多寡が大きく異なるため、労働分配率(社会保険料・賞与を含み、代表者報酬は含まない)がよく話題になります。
規模にもよりますが、100人以上の事務所で考えると、理想は50〜60%程度とされているように感じるのですが、弊社の連結ベースでは代表者報酬も含め65%ほどという感覚です。それでも高すぎるとは感じていませんが、税理士法人全体で見ればどうも高い方に位置されるように感じます(私の代表者報酬が高いということはございません笑)。
この点について実はずっともやもやしていました。このもやもやについて、Big4監査法人の損益計算書(P/L)を眺めて電卓を叩き労働分配率を計算し、遅ればせながら自分の中で整理がついてきまして、霧が晴れてきました。日本のBig4監査法人の労働分配率(2023/24期、パートナー役員報酬含む)は62〜74%ほどです。この差は、パートナーの取り分が役員報酬とされてP/Lの販管費に含めているのか、税引後当期純利益からの配当とするかの違いだと理解しています。これはP/Lに表れる利益の厚薄の差からも読み取れます。
私は、役職員を「会社に人生の時間を投資しているオーナー」と捉え、配当的な意味合いも含めて賞与で還元しています。その結果として労働分配率は高めなのですが、ワンストップファームとして規模が拡大する中ではむしろ自然な形かなと思っています。高すぎても未来への投資余力や強固な財務基盤を確保できないので、バランスを取りながら経営を行うことが重要であるのは言うまでもありません。明確な指標がないものの極めて大切なこのポイントについて、経営者としての感度を常に研ぎ澄ましていきたいと思います。
社内アピールのすすめ
- 2025.09.01
- ビジネスの話
社内アピールは個人的に組織で活躍するためには結構大事だなと昔から思っていることの1つです。日本人は一般的に自己アピールが得意ではないと言われます。
まず、欧米の企業ではリストラが当たり前の環境であり、もちろん業務で成果を上げてリストラ対象にならないよう努力することは大前提ですが、もう一つ重要な点があると聞きます。それは「上席に覚えてもらうために自分を売り込むこと」です。外部に営業するように、内部でも営業する…そうした発想です。 仮に会社がどうしても一人だけリストラをせざるを得ない状況で、能力が同程度のメンバーが並んでいた場合、日頃の印象や記憶に残っているかどうかで判断が分かれる…というのが人間の性とも言えます。もちろん全ての欧米企業に当てはまるわけではありません。
一方で、日本企業ではリストラはめったにありませんのでこの点が軽視されがちだと感じます。ただリストラに限らずで、どんなに公平な人事制度を取り入れたとしても、最後評価するのはAIではなく人ですので、昇格という観点でも重要なことのように思います。
私自身も監査法人時代に特別なことをしていたわけではありません。強いて挙げるなら、日々遅くまで働いたり事務所で残って勉強して、上司や先輩、時には代表社員から夕食に誘われれば必ず参加していた程度でしょうか。もっとも、今の時代は「飲みに行こう」と気軽に声を掛けにくくなっているので、そういう風景も見られないのかもしれません。最近になってちょっとしたきっかけではあるのですか、若手を含む何人かから、声を掛けてもらったりチャットで連絡をもらったりすることがあり、やはりとても嬉しいです…人間ですもの。そうしたやり取りは、やはり記憶に残るものだと実感します。だからこそ、何気ないやり取りや小さなつながりが、思っている以上に後々のかたちに影響していくのかもしれません。
小さな時間の積み重ねが大きな成果を生む
小さな時間の積み重ねが大きな成果を生みます。そして時間の使い方を見直すだけで驚くほどの変化が起こります。「忙しい」は理由になりません。「成果を上げる人は重要なことに集中する。本質的な課題に力を注ぐことで結果を出す」というドラッカーの言葉もあります。
また、何か成し遂げるためには一定のハードワークが必要だと考えています。この「ハードワーク」の意味ですが、ただ長い時間働くということではなさそうです。仕事や関係する趣味等も含め楽しむことができたなら、疲れも軽減されるとともに、情報収集や人脈形成も相まって大きな成果に結びつきます。
さらに、仕事の熱量が高いほど生活満足度向上に繋がったり、幸福度が高いほど様々な事柄の成果が出ると言うのには納得感があります。日本でもこれまで以上に幸福経営を取り入れていくことが求められると感じます。
そして、もっとDEI(Diversity, Equity & Inclusion)が進んでいく会社にしたいなと思っています。そのために”自己開示する力”が重要だし一方周りにもそれを受け入れる”寛容さ”が必要だと思います。お互いを”理解”することって大切で、例え”理解”できなくても”認識”し合うことだけでも一歩前進します。心理的安全性が高いコミュニティでは1人1人が大きな力を発揮でき、結果として組織の成果も非常に大きくなります。
一人ひとりが自分らしさと情熱を持って行動し、互いを尊重し合える環境を築くことが、持続的な成長と真の成果への最短ルートになるのだと思います。

若いうちに恥をかき捨てよう
私はもう若者と言える年齢ではありませんが、海外の代表者、拠点長、パートナーたちと比べると、まだ若い部類かもしれません。
RSM各国のオフィスを訪れ、打ち合わせをして、執務用に会議室を借りて、食事もご馳走していただく…下手な英語でも、相対的に若いから許されている部分があるのかもしれません(もし許されていなければ、届かないかもしれませんが、この場を借りてお詫びします…)。
でもやはり、体力があって、恥をかいてもそのまま成長に変えられるのは、若さの特権だと思います。何歳までが若いかは人それぞれですが、若ければ若いほど失敗は許されやすく、的外れな質問すら笑って受け流してもらえるもの。相手もきっと覚えていません。
監査法人の時「アホな質問はすべてスタッフのうちにし尽くしてなるべく持ち越すなよ!年次が上がると恥ずかしくて聞けなくなるからな!」とよく先輩に言われたものでした。それを忠実に守りアホな質問をたくさんして成長しました。
ChatGPTがなくインターネットの情報自体も怪しい時代でしたので、先輩に何でも聞いていました。今は調べるツールが充実していて、ある意味過酷な時代だなあとも感じます。
ぜひ、恥を恐れず、どんどん挑戦して失敗してほしいです。社内でも海外でも、そして新しい業務にも。未熟さを理由に諦めず、「今だからこそできること」に思い切り飛び込めたらいいですね。
そんなこんなで私は自分より若い人には仏のようにめちゃくちゃ寛容です。

課外活動のすすめ
Big4の監査法人にいると、自分次第ですが課外活動のチャンスはたくさんあります。最近は皆忙しすぎてそれどころではないのよと言われてしまいそうですが…。
その監査法人にずっと勤めるかどうかはさておき、公認会計士として30-40年以上の長いキャリアを歩む中で、先輩・同期・後輩・顧客との関係を良好に保つことは本当に重要です。
なぜなら、思っている以上にこの業界は狭いからです。公認会計士は間に1人入るとほぼ皆繋がっているとよく言われます。もちろん、海外にまで目を向ければ広い世界ですから、多少国内でこじらせても海外に出ちゃえば大丈夫かもしれませんが。
大手監査法人の名刺を持っているうちは絶好のチャンスです。たとえ準会員であっても名刺一つで軽んじられることはないでしょうし、銀行・証券会社・VC・PEファンド・弁護士・税理士・医師など、さまざまな分野のプロフェッショナルと接点を持てる可能性が一気に広がります。
いずれにせよ、皆が求めているのは長く信頼できる付き合いだと思います。だからこそこの環境を最大限に活かして、良い関係性を構築していくことが、将来の成功に繋がります。監査法人の最初の5年10年の努力でその後も楽にいけるとまでは言いませんが、必ず役に立つと思います。
本業だけでなく、人脈づくりや異業種との交流など、名刺一枚で広がる世界があります。飲み会の幹事を努めるなどもおすすめです。この業界はシャイな人も多いかもしれませんが、どなたかの参考になれば幸いです。

【アジア的阿吽の呼吸と欧米的ビジネスライクのはざまで】
アジア諸国(インド除く)とのビジネスでは、文化的な近さもあって、ある程度わかり合える空気みたいなものが存在します。報酬に関しても、まずは無料相談から始まり、徐々に条件を調整していい塩梅に落ち着く…そんな流れも珍しくありません。
時には“阿吽の呼吸”のような感覚が求められる場面もありますが、さすがに国をまたいでそれを期待するのは難しいですよね。 阿吽で行けているつもりが全く噛み合っていなかったということも。
一方で、アメリカやイギリスでは、良くも悪くも非常にビジネスライク。無料相談という概念はあまりなく、初めから相談料に関して見積もりベースで話が進みます。
常にベストプライスを提示し、それで合意が取れれば進める、合わなければそこで終了。必要があれば、率直に予算を伝えて調整するというスタンスです。
皆さんは、どちらのスタイルが合っていますか?国内の業務で成功するためには高い専門性も必要ですが、やはりクライアントとのリレーション構築、場の空気を読む、期待値コントロールなど、当たり前ですが資格試験にはでてこない様々スキルが求められます(笑)国際案件に関わることが増えてきた最近では、私自身、こうした欧米式の合理的な進め方に徐々に心地よさを感じるようになってきてしまいました。
もともとウェットな関係づくりに強みを持っていた純ジャパニーズな私も、変化を遂げています。そして社内においても、これまでの関係性を大切にしつつもwin-winでいけるよう考えながらビジネスライクにも進める…そんな「融合」や「両立」ができるようになってきたと少しずつ感じています。
人のいい日本人が、その優しさから利を得られず没落しないように、主張すべきことはしっかり主張する。これからも日本人経営者、日本人資格者として頑張っていきたいと思います。

信頼を得る行為と失う行為
- 2025.06.20
- ビジネスの話
昔上司からの評価ばかりを気にしていた頃、大切なことに気づけていませんでした。それは同僚や部下への配慮が欠けていたということです。信頼とは、目立たないけれど何よりも尊いものであり、上下関係にかかわらず、誰に対しても変わらぬ姿勢で接する中で少しずつ築かれていくものですね。
そのためには、まず自分が信頼に足る人間になること。そうすれば、自然と信頼できる人が周りに集まり、さらにその人たちが素晴らしい縁をつないでくれる。この流れを実感すると、無理に人脈を広げることに意味はなかったと気づきます。ただ、そのことに気づくまでには、誰しも遠回りをするものなのかもしれません。
信頼でき気持ち良く仕事ができる人は
- レスが早い
- メンタルが強い
- コミュ力が高い
- 合理的な判断ができる
- 問題解決能力が高い
- 話が短く要点を押さえている
- 人間的な部分も見せられる
- 客観的に物事が見られる
- 中長期視点がある
- 自責で考える
といった特徴を持っています。
この特徴を信頼を得る行為と結びつけてみます。
まず大切なのが、レスの早さ。即答できなくても「確認します」「○日までお時間下さい」のリアクションをすぐできるかどうか。すごくシンプルで手っ取り早く信頼を獲得できて自らの評価を上げられる方法です。また、仲間を信じ、仲間に信頼され、クライアントに対して良い仕事をするために大切なことは、ぶれない、嘘をつかない、隠し事をしない。信頼の積み重ねが、組織の力を高めるのだと思います。そして、話を聞く ⇒ 課題を認識する ⇒ 解決する ⇒ 信頼が生まれる ⇒ さらに相談を受ける…会社も個人もこのサイクルをどれだけ積み重ねられるかが成長の鍵ですね。当り前ですが「信頼こそが最大の資産」。さらに、自己開示により相手と仲良くなれ信頼を勝ち取ることができるか。
自分の情報を差しさわりない範囲で先に多く伝える力はビジネスでもプライベートでもすごく重要です。
自分の話はせず「あなたの情報を教えなさい」というのは変です。特にマネジメントする人にとって必須スキルではと思います。なお、経験上ですが、経営トップはまどろっこしい話が嫌いなので、直接交渉できる時は単刀直入に聞いてもいいと思います。
- 相見積もりですか?決め手は何ですか?
- どのくらいの予算だったら許容できますか?
そんな本音トークが信頼を勝ち取る事もあります。
※諸刃の剣であり撃沈の可能性もあります。
一方で信頼を失う行為に触れます。
人生どうしても避けられないことが起きるのでドタキャンすることも致し方ありません。でも信頼を失いたくないので基本的にはそうしないで日々過ごします。そのリスクを低減させ、極力これまで積み重ねてきた信頼を減らさないように努めるに尽きます。
また、会議にて
- 強化します
- 徹底します
- 意識を高めます
という発言は一見やるそぶりを見せているものの、何も具体的なことを言えていないので、芳しくない結果が続くと信頼を失っていくので要注意です。
信頼を失うのは一瞬。昔は失敗をした人に再度チャンスを与えられるような心の広さを持ち合わせていませんでした。ただ失った信頼を取り戻すべく努力している者が再び信頼に足る人物となっていく出来事に多く触れ、時間はかかりますが積極的に機会を提供し応援できるようになってきました。
弊社営業ルートは、金融機関からの紹介はなく、WEB経由、そして一つ一つの仕事を大切に行ってきた結果のご紹介です。金融機関と大手事務所の特別な関係に気づき、諦めると同時に別の戦略を考えるに至りました。今後もお客様との信頼関係を大切にし、常に最善のサービスを提供していきたいと思います。カッコよく表現できないのですが、働き方改革やコロナ禍など色々経て、一層人と人の繋がりや信頼関係の深さが組織の強さになり、それが良い結果に結び付く時代が来るような気がしています。

【AI→AGI時代と士業事務所の生き残り】
AIは既に会計・監査・税務・人事・労務・法務などの領域でとても浸透してきていますが、今後数年で登場するかもしれないAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)は、我々士業、例えば公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの仕事を根底から変える存在になりそうです。
今のAIは、データ分析、帳簿記帳、税額計算、給与計算、社会保険手続きなど、定型業務を高速で処理する特化型AIです。これでもインパクトは大きいのですが、これから海外で台頭してきそうなAGIというものは
- 法改正を自動ですべてリアルタイムでキャッチアップし
- 顧問先の過去の決算や業種特性を踏まえて
- 最適な組織体系、節税対策、人事制度設計などをどんどん提案し
- 状況に応じて説明のトーンや言語まで自由自在に調整できる…
つまり、士業事務所の中堅からベテラン職員レベルの判断や提案までもを、当然ながら24時間365日休まず行う存在になります。
これにより、例えば
- 会計帳簿・決算書・申告書のレビュー
- 雇用契約書や就業規則をはじめとする規程のドラフト作成
- 日本進出企業や海外進出企業への多言語支援
- 世界中の法制度を理解した上で最適な各種提案
- グループ内組織再編の設計など
従来専門家がやるべきとされてきた領域もますますAGIがカバーしていきます。業法とライセンスの問題はありますが。AGIについて引き続きものすごい脅威を感じながらも、ビジネスにうまく活用できればチャンスになりそうです。
その先にはASI(Artificial Super Intelligence:超人工知能)もあるようで、個人的にはとてもワクワクしています。こういう情報について海外から早めに得られるようになっているのは私にとって大きいです。
結局のところAI台頭時代においても言われますが、柔軟にこれらを使いこなせるスキル、創造力やコミュニケーション能力、体力や精神力(やりきる力)など、人間力・人間的な魅力のある者以外は活躍が難しくなるということだと理解しています。
AIの進化を脅威として恐れるのではなく、柔軟に受け入れ活用し、人間ならではの力を磨き続けることこそが、これからの士業に求められる姿勢だと強く感じています。