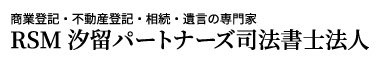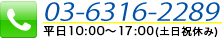商業登記関係 合同会社の持分を信託したことによる業務執行社員・代表社員の変更登記
合同会社の持分譲渡
合同会社の持分は譲渡することができ、既存の社員Aが持分の全部を譲渡したときは退社し、当該持分を既存の社員でない者Bが譲り受けたときはBが入社します。
唯一の社員Aがその持分の全部をB(個人)に譲渡したときは次のように社員、業務執行社員及び代表社員に変更が生じます。
信託による持分の移転
合同会社の持分も信託の対象とすることができるものとされており、持分が信託されると当該持分は受託者へ移転します。
委託者たる社員Aの持分の全部が受託者Bへ移転すると、前述の持分全部譲渡のとおり、委託者Aが退社し受託者Bが入社しますので、社員Aが業務執行社員や代表社員であるときはその変更登記をする必要が生じます。
合同会社は株式会社と異なり所有と経営が分離していないため、持分の全部を信託すると委託者Aは業務執行社員や代表社員で居られなくなりますが、株式会社であれば取締役兼株主Aが株式を信託したとしてもそれだけではAは取締役を退任せず、また、Aの任期が満了しても受託者が委託者を取締役として選任することも可能です。
信託に基づく業務執行社員、代表社員の変更登記
持分が贈与、売買、信託に基づき譲渡されたのであれば、それにより業務執行社員、代表社員が変わるのであれば、内容に応じて登記手続きを行います。なお、社員が複数名いて、業務執行社員、代表社員に変更が生じなければ、登記手続きは不要というケースもあります。
合同会社の定款、既存の社員の人数と役員構成、譲受人の数、社員が個人・法人のどちらか等の要因によって譲渡手続き・登記手続きの内容が変わるため、ケースごとによる判断が必要です。
ここでは合同会社Xの唯一の社員Aが、その持分全部を長男Bに信託したケースを見てみます。
信託契約の締結
AとBで、Aを委託者・Bを受託者(+一般的にはAを受益者)とする信託契約を締結し、信託財産に合同会社Xの持分を含めます。
総社員の同意
持分を譲渡(信託)するときは、原則として総社員の同意が求められるので(会社法第585条1項)、社員たるAの同意書を作成します。
このときに、持分の全部がAからBへ譲渡(信託)されたこと及びそれに伴い定款の内容が変更することが当該同意書から分かり、ABともにその内容に同意していることが分かる内容であれば、登記手続き上、持分が移転したことの分かる契約書等(ここでは信託契約書)を添付せずに登記をすることが可能となります。
管轄法務局へ登記申請
業務執行社員、代表社員に変更が生じたときは、その変更から2週間以内に登記をします(会社法第915条1項)。
当該登記の添付書面は次のとおりです。
- 総社員の同意書
上記の他に、一般的には印鑑届書及びBの印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を同時に提出し、登記申請行為を代理人に委任する場合は委任状も添付します。
上記は登場人物が2名の個人というシンプルな例ですが、既存社員が複数名いる、定款に別段の定めがある、受託者が法人であるような場合、譲渡手続き及び登記の添付書面が大きく変わりますのでご注意ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。