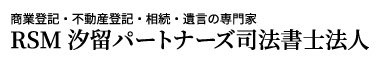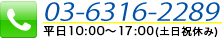商業登記関係 株主総会の招集通知はいつまでに発しなければならないか
株主総会の招集通知を発する時期
定時株主総会・臨時株主総会を問わず、株主総会を開催するときは原則として株主へ招集通知を発する必要があります(会社法第299条1項)。
招集通知はいつまでに発しなければならないという期限があり、この期限を守らなかったときは、株主総会の手続に法令違反があるものとして株主総会決議の取り消されてしまう可能性がありますので注意が必要です。
特に、招集通知を発する日と開催日の期間の数え方を誤解していて当該期間が1日不足しているケースを見かけることが少なくありません。
公開会社の場合
公開会社である株式会社においては、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発しなければなりません(会社法第299条1項)。
この2週間の期間の数え方につき、例えば3月22日(水)に株主総会を開催するのであれば、3月7日(火)までには招集通知を発しなければらないことになります。
2週間前までに発するとは、招集通知を発する日除いて2週間の日数(中14日)が必要ということです。つまり、株主総会開催日の15日前が招集通知をする発する期限ということになります。
非公開会社(公開会社でない株式会社)
非公開会社においては、株主総会の日の1週間前までに、株主に対してその通知を発しなければなりません(会社法第299条1項)。
この1週間の期間の数え方につき、例えば3月22日(水)に株主総会を開催するのであれば、3月14日(火)までには招集通知を発しなければらないことになります。
1週間前までに発するとは、招集通知を発する日除いて1週間の日数(中8日)が必要ということです。つまり、株主総会開催日の8日前が招集通知をする発する期限ということになります。
ただし、株主総会において書面投票制度(会社法第298条1項3号)または電子投票制度(会社法第298条1項4号)を採用する場合は、非公開会社であったとしても、当該株主総会につき株主総会の2週間前までに招集通知を発する必要があります。
招集期間の短縮
一定の条件を満たすことにより、招集期間を短縮することができます。株主が1名しかいない、あるいは親族しかいないのに、招集通知を発送してから1-2週間経過しないと株主総会を開催できないのは不便ですし、株主全員が了承・同意しているのであれば招集期間を設けなくても誰も不利益を被らないといえます。
定款による招集期間の短縮(非公開会社、取締役会非設置会社)
非公開会社でかつ取締役会非設置会社においては、定款で定めることにより、招集期間について1週間を下回る期間を定めることが可能です。一例としてのその期間を3日や5日とすることができます。
定款による招集期間の短縮ができない会社
次の会社においては、定款に招集期間の短縮を定めることはできません。
- 公開会社
- 非公開会社で取締役会設置会社
- 書面投票制度または電子投票制度を採用した場合
株主全員の同意
株主全員が同意しているときは、招集手続き自体を省略することができます(書面投票制度または電子投票制度を採用した場合を除きます)(会社法第300条)。招集通知を発していないくても、株主全員が集まり、今から株主総会を開催することに同意しているのであればその場で株主総会をすぐに開催することができるということになります。
また、株主全員の同意があるのであれば、招集手続き自体を省略することができるため、招集期間の短縮もできると解釈されています。この場合も、会社法第300条から、書面投票制度または電子投票制度を採用した場合は招集期間の短縮はできないように思います。
株主総会の決議の省略
会社法第319条により、取締役等が提案した議案に対して株主全員が書面等により同意をしたときは株主総会の決議があったものとみなされます。みなし株主総会(決議)といわれたりします。この株主総会の決議の省略は、実際に一同が会して(テレビ電話やskype含む)株主総会を開催する必要がないため、株主が1名あるいは少数である会社においてよく利用されています。
≫みなし株主総会(書面決議・みなし決議)-会社法第319条1項
メール等の電磁的方法による招集通知
招集通知は、次に該当する場合には書面でしなければなりません(会社法第299条2項)。
- 書面投票制度または電子投票制度を採用した場合
- 取締役会設置会社である場合
そのため取締役会非設置会社で書面投票制度または電子投票制度を採用しない場合は、口頭やメールでも株主総会の招集を行うことができることになります。ただし、後で言った言わないとならないよう、特に外部株主がいる場合は招集通知を発した記録が残る方法とすることが無難です。
取締役会設置会社においても、株主の承諾を得ることで、メール等の電磁的方法により招集通知を発することも可能となります(会社法第299条3項)
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。