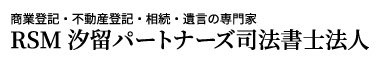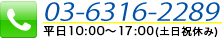商業登記関係 一般財団法人を新たに設立する手続きと登記(金銭拠出)
一般財団法人の設立
一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人のことをいい、設立の登記をすることによって成立する法人です(一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A(法務省)A9)。
一般財団法人は、主に次の手続きによって設立することが可能です。設立者は個人であり、拠出する財産は金銭のみとし、遺言によらず、会計監査人を設置しない一般財団法人を前提としています。
- 定款を作成する。
- 作成した定款につき公証人の認証を受ける。
- 財産を拠出する。
- 設立時理事等が就任を承諾し、設立手続きの調査をする。
- 法務局へ登記申請をする。
以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を「法人法」といいます。
定款を作成する
一般財団法人を設立するには、まずは設立者が定款を作成します(法人法第152条1項)。一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録します(法人法第153条1項)。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所の所在地
四 設立者の氏名又は名称及び住所(設立者は法人でも可)
五 設立に際して設立者が拠出をする財産及びその価額
六 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
八 評議員の選任及び解任の方法
九 公告方法
十 事業年度
上記五の拠出をする財産の価額の合計額は、300万円を下回ってはならないものとされています(法人法第153条2項)。
設立時理事等
設立時の設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ3人以上でなければならず(法人法第160条1項)、設立時監事は1名以上置く必要があります。
監事は一般財団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができず(法人法第65条2項、法人法第177条)、評議員は一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができません(法人法173条2項)。
そのため、一般財団法人を設立するには評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の計7名以上の員数が必要です。
また、次の者は評議員、理事又は監事になることができません(法人法第65条1項、法人法第160条2項)。
- 法人
- 法人法律若しくは会社法等※の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
※法人法第65条をご確認ください。 - 上記に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
定款作成時に設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事や、設立時の主たる事務所が決まっている場合は、それらを定款の附則に記載することで設立者の決議書等といった書類の作成を省くことができます。
名称
一般財団法人は、その名称中に一般財団法人という文字を用いる必要があります(法人法第5条1項)。また、一般財団法人は、その名称中に、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いることは認められていません(法人法第5条3項)。
一般財団法人も同一の名称の法人が同一の主たる事務所に存在することが禁止されていますので、これから設立する一般財団法人の主たる事務所の場所に同じ名称の一般財団法人がないか確認することは必須です。
同一の主たる事務所に同一名称の一般財団法人がないかを確認する方法の一つに≫国税庁法人番号公表サイトで検索する方法があります。
なお、使用したい名称と同じ名称の法人が既にある場合は、設立する法人の主たる事務所の場所に同じ名称の法人がない場合であっても、別の名称にして設立する方が無難ではあります。
評議員の選任及び解任の方法
評議員の選任及び解任の方法は一般財団法人の定款の絶対的記載事項であり(法人法第153条1項8号)、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めはその効力を有しません(法人法第153条3項1号)。
評議員の選任及び解任の方法としては、次のような記載例があります。
公告方法
一般財団法人は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができます(法人法第331条1項)。
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
- 不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
上記4の法務省令定める方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法です。
法第331条第1項第4号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
作成した定款につき公証人の認証を受ける
設立時の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じませんので(法人法第155条)、設立登記を申請するまでに公証人の認証を受ける必要があります。
設立する一般財団法人の主たる事務所の所在地のある都道府県内にある公証役場に予約をして、公証人の認証を受けることになります。
財産を拠出する
設立者は、設立時の定款につき公証人の認証を受けた後遅滞なく、拠出に係る金銭の全額を払い込みをします(法人法第157条1項)。
設立者名義の法人口座に拠出に係る金銭の全額を入金する、又は振り込む方法で拠出するケースが多いでしょうか。
公証人の認証を受ける前の財産の拠出
法人法第157条1項の規定では、設立時の定款を公証人に認証してもらった後に金銭の拠出を行う旨を規定していますが、公証人の認証前に財産の拠出が行われた場合でも登記手続き上の問題はありません。
設立時理事等が就任を承諾し、設立手続きの調査をする
設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査します(法人法第161条1項)。
- 財産の拠出の履行が完了していること。
- 前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
法務局へ登記申請をする
一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(法人法第163条)。
一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、上記の設立時理事及び監事の調査が終了した日又は設立者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません(法人法第302条1項)。
2025年11月現在、法務局が開庁している日にしか設立登記の申請をすることができないため、登記申請日=法人設立日は平日に限られます。
登記すべき事項
一般財団法人の登記すべき事項は≫法人法第302条2項のとおりです。
法務局の提供している≫一般財団法人設立登記申請書も参考になります。
添付書類
一般財団法人設立登記の添付書類の一例は次のとおりです。
- 定款
- 財産の拠出の履行があったことを証する書面
- 設立時理事、設立時代表理事、設立時監事及び設立時評議員の就任承諾書
- 設立時理事、設立時監事及び設立時評議員の本人確認証明書
- 設立時代表理事の印鑑証明書
上記の他に、代表理事が印鑑提出を行う場合は「印鑑届書」も登記申請と併せて提出します。印鑑届書には代表理事の発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が求められますが、登記申請書に添付する印鑑証明書を援用することもでき、援用する場合は登記申請書に添付する印鑑証明書も発行後3ヶ月以内のものを準備します。
登録免許税
一般財団法人設立登記の登録免許税は6万円です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。