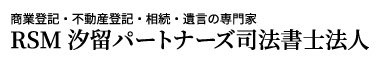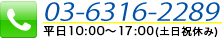商業登記関係 代表取締役の交代と印鑑廃止届が必要なケース
会社・法人における印鑑の提出
令和3年(2021年)2月15日以降、会社・法人における法務局への印鑑の提出は任意となりましたが、まだほとんどの会社・法人において印鑑の提出を行っている状況かと思います。
≫オンラインによる印鑑の提出又は廃止の届出について(商業・法人登記)_法務省
また、印鑑の提出は、オンラインによる登記申請と同時に印鑑の提出を行う場合は、オンラインによっても印鑑の提出を行うことができますが、紙の印鑑届書を提出する方法がまだ主流であるように感じます。
そのため、このページでは印鑑の届出を書面によって行うことを前提としています。
代表取締役の交代と印鑑廃止届
株式会社の代表取締役Aが法務局へ印鑑の届出を行っている場合、この印鑑の登録を廃止することも可能です。法務局へ届け出ている印鑑をここでは「会社実印」といいます。
代表取締役がAのみであれば印鑑の廃止手続きを行うことは稀であり、代表取締役が退任・追加されるようなケースにおいて印鑑届書や印鑑廃止届書を準備するかどうか検討が行われます。
代表取締役は変わらないが商号変更をする場合(印鑑廃止届は不要)
代表取締役がAのみである株式会社Xにおいて、商号を株式会社Pに変更する場合、商号変更登記と同時に会社実印を変更することがよく行われます。
「株式会社X」と彫られた会社実印を、「株式会社P」と彫られた会社実印に変更するようなケースです。
この場合、商号変更の登記申請と同時に、「印鑑届書(株式会社Pと彫られた印鑑+代表取締役Aの実印)」と「代表取締役Aの個人印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)」を提出する方法で印鑑の提出を行うことになります(同日ではなく後日変更することも可能です)。
代表取締役が交代するケース
上記の株式会社Xにおいて代表取締役がAからBに交代する場合、代表取締役Aは退任することになることから、代表取締役Aの印鑑登録は自動的に廃止されるため代表取締役Aの印鑑廃止届の提出は不要です。
印鑑届出をする者がBに代わりますので、Bの印鑑届書の提出は別途必要となります。このことは、代表取締役Aの退任日と代表取締役Bの就任日が離れている場合でも変わりません。
なお、後任の代表取締役が選定されないと登記申請をできる者がいなくなるため、代表取締役Aの退任による変更登記のみを行うことはできません。
代表取締役が追加されるケース①(印鑑廃止届は不要)
上記の株式会社Xにおいて代表取締役Bが追加で選任され、当該追加後の代表取締役がABの2名となるケースはどうでしょうか。
代表取締役Bが印鑑の登録をするかどうかは任意ですので、引き続き印鑑の登録者をAのみとするのであればBが印鑑の登録手続きをする必要はありません。
Aに加えてBも印鑑の届出を行う場合は、Bが印鑑届書の提出も行うことになります。この場合、Bの会社実印につき、Aの会社実印とは別の印鑑を用意します。
代表取締役が追加されるケース②(印鑑廃止届が必要)
上記の株式会社Xにおいて代表取締役Bが追加で選任され、印鑑登録者をBのみとする場合は、Aの印鑑廃止届書+Bの印鑑届書の提出を同時に行うことになります。
Bの印鑑届書にAの印鑑カードを引き継ぐ旨を記載することにより、Aの印鑑カードをBが引き続き使用することも可能です。
この場合、Aが使用していた印鑑とは別の印鑑をBが登録することも可能です。
既存の代表取締役の印鑑提出者を変更するケース(印鑑廃止届が必要)
代表取締役がCD2名(印鑑登録者はCのみ)いる株式会社Yにおいて、新たにDも会社実印の登録をする場合は、Dが印鑑届書の提出も行うことになります。この場合、Dの会社実印につき、Cの会社実印とは別の印鑑を用意します。
印鑑登録者をDのみとする場合は、Cの印鑑廃止届書+Dの印鑑届書の提出を同時に行うことになります。
Dの印鑑届書にCの印鑑カードを引き継ぐ旨を記載することにより、Cの印鑑カードをBが引き続き使用することも可能です。
この場合、Cが使用していた印鑑とは別の印鑑をDが登録することも可能です。
複数いる代表取締役のうち1名が退任するケース
上記の株式会社Yにおいて、Cが代表取締役を退任するときは、Dが新たに印鑑登録をすることになりますが、このときにCの印鑑廃止届は不要です。
Cの印鑑登録はCが代表取締役を退任することで自動的に廃止されます。
Dが代表取締役C退任の登記申請人となり、同時にDが印鑑の登録を行うことになります。この時に、Dが登録する印鑑はCと同じ印鑑とするかは任意です。
会長、社長が交代するケース
代表取締役がEF2名(2名とも印鑑登録をしている)いる株式会社Zにおいて、内部の規定により役職によって登録する印鑑が決まっているケースがあります。
社長は社長印を登録し、会長は会長印を登録している会社において、社長がE、会長がFである場合、Eが社長印を、Fが会長印を登録しています。
会長Fが退任し、Eが社長から会長となり、Gが新たに代表取締役に就任し社長になるようなケースでは、Eが会長印を押した印鑑届書を、Gが社長印を押した印鑑届書をそれぞれ法務局へ提出することになります。
EがFの印鑑カードを、GがEの印鑑カードを引き継ぐようにしたい場合は、Eにつき印鑑カード廃止届が必要となります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。