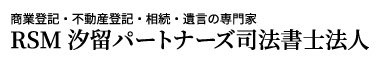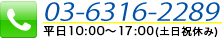商業登記関係 合同会社が合同会社を設立する、分割型分割による新設分割の登記
新設分割の手続き
新設分割とは、一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会社法第2条30号)。
新設分割をすることができる会社(分割会社)は株式会社又は合同会社であり、新設分割により設立することができる会社(新設分割設立会社)は株式会社、合同会社、合資会社又は合名会社です。
会社分割には分社型分割(物的分割)と分割型分割(人的分割)があり、分割型分割は分社型分割+剰余金の配当(現物配当)として整理されます。
株式会社X(株主はAのみ)が株式会社Yを新設分割により設立するときに、株式会社Yの発行済株式を株式会社Xが取得し、株式会社Yが株式会社Xの完全子会社となることが分社型分割であり、株式会社Xが取得した株式会社Yの株式を新設分割計画(及び株主総会決議)に基づきAに現物配当することが分割型分割です。
合同会社と新設分割
新設分割において分割会社、新設分割設立会社ともに株式会社が登場することが多い印象ですが、上記のとおり合同会社も分割会社となり、また、新設分割設立会社となることができます。
合同会社は株式会社と異なり、業務執行社員(や代表社員)には社員しかなることができないため、新設分割設立会社(合同会社)の業務執行社員は分割会社となり、分割会社が新設分割設立会社の持分を現物配当したときは、それに伴い新設分割設立会社の業務執行社員には分割会社の社員がなります。
また、会社法第763条1項12号及び会社法第765条1項8号では、新設分割計画書において定める事項として、「新設分割株式会社が新設分割設立株式会社(持分会社)の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨」とされているとおり、合同会社が分割会社となる新設分割においては分割対価を現物配当する旨は新設分割計画書の記載事項ではありません。
そのため会社法上は、合同会社を設立する分割型分割による新設分割を行う場合は、新設分割の効力発生日に(又は事前に条件付決議をすることによって)、分割会社が社員の同意によって新設分割設立会社の持分を配当することになります(税務面の論点は顧問税理士の先生にご確認ください)。
新設分割のスケジュール
分割会社が合同会社(以下「分割合同会社」といいます。)であり、新設分割設立会社も合同会社(以下「新設合同会社」といいます。)である新設分割につき、2026年4月1日を効力発生日とするスケジュール例は次のとおりです。
| 1月中旬 | 分割の準備 (新設分割計画の内容、債権者の確認、労働者との協議等) | |
| 2月16日 | 社員の同意 官報公告の申込み | |
| 2月25日 | 労働者への事前通知 | |
| 2月25日 | 官報に分割公告が掲載 債権者への個別催告 | |
| 4月1日 | 分割の登記申請 | 設立の登記申請 総社員の同意(現物配当) |
新設分割の手続きの一例
新設分割の手続きの一例は次のとおりです。
- 新設分割計画の作成
- 社員の過半数の決定 ※
- 債権者保護手続き(分割合同会社が併存的債務引受をした場合を除く)
- 登記申請
※合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合は総社員の同意(会社法第813条1項2号)
新設分割会社・新設分割設立会社が株式会社のケースとは異なり、合同会社の場合は、反対株主への通知、事前備置・事後備置の義務はありません。
新設分割計画の作成
新設分割をする合同会社は、新設分割計画を作成します(会社法第762条1項)。新設分割計画の法定記載事項は次のとおりです(会社法第765条)。
- 新設分割設立会社が合同会社であること
- 新設合同会社の目的、商号及び本店の所在地
- 新設合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の名称及び住所 ※
ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
ハ 当該社員の出資の価額 - 前二号に掲げるもののほか、新設合同会社の定款で定める事項
- 新設合同会社が新設分割により分割合同会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
- 新設合同会社が新設分割に際して分割合同会社に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設合同会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- 前号に規定する場合において、二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、分割合同会社に対する同号の社債の割当てに関する事項
※(分割合同会社の社員ではなく)分割合同会社を記載することになると思われます。某法務局からはそうすることを求められました。
分割合同会社は、その事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合、新設分割の効力発生日の前日までに、新設分割計画について総社員の同意を得なければなりません。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めに従います(会社法第813条1項)。
債権者保護手続き
合同会社が新設分割をするときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告します(会社法第810条2項、会社法第813条2項)。
- 新設分割をする旨
- 新設合同会社の商号及び住所
- 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨(1箇月を下ることができない)
公告方法が新聞又は電子公告である合同会社は、官報公告に加え、定款で定められた公告方法で上記事項を公告したときは知れている債権者への催告をすることは要しません(≫ダブル公告)。
新聞又は電子公告によるダブル公告をするときは、新聞又は電子公告による公告掲載の先日までに当該公告方法への変更登記が申請されている必要があり、電子公告による公告をするときは電子公告調査会社による調査が必要となる点にご留意ください。
なお、分割合同会社が新設合同会社に移転する債務につき併存的債務引受をする場合は債権者保護手続きは不要とされています。
会社分割に伴う労働契約の承継等
分割合同会社から新設合同会社へ承継される事業に就いている従業員は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に基づき、事前の通知を受ける権利や異議を申し出る権利が与えられており、分割合同会社はその従業員に対する一定の手続きをしなければなりません。
新設分割にかかる新設分割計画が作成された日から起算して2週間を経過する日までに、一定の事項を書面によって通知する必要があります。
新設分割の効力発生
新設分割においては、登記が効力発生要件となっているため、新設分割にかかる登記申請をした日に効力が発生します。
そのため、効力発生日として法務局が開いていない土日祝日等を定めることはできません(2025年11月現在)。
新設分割の登記申請
法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任します(会社法第598条1項)。
そして、合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所は登記事項です(会社法第914条8号)。
合同会社Xの社員が株式会社Zであるときに、合同会社Xが新設分割により合同会社Yを設立する場合、新設分割によって設立される合同会社Yの持分は合同会社Xが取得しますので、合同会社Yの唯一の社員は合同会社Xとなり、合同会社Aは職務執行者を選任することになります。-①
次いで、合同会社Xは剰余金の配当として合同会社Yの持分全部を株式会社Zに現物配当したときは、合同会社Yの業務執行社員・代表社員はZになりその旨の登記を行うことになります。
上記において役員に係る登記すべき事項につき、合同会社X及びその職務執行者の登記を省略し、株式会社Z及びその職務執行者の登記のみすることができるかどうかの回答は、某法務局では省略できないというものでした。
添付書類
新設分割の登記は、新設合同会社の設立登記と分割合同会社の変更登記を同時に(連件で)行います。この登記の添付書類の一例は次のとおりです。
【設立会社にかかる登記申請添付書類(一例)】
- 新設分割計画書
- 定款
- 職務執行者選定書
- 職務執行者の就任承諾書
- 分割会社の総社員の同意書
- 債権者保護手続き関係書面
- 分割会社の登記事項証明書(設立会社と管轄法務局が異なる場合)
- 資本金の計上証明書
- 委任状(司法書士に委任する場合)
(分割会社の会社法人等番号を記載した場合は不要)
この他に、印鑑届書と保証書も併せて法務局へ提出します。
【分割会社にかかる登記申請添付書類(一例)】
- 委任状(司法書士に委任する場合)
登録免許税
新設合同会社の登記の登録免許税は資本金の額に1000分の7を乗じた金額(3万円未満の場合は3万円)であり、分割合同会社の登録免許税は30,000円です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。