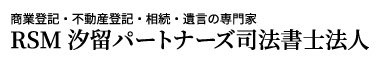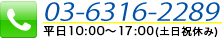商業登記関係 新株予約権の募集事項の取締役(会)への委任と産業競争力強化法第21条の19
新株予約権の募集事項の委任
株式会社は、株主総会の決議によって、募集新株予約権の募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができます。
募集事項の決定を取締役(会)に委任するときは、株主総会では次に掲げる事項を定めます(会社法第238条1項)。
- その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の内容及び数の上限
- 前号の募集新株予約権につき金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
- 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限
無償のストックオプションに係る募集事項を委任する場合、上記1及び2を株主総会で決議することになります。
募集新株予約権の内容
募集事項の一部である新株予約権の内容は会社法第236条1項に定められており、無償ストックオプションを前提とすると、会社法第238条1項に基づき募集事項の決定を取締役(会)へ委任した場合の取締役(会)で決定することができる事項は、主に次の2点です。
- 発行する募集新株予約権の数
- 募集新株予約権を割り当てる日
募集新株予約権の募集事項が取締役(会)へ委任されるケースにおいて、取締役(会)で新株予約権の行使価額や取得条項といった新株予約権の内容を決めることはできません。
募集事項の委任の有効期限
株主総会の決議によって募集事項を取締役(会)へ委任したときは、取締役(会)に基づき発行する新株予約権の割当日が、募集事項の委任に係る株主総会決議の日から1年以内の日である必要があります(会社法第239条3項)。
一度、株主総会の決議により募集事項の委任を受けたとしても、その委任に基づき無期限に取締役(会)で募集事項を決定することができるわけではありません。
取締役会非設置会社と割当ての決定(総数引受契約の承認)
取締役会非設置会社において、株主総会の決議により募集事項の決定を取締役に委任したときでも、募集新株予約権の割当ての決定または総数引受契約の承認は株主総会の決議事項です。
そのため、募集新株予約権を発行するときに、委任に基づき募集事項を取締役が決定した後に、株主総会の決議で募集新株予約権の割当ての決定または総数引受契約の承認をする必要が生じてしまいます。
取締役による当該募集事項の委任に基づく募集事項の決定に加えて、割当ての決定または総数引受契約の承認も取締役の決定で行うには、株主総会の決議で募集事項の委任の決議をするのと併せて、割当ての決定または総数引受契約の承認を取締役の決定で行えるようにする定款変更の決議も行います。
≫取締役会非設置会社において、株式や新株予約権の割当てを取締役の決定で行う方法
募集新株予約権の機動的な発行
募集新株予約権の発行手続きにおける募集事項の委任では、「行使価額」「行使期間」を取締役(会)で決定することができず、委任に基づく募集事項の決定も委任に係る株主総会の決議日から1年以内という期限もあります。
そこで、よりスムーズに取締役(会)の決定に基づき募集新株予約権の発行をすることができるよう「募集新株予約権の機動的な発行に関する制度(以下、「本制度」といいます)」が新設されています。具体的には、産業競争力強化法(以下、「産競法」といいます」第21条の19が新設されました。
≫募集新株予約権の機動的な発行(ストックオプション・プール)に関する制度(経済産業省)
本制度を利用するには経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることその他条件がありますが、本制度を利用すると、「行使価額」「行使期間」も取締役(会)に委任することができ、また、委任に基づき取締役(会)で募集事項を決定できる期間も会社設立日から15年を経過する日の前日までと伸長されます。
なお、委任に基づき募集事項の決定をすることができる他の新株予約権の内容(募集新株予約権の数の上限等)は変わりません。
行使期間
新株予約権の行使期間は、本制度を利用しない場合は株主総会で定める必要がありますが、株主総会で「付与決議日後2年を経過した日から付与決議日後10年を経過する日まで」のような定め方もすることができます。
本制度を利用すると行使期間は取締役(会)が決定することができるようになりますが、税制適格ストックオプションを前提とする場合においては、行使期間に関しては本制度を利用するメリットは少ないかもしれません。
会社設立後15年を経過する日の前日までを割当日とする
本制度を利用する場合、募集事項の委任を受けてから1年以内に当該委任に基づき発行する新株予約権の割当日としなければならないという制限は無くなりますが、割当日において、設立の日以後の期間が15年未満である必要があることから、設立後15年以上経過している株式会社においては本制度を利用することはできません。
経済産業大臣及び法務大臣の確認
この制度を利用するには経済産業大臣及び法務大臣の確認を得ることが求められます。
本制度を利用することができる条件、上記確認を得る方法は ≫募集新株予約権の機動的な発行(ストックオプション・プール)に関する制度(経済産業省) のサイトをご確認ください。
株主となろうとする者への通知
本制度に係る募集事項の委任の株主総会決議があった場合には、その後株主となろうとする者、新株予約権者となろうとする者に対し、当該決議があった旨を通知し、又は通知に準ずる措置を講じなければなりません(産競法第21条の19第2項)。
経済産業省・法務省のQ&AのQ5-1.によると、通知に準ずる措置はウェブサイトに表示する方法がこれに該当します。
≫産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する Q&A(経済産業省・法務省)
決定した募集事項の株主への通知
株主総会の決議による委任に基づき、取締役(会)が募集新株予約権の募集事項を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知することが求められます(産競法第21条の19第3項)。
本制度を利用して新株予約権を発行するときは、上記通知をスケジュールに組み込む必要があります。
有利発行と株主総会の決議
本制度に基づき取締役(会)がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、金銭の払込みを要しないこととすること又は払込金額が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めます。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなりません(産競法第21条の19第3項)。
一 当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
二 当該募集新株予約権を行使することができる期間
三 当該募集新株予約権の数の上限
四 当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から1年以内とする旨
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。