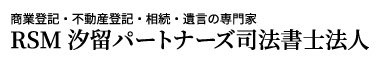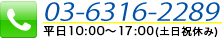商業登記関係 取得請求権付株式に係る取得請求権の行使と株式の交付
取得請求権付株式と行使
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として当該株式会社に対してその取得を請求することができる旨を定めることができ(会社法第107条1項2号)、また、当該株式会社に対してその取得を請求することをできる旨を定めた種類株式を発行することができます(会社法第108条1項5号)。
全部の株式の内容として取得請求権を定めるケースはあまり見かけず、対価として社債、新株予約権、新株予約権付社債を定めるケースも実務ではあまり見かけないところです。
よく見かけるケースは、スタートアップに利用される優先株式に、その対価を普通株式として取得請求権をが設定されるケースです。ここでは普通株式を対価とする取得請求権が付されたA種優先株式につき、その取得請求権が行使される事例を見ていきます。
<前提>発行済株式数が下記内容の株式会社Xにつき、A種優先株式500株の取得請求権が行使される。
1万2000株
各種の株式の数
普通株式 1万株
A種優先株式 2000株
取得請求権付株式の内容
種類株式の内容として当該株式会社の他の株式を対価とする取得請求権を定めたときは、当該種類株式に係る発行可能種類株式総数の他に、次の内容を定款に定めます(会社法第108条2項5号)。
- 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨
- 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間
- 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
取得することを請求することができる期間はA種優先株主となった日以降いつでも、A種優先株式1株の取得請求の引換えに交付される株式は当初普通株式1株とすること多いため、株式会社Xにおいてもそのような定め方をしているものとします。
取得請求付種類株式の取得請求権の行使
取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができます(会社法第166条1項)。
会社法上、この請求は書面によることを求められていませんが、後のトラブルを防ぐために口頭ではなく書面又は電磁的記録で行うことが一般的です。
取得請求権を行使するときは、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにして行います(会社法第166条2項)。
A種優先株式につき株券を発行しているときは、株券不所持の申出がされていない限り、取得請求権の行使の際に当該株券を株券発行会社に提出します(会社法第166条3項)。
発行可能株式総数、発行可能種類株式総数
A種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付するときは、自己株式である普通株式を交付する場合を除き、発行済株式の総数及び発行済普通株式の総数が増えることになります。
普通株式を交付した結果として発行済株式の総数が発行可能株式総数を超過する場合又は発行済普通株式の総数が普通株式に係る発行可能種類株式総数を超過するときは、取得請求権の行使の前提として、発行可能株式総数及び/又は普通株式に係る発行可能種類株式総数の変更を行うことになります。
株式の取得と対価の交付
株式会社Xは、取得請求権が行使された日に、その請求に係るA種優先株式を取得し(会社法第167条1項)、取得請求権を行使した株主は、その請求の日に、普通株式の株主となります(会社法第167条2項)。
A種優先株主がA種優先株式500株の取得請求権を行使した結果、株式会社XはA種優先株式500株を取得し、当該A種優先株主は普通株式500株を取得します。
なお、A種優先株式の内容として取得請求権の対価となる普通株式数に調整式がある場合は、その調整式が適用された結果、交付する普通株式数が550株等となることがあります。
交付する株式数に端数が生じたときは会社法第167条3項に従いますが、端数につき金銭による処理が生じないように交付する株式数の小数第1位を四捨五入する、切り捨てる等の定めが設けられていることが少なくありません。
取得請求権行使後の発行済(種類)株式数
A種優先株式の取得請求権が行使され、発行会社がA種優先株式の取得と引換えに自己株式ではない普通株式を交付したときの発行済株式の総数及び各種の株式の数は次のとおりです(①)。
1万2500株
各種の株式の数
普通株式 1万500株
A種優先株式 2000株
上記①の後、取得したA種優先株式につき、自己株式の消却をしたときの発行済株式の総数及び各種の株式の数は次のとおりです。
1万2000株
各種の株式の数
普通株式 1万株
A種優先株式 2000株
全て自己株式たる普通株式を交付したときは発行済株式の総数及び各種の株式の数に変更は生じません。
取得請求権付種類株式の取得と登記
取得請求権が行使され、自己株式ではない普通株式を交付したときは発行済株式の総数及び各種の株式の数に変更が生じますので、変更が生じてから2週間以内に変更登記を申請します。
当該登記の添付書面の一例は次のとおりです。
- 取得請求権の行使書
- 委任状(代理人に委任する場合)
取得したA種優先株式につき自己株式の消却も行った場合は次の書面も添付します。
- 取締役会議事録(取締役会非設置会社は株主総会議事録)
- 株主総会議事録を添付する場合は株主リスト/li>
- 取締役会決議がみなし決議の場合は定款
変更登記が不要であるケース
取得請求権の対価として交付する普通株式であり、取得したA種優先株式を消却しない場合は、発行済株式の総数及び各種の株式の数に変更が生じませんので、変更登記は不要です。
(種類株式の内容に変更が生じないことが前提です。)
対価となる株式数の変更
取得請求権の対価となる株式数につき、調整式が設けられている場合、取得請求権の行使の前提として種類株式の内容の変更を求められることがあります。
種類株式の内容が、取得請求権の行使の対価がA種優先株式1株につき当初普通株式1株であるときに、ダウンラウンドによる調達があった等してこの対価が自動調整により普通株式2株になった場合、この変更が生じたことを登記簿に反映させた上で取得請求権の行使による変更登記をすることが求められるケースです。
株式分割による新株予約権と同様に、自動調整による変更が生じたことを示すことでその内容の変更登記まで必須とされるかどうか、必要に応じて事前に法務局へ確認ください(内容の変更登記をした方が、第三者が登記簿を見たときに取得請求権の行使により将来増加する普通株式数が分かります)。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。