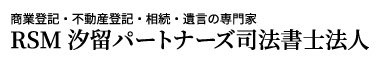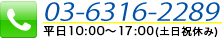商業登記関係 代表取締役の変更と本店移転登記の同時申請における代表取締役等住所非表示措置の申出
代表取締役等住所非表示措置の申出
代表取締役等住所非表示措置(以下「非表示措置」といいます。)の申出を行うときは、本店の実在性を確認した旨の書面が求められます。
本店の実在性を確認した旨の書面は、具体的には次のどちらかです。
- 株式会社が受取人として記載された配達証明書(+株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証)
- 登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
株式会社X(東京都港区●●一丁目1番1号)の代表取締役Aが、自身の住所変更登記と同時に非表示措置の申出をするときの実在性を確認する本店は東京都港区●●一丁目1番1号の本店です。
また、株式会社Xの代表取締役Aが辞任して新たに代表取締役Bが就任する場合において、この変更登記と同時に非表示措置の申出をするときの実在性を確認する本店も同様に東京都港区●●一丁目1番1号の本店です。
本店移転の登記と非表示措置の申出
本店を他の登記所の管轄区域内に移転する(以下「管轄外本店移転」といいます。)登記をするときは、その新所在地における登記と同時に非表示措置の申出をすることができます。
株式会社Xが本店を東京都渋谷区■■一丁目1番1号に移転するケースにおいて、その本店移転登記と同時に非表示措置の申出をするときの実在性を確認する本店は東京都渋谷区■■一丁目1番1号です。
これは、原則として実在性を確認する本店所在場所が登記申請書に記載する申請人たる法人の本店所在場所であるためです。
管轄外本店移転登記を申請するときに、新所在地における登記と同時に非表示措置の申出をすることができるとありますので、非表示措置の申出をするのであれば、東京法務局港出張所経由で申請する東京法務局渋谷出張所宛ての(下記②の)申請において非表示措置の申出をすることになります。
代表者変更又は住所移転と本店移転の登記
株式会社Xにおいて、2025年2月10日付けで代表取締役がAからBに交代し、同日に本店を東京都渋谷区■■一丁目1番1号に移転した場合はどうなるでしょうか。
管轄外本店移転の登記を申請するときは、株式会社Xの場合は東京法務局港出張所に対して、東京法務局港出張所に対する本店移転の登記申請(1/2)と、東京法務局渋谷出張所に対する本店移転の登記申請(2/2)を連件で申請します。
上記(1/2)の登記申請において他の変更登記も併せて行うことができるため、①(1/2)として役員変更と本店移転の変更登記を、②(2/2)として本店移転の変更登記を申請することはよく行われているところです。
閉鎖事項証明書にBの住所の記載を希望するかどうか
①②の登記を申請する場合、①の登記と同時に非表示措置の申出をすることも、②の登記と同時に非表示措置の申出をすることも手続き上は可能です。
ところで、①②の登記申請した場合の役員欄については、閉鎖事項証明書に(代表)取締役がBに交代した旨の記録がされ、履歴事項証明書にはBが(代表)取締役に就任した旨の記録しかされません。
つまり、①の登記と同時に非表示措置の申出をせずに、②の登記と同時においてのみ非表示措置の申出をすると、履歴事項証明書にはBの住所は非表示措置が講じられているものの、閉鎖事項証明書にはBの住所が全て記載されることになるリスクがあります。
非表示措置の申出をしたい人(ここではB)が、誰でも法務局で取得することができる閉鎖事項証明書に住所を記載されることを望むことは無さそうです。
なお、①の登記と同時に非表示措置の申出をしたときは、新本店の登記簿事項証明書では非表示措置が自動継続されますので、②の登記と同時に非表示措置の申出をする必要はありません。
≫代表取締役等住所非表示措置が自動的に継続されるケース、されないケース
実在性を確認する本店所在場所
①の登記と同時に非表示措置の申出をするときに実在性を確認する本店所在場所は、①の登記申請書に記載する登記申請人たる法人の本店所在場所です。
つまり、東京都渋谷区■■一丁目1番1号となります。
もし仮に(代表)取締役をAからBに交代する役員変更登記だけを先行して行っておくようなことがあるのであれば、当該役員変更登記と同時に非表示措置の申出をするときの実在性を確認する本店所在場所は東京都港区●●一丁目1番1号となります。
代表取締役の住所変更+管轄外本店移転の登記
株式会社Xにおいて、代表取締役がAからBに交代するのではなく、Aの住所変更と管轄外本店移転が生じた場合の登記及び非表示措置の申出についても上記と同様です。
(1)代表者住所移転+本店移転の変更登記と(2)本店移転の変更登記を申請する場合、(1)の登記と同時に非表示措置の申出をしない限り、Aの移転後の住所が閉鎖事項証明書に記載されるリスクがあります。
非表示措置は、司法書士としてはとても気を遣うところですね。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。