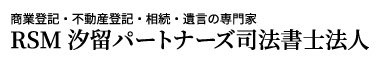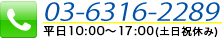相続関係 遺言関係 遺言を書こうと思った方に読んで欲しいページ
相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人といいます)が有していた財産に属する権利義務(相続財産をいいます)を相続人が引き継ぐことをいいます。ここでいう「義務」と書いているのは、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけではなく、マイナスの財産(借金など)も相続人が引き継ぐことを意味しています。
法定相続人
被相続人の相続財産を誰が引き継ぐのかは民法に定められています。簡単にまとめると次のとおりです。また、こちらの記事(法定相続人)も参照ください。
| 配偶者がいる場合 | 配偶者は必ず相続人となる |
|---|---|
| 第1順位相続人 | 被相続人の子や孫 |
| 第2順位相続人 | 被相続人の直系尊属(父母や祖父母) |
| 第3順位相続人 | 被相続人の兄弟姉妹やその子 |
先順位の者が生存していて相続人となる場合は、後順位の相続人は相続する権利がありません。
なお、子の子(つまり被相続人の孫)や祖父母、兄弟姉妹の子(甥や姪)は、それぞれ子や父母、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているなどの場合のみ相続人となります。
遺言とは
遺言とは、被相続人の最終的な意思表示や希望を表したもののことをいいます。自分が死んだあとに、相続財産の処分等に対して自分の意思を反映することができるということです。これが遺言の最大の特徴といえます。
遺言と似たような言葉に遺書があります。遺書の一般的なイメージとしては、死ぬ前に自分の想いや希望を綴った手紙になりますが、方式は決まっておらず自由に書くことができます。
それに比べて遺言は、被相続人の意思を明確に担保するために法律によってその方式が定められており、それを満たしていない遺言は無効となってしまいます。上記のとおり、遺言は死後に自分の意思を相続財産に反映することができる一方で、被相続人の死後はその意思が本当なのかどうか確認することはできなくなってしまうので、その方式は厳格なものとなっています。
遺言を書くことができる人
遺言は満15歳以上の人なら誰でも書くことができます。ただし、遺言の内容及びその結果を認識することができる意思能力が必要とされています。意思能力があれば、手が震えて文字を書くことができない、目が見えない、話すことができない、体を動かすことができない人であっても遺言を作成することは可能です。成年被後見人であっても、意思能力が回復している状態で、医師2名以上の立会いのもと遺言を作成することができるとされています(民法第973条)。
何から手をつけるか
いざ遺言を書こうと思い立っても、何から手をつけていいのか分からない方もいらっしゃるかと思います。
まずは、ご自身が所有しているプラスの財産である土地、建物、車、あるいは預貯金、株式などの有価証券がどれだけあるのか一覧表(財産目録といいます)を作成してみてはいかがでしょうか。相続人が承継することになるマイナスの財産(借金)も併せて財産目録に記載してください。
相続財産が確定したら、自分の相続人が誰になるのかも書き出してみてください。誰が相続人となるかは法律で定められているため、思い込みで決めないように気をつけましょう。
こちらの記事もご参照ください(遺言を書くときに、まず何をするべきか)(法定相続人)。
各遺言の方式
遺言には主に3つの方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。
それぞれの遺言にはメリット、デメリットがあり、遺言を書かれる方に一番合った遺言形式を選んでください。
なお、当事務所では公正証書遺言をお勧めすることが多いです。もちろん、お客様によっては公正証書遺言がベストではないこともありますので、そのときは自筆証書遺言や秘密証書遺言をお勧めすることもあります。
遺言の方式、各遺言のメリット、デメリットについてはこちらの記事をご参照ください(遺言の種類と選び方)。
遺言に書けること(遺言事項)
遺言書に記載することにより遺言としての法的効力が生ずる事項(遺言事項といいます)は、法律によって定められています。つまり、遺言事項以外のことを遺言に記載しても法的効力が認められません。遺言事項についてはこちらの記事をご参照ください(遺言事項について)。
遺言事項以外のことを遺言に書いてはいけないのかというと、そうではありません。むしろ、書かれているケースは多いと思います。特に自分が相続財産について相続人間で差をつけた理由や相続人への感謝の想いといった付言事項を、当事務所でも書くことをお勧めしております。他にも自分が死んだ後の葬式はこうして欲しい、墓はこうして欲しいといった希望を書かれるケースもあります。
遺言の記載方法
遺言の内容は明確であることが望ましいです。なぜなら、遺言の内容が2つ以上の意味で解釈ができてしまうとその解釈をめぐって相続人同士で争いになってしまう可能性が生じてしまいますし、何より本人の意思や想いの実現が叶わなくなってしまうかもしれません。その遺言の内容をを誰が見ても理解できる、同一の解釈ができるものであるような明確な記載をしておくと遺言が無効となる可能性や後で内容をめぐって揉める可能性が低くなります。
主な注意点
遺言の書き方として、主な注意点は次のとおりです。
■法定相続人には「相続させる」、法定相続人以外の人には「遺贈する」と記載してください。「~~さんがもらってください」「~~さんにあげようと思います」という表現は避けた方がいいでしょう。
■誰に相続させるのか、対象となる人は明確に記載してください。一般的には氏名、生年月日、続柄(と住所)を記載します。
■不動産の記載は、登記簿謄本に記載されているとおりに記載してください。自宅とか裏の畑、那須高原の別荘などの記載は避けましょう。
■預金については、銀行名、支店名、口座番号など、どの口座を対象としているのか明確にしておきましょう。
■遺言執行者を指定しておくと相続手続きがスムーズにいきますので、指定することをお勧めしております。ご依頼をいただければ当事務所で遺言執行者を承ります。
■遺言作成後に取得する財産もあるでしょう。そのような遺言に記載のない財産についても、誰に相続させるのか記載しておくと後で揉めないかもしれません。
■付言事項として、家族への想いや財産配分の理由などを入れておくと、相続人同士で紛争となる可能性は下がるかもしれません。
■財産を個別指定するのではなく全財産を○○に相続させるという遺言も有効です。
遺言執行者の選任
遺言において遺言執行者を選任することができるとされています。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをする人のことをいいます。遺言の内容を実現する、とは例えば預貯金や不動産を相続人Aに相続させるという遺言内容であれば、金融機関において被相続人名義の預貯金口座を解約したり、法務局において不動産の名義変更手続きをしたりすることをいいます。
遺言執行者の選任が必要な遺言事項
遺言事項のうち、遺言執行者の選任が必ず必要になる事項があります。
それは次のとおりです。
①認知
②推定相続人の廃除
③推定相続人の廃除取消し
④一般財団法人の設立行為
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者は必ず選任しなくてはならないものではありません。しかし、遺言執行者を選任するメリットがあるため、多くの遺言において遺言執行者を選任する旨の記載があることも事実です。
(被相続人の)最大のメリットは、遺言の内容が実現される可能性が高まることです。遺言の内容のとおりに相続財産が分配されるのかどうかは、被相続人の死亡後は、被相続人は確認をすることができません。遺言執行者は遺言の内容を実現する義務があるため、実現される可能性は高くなります。
相続人のメリットとしては、預貯金口座の解約等の面倒な手続きを遺言執行者に任せてしまえる点にあるかと思います。
遺言執行者に専門家を選任する
遺言執行者は戸籍を集めたり、各役所に手続きが必要であったり、必要に応じて不動産の売却等をしなくてはならないこともあります。遺言執行者の仕事は(遺言の内容によっては)決して簡単なものではありません。
報酬という費用はかかってしまいますが、相続人のうちの1名ではなくそのような手続きに精通している司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に選任するという方法もあります。
遺言を書くにあたり
誰にどれだけ財産を相続させる(遺贈する)かは、財産所有者たる遺言を書く人の自由です。相続人のうち誰か1名に、あるいは第三者や慈善団体などに全財産を相続させ(遺贈し)ても問題はありません。
ただし、兄弟姉妹(とその代襲相続人である甥、姪)を除く法定相続人には遺留分というものがあります。
遺留分とは
遺留分とは相続人(兄弟姉妹、甥、姪を除く)が最低限請求することのできる相続財産の割合のことをいいます。例えば相続人が子2名(A、B)いた場合、各相続人の遺留分はそれぞれ4分の1ずつとなります。全財産をAに相続させることを内容とする遺言があったとしても、BはAに対して全相続財産のうち4分の1に当たる財産を請求することができます。
遺留分は請求をすることができる、ということになっておりますので遺留分に当たる財産を請求するのかどうかはB次第であり、必ず請求されるとは限りません。もしBが遺留分に当たる財産を請求しなければAはBに財産を分ける必要はありません。遺留分を請求する権利にも時効があり、次の期間までに権利を行使しないと時効により消滅します(民法1042条)。
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
・相続開始の時から10年を経過したとき
遺留分という言葉はだいぶ普及してきていると思います。テレビドラマなどで聞いたりすることもありますし、インターネットでも遺留分に関する記事を目にすることがあります。遺留分自体はは正当なBの権利であり行使することは何の問題もありませんが、遺留分をBがAに請求することはAにとって面白いことではなく、そのことによってAB間の仲が悪くなってしまう可能性もあります。
もしそうなる可能性があるのであれば、最初から相続財産の4分の1に相当する財産をBに与える旨、AとBに遺す財産を均等にしなかった理由・想いを遺言に記載しておいた方がいいかもしれません。また、全財産をAに相続させるという遺言内容にした場合も、遺留分の請求がBからAにされた場合に備えて、全体の相続財産のうちどのような順番(まず金銭、次に株式などの証券、など)で4分の1に相当する相続財産をBが受け取ることができるか遺言で指定しておくこともできます。
付言事項
相続分の差は愛情の差?
上述のとおり遺言事項以外のことを遺言に記載しても法的な効力はありません。しかし、遺言によって相続人が取得する相続財産に差を設けたりするときは、その遺言を読んだときに相続人がどのような気持ちになるでしょうか、特に受け取る相続財産が少ない相続人は快く思わない可能性が高いかもしれませんね。受け取る相続財産が少ない相続人がどの点についてマイナスの気持ちを抱くのかと言うと、受け取る財産が少なくて残念だということもあるとは思いますが、それ以上に他の相続人と差をつけられたという点に対してということが根本にあるように思います。
相続人が子ABの2名だけであった場合、相続財産のうちAに4分の3、Bに4分の1の割合で相続させる以上、という内容の遺言は一見法律的には何の問題もないように見えます。実際、法的な要件を満たしている限り有効なものであり、Bの遺留分も侵害していません(不動産などがある場合は、相続分の指定は避けたほうがいいかもしれません)。
付言事項は家族への最後のメッセージ
しかしBは何で自分の方がAより少ないのだろうかと考えるはずです。そして被相続人は遺言を書いてAの相続財産割合を多くしたのには理由があるはずです。相続人(家族)へのメッセージとして、遺言書の最後に、このような内容の遺言にしたのかその理由を相続人全員に理解をしてもらえるように付言事項を入れておくことでBも納得してくれるかもしれません。家族への想いを付言事項として入れておくことで相続人同士の争いが防げたケースを何度も見てきました。弊所へ遺言作成のご依頼をいただいた際は、付言事項を入れることをお勧めしております。
遺言の保管方法
遺言は自分が死ぬまでは内容(または場所)を知られたくないけれども、死後は発見して欲しい、という扱いがなかなか難しいものです。見つかりやすい場所に保管をしておけば、もしかしたら偽造されてしまったり捨てられてしまう可能性もあります。反対に誰も見つけられないような場所に保管をしておけば、死後に誰も遺言を見つけられず相続人に想いを伝えることができなくなってしまう可能性もあります。
遺言の種類による保管方法
自筆証書遺言は見つけられない、無くしてしまう、偽造されてしまうリスクが一番高い遺言です。家族が存在は知っているが開けることができない貸金庫に入れておいたり、あるいは司法書士や弁護士などの専門家に保管の依頼をすることもできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言は、公証役場に保管されるため無くしてしまうリスクや偽造されてしまうリスクは低いといえます。しかし、遺言を書いたことを相続人の誰もが知らなければ、死後もその存在が知られないままとなってしまうリスクはあります。相続人が公証役場で遺言検索システムを利用すればその存在が分かりますが、そのシステム自体も世間に浸透しきっているとはいえないと思います。そうであれば、発見されないというリスクを回避するために、誰かに遺言を作成したこと、公証役場に遺言があることを伝えておいてもいいかもしれません。
後からでも修正可能
遺言は一度書いたら、二度と内容を変更することができないというものではありません。修正は何回でも行うことができます。取り消すことも可能です。
不動産XはAに相続させようと思っていたが、やっぱりBに相続させることにしたい、と心変わりすることもあるでしょう。
破棄
自筆証書遺言は、その遺言書を破棄することにより、その内容が取り消されたことになります。自筆証書遺言自体がなかったことになりますので、分かりやすい取消方法といえます。
公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているため、お手元にある謄本などを破棄したとしても取り消されたことにはなりません。
新しい遺言
以前書いた遺言とは別に、その以前書いた遺言の内容を撤回するという遺言を新しく作ることにより、以前書いた遺言を取り消すことができます。以前書いた遺言の内容の一部だけを訂正したい場合は、以前の遺言の内容と矛盾する遺言や一部だけを訂正する旨の遺言を新しく作ることにより一部訂正が可能です。
例えば、前述の例ですと、不動産XはBに相続させるという内容の遺言を新しく作ることが考えられます。
しかし何通も日付の異なる遺言が出てくると混乱の元になってしまう可能性がありますので、それを避けるためにも以前の遺言は破棄し、新しく書き直すという方法もお勧めです。
遺言自体を訂正
自筆証書遺言の場合、遺言を自分で訂正することが可能です。しかし、遺言は要式が細かく定められており、訂正する際にも要式が定められています。それを知らずに、ただ二重線を引いて隣に訂正後の文言を加えても、その訂正は有効となりません。訂正自体が無効となり、訂正前の遺言が有効となってしまうこともありますので、であれば新しく遺言を書き直したほうがいいかもしれません。
遺言の内容に反する行為
前述の例でいえば不動産Xを被相続人がその生前にCに売却してしまった場合、不動産XをAに相続させるという遺言はその部分においてのみ取り消されたとみなされます。不動産X以外の財産にかかる部分は、依然有効のままです。
遺言は死後に訂正することができない
遺言は被相続人の最終的な意思表示です。それ故に死後に遺言を訂正することは残念ながらできません。その遺言の内容がしっかりと実現したかどうかを見届けることも残念ながらできません。
そうであれば、そのような大切な遺言を訂正しなくてもいいように、そして遺言が無効とならずにしっかりと実現されるためにも遺言の作成を専門家に手伝ってもらうことは悪い選択ではないと思います。
遺言は、書き方も大事ではありますが、実質的な観点から相続税についても検討をしなければ意思の実現が叶わないケースもあります。そのような点からも、遺言の作成のご相談は、各士業専門家の集まる汐留パートナーズグループにご相談ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。