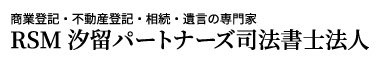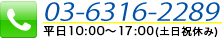相続関係 不動産登記関係 遺言による相続登記が、第三者への対抗要件に(相続法改正)
相続法の改正
2019年(令和元年)7月1日に改正された相続法が施行されました。
相続法の改正された内容の一つとして、遺言により不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしないと第三者へ対抗することができない、というものがあります(民法第899条の2)。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
相続法改正の趣旨
被相続人A、相続人が長男Bと次男Cであるケースで、Aがその所有する不動産は全てBに相続させる旨の遺言をのこしていたとします。
(不動産を相続しない)Cの債権者からすると、亡Aが不動産の名義人であり、Cが不動産の一部を相続するであろうから、万が一Cが返済できない場合でも不動産の売却代金から回収できると考えるかもしれません。
ところで、遺言の内容を知らない債権者からすると、当該遺言の存在はその期待を一方的に奪うものであり、現在の権利関係が正しく反映されていない状況は、登記制度に対する信頼を揺るがす一因ともなり得ます。
改正された相続法によれば、自分の権利を守るためには、遺言がある場合でもその登記をして自分の権利を保全してください、ということになりました。
今までとの違い
2019年6月以前に発生した相続においては、遺言があれば、その相続登記をしなくても第三者に対して自分(B)が所有者であることを主張することができました。
上記の例で言えば、Bは、Cの債権者に対して、自分が所有者であるから差し押さえ等をしても無効であることを、相続登記をしなくても言うことができたのです。
遺言があれば、それが有効なものである限り、その相続登記をしなくても遺言だけで第三者へ所有権を主張できるという、遺言が非常に強力なものとして存在をしていました。
相続登記と対抗要件
改正された相続法によると、遺言によって不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。
もし、遺言によって不動産を承継した相続人以外の人が、その相続登記よりも先に何かしらの登記を入れてしまった場合、当該相続人の相続分を超える部分については、自身がその不動産の所有者であることを主張することが極めて難しくなります。
改正相続法が施行されたことにより、登記はいつでもいいや、、、と放置をしておくと、ある日突然、自分の所有権が脅かされる事態が生じ得ることになったと言えます。
第三者とは
不動産を遺言によって相続した相続人と対抗関係になり得る第三者とは、(遺言があるために不動産を相続しない)相続人が不動産の一部を相続したとして取引等に入った相手方の個人や法人が該当します。
典型的な例としては、(遺言があるために不動産を相続しない)相続人の債権者でしょうか。
債務者が相続したであろう不動産の持分について、差し押さえ等をするケースが考えられます。
また、(遺言があるために不動産を相続しない)相続人が自分の持分について誰かに売却してしまうようなケースも、当該買主は第三者に該当します。
なお、相続人同士は第三者に該当しないため、対抗要件たる登記がなくても遺言によって不動産を相続した相続人は、他の相続人に対し、自分の権利を主張することができます。
対抗要件が必要な範囲
第三者へその所有権を主張するために対抗要件が必要とされる範囲は、自分の法定相続分を超える部分についてのみです。
遺言によって不動産を相続した相続人も、自分の法定相続分については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することが可能です。
被相続人A、相続人が長男Bと次男Cであるケースで、自宅を長男Bに相続させる旨の遺言があった場合、長男Bは自身の相続分である持分2分の1については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することができます。
一方で長男Bは、自分が遺言によって相続することになる残りの持分2分の1については、相続登記をしない限り第三者へ対抗することができません。
いつから改正法が適用されるか
改正された相続法は、2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続について適用されます。
2019年6月以前に発生した相続については、改正前の民法が適用されますので、遺言があれば相続登記をしなくても、第三者に対抗することは可能です。
2019年6月以前に遺言が作成され、2019年7月以降に相続が発生したのであれば、改正後の相続法が適用されますので、第三者へ対抗するためには相続登記が必要となります。
解決方法は相続登記をすること
遺言により法定相続分を超えて承継した部分につき、登記を先にした方が不動産の権利を得るのであれば、解決方法は相続登記を早くすることです。
相続放棄や相続税の申告・納付と異なり、相続登記にはしなければならない期限や罰則というものがありません。
そのため、相続登記はつい後回しになってしまいがちな手続きかもしれません。
しかし、遺言がある場合の相続登記の重要性は、2020年7月以降格段に増したと言えます。
相続に関わる専門家(弁護士、税理士、行政書士等)の先生も、遺言がある場合の相続案件においては、相続人のためにも相続登記を勧めていただければと思います。
相続登記をする
上記のとおり、遺言により不動産を相続した人がその権利を保全するための唯一の方法は、できるだけ早く相続登記をすることです。
不動産を承継しない相続人の債権者が、当該相続人が相続によって不動産を相続する権利があることを把握するまでには時間がかかると思われますが、相続登記を怠ったために権利の一部を失う状態は早く解消しておいた方がいいでしょう。
特に、自筆証書遺言による相続登記をするためには家庭裁判所の検認手続きが必要ですので(2020年1月現在)、公正証書遺言に比べて相続登記をするまで時間がかかります。
遺言による相続登記をご検討されている方は、次のページをご確認ください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。