バリューチェーン全体におけるサステナビリティ対応:戦略的に進めるために
2025年7月22日
はじめに
サステナビリティへの対応は、もはや企業価値を高めるための選択肢ではなく、必然となりつつあります。人権や生物多様性といった地球規模の課題が顕在化し、国際的な規制が強まる中、ESG投資も拡大しています。こうした背景の下、企業には自社内の取組みにとどまらず、「バリューチェーン全体を通じた責任ある行動」が求められています。
ここでいう「バリューチェーン」とは、一言でいえば、企業が事業を行う上で外部と交わすあらゆる相互作用、資源、関係性の集合体を指します。そして、「バリューチェーン全体を通じた責任ある行動」とは、原材料・サービスの調達から、製品・サービスの提供、流通、消費、廃棄に至るまでの一連のプロセスに関わるあらゆる関係性と作用に、企業としての倫理的・環境的・社会的責任を果たすことを意味します。
そのバリューチェーン全体の中で、例えば「責任ある調達」や「サステナブル調達」といった個別の事業ポイントを、全体の構造との関係性の中で捉え直す必要があります。また、こうした視点は、自然環境との関係性だけでなく、人権や地域社会など、より広範な社会との関係性を統合的に捉えることを促します。
上記を前提として、サステナビリティを単なるCSR、リスク管理、または規制対応にとどまらず、戦略的かつ全体最適を見据えたバリューチェーンマネジメントをどのように進めたらいいのでしょうか。以下では、企業がサステナビリティをバリューチェーン全体で戦略的に進めるための要点を、下記に整理していきます。
バリューチェーンを俯瞰する視点からの戦略設計
3側面の調和
そもそもサステナビリティ(Sustainability)とは、環境・社会・経済の3側面の調和を図り、将来世代にも持続可能な価値を引き継ぐ社会を実現しようとする概念です。「持続可能性」という言葉が一人歩きしがちな中で、この3側面のバランスと相互作用を改めて中心に据え、企業活動やバリューチェーン全体を捉え直すことが必要です。
とりわけ近年では、人間の経済活動が引き起こす自然環境の劣化が深刻化し、その影響が社会的弱者や将来世代に及ぶ構造が明らかになってきました。こうした中で、サステナビリティに関する情報開示や説明責任が、企業に対してより強く求められるようになっています。
このような背景の下、企業経営においては、その場しのぎの短期的対応ではなく、中長期的な視座に立った価値創造の方向転換が問われています。サステナビリティは、リスク管理のための付属的課題ではなく、経営の根幹に関わる戦略課題であり、バリューチェーン全体の構造を俯瞰しながら、3側面の調和に基づいて意思決定を行う視点が不可欠です。
俯瞰的手法としてのマッピングアプローチ
上記を踏まえ、戦略上、まず企業に求められるのは、自社のバリューチェーン全体を「俯瞰」する視点の確立です。環境・社会面での影響を把握し、サステナビリティ対応をバリューチェーン全体で戦略的に進めていくためには、まず「何が課題で、どこに影響があるのか」を俯瞰的に整理する必要があります。ここで重要となるのが、マッピングアプローチです。
端的にいいますと、マッピングとは、サステナビリティ課題をバリューチェーン全体にわたって可視化し、構造化するプロセスを指します。これは、いわば「全体地図」を描く作業であり、どのステークホルダーに、どのような影響(リスク/機会/責任)が発生し得るかを、各バリューチェーン上の工程(調達、生産、物流、販売、使用、廃棄)に結びつけて分析します。
たとえば、温室効果ガスの排出源をScope1(自社の直接排出)、Scope2(購入した電力等による間接排出)、Scope3(バリューチェーン上の他者による間接排出)に分類し、Scope3の主要な排出項目を特定することは、脱炭素戦略を立てるうえで欠かせません。この分類をベースに、水リスク、労働環境、人権リスク、生物多様性への影響、循環経済の可能性などが、それぞれの事業活動とどのように関係するのかを整理し、課題と影響のホットスポット、またサプライヤーや消費者といった関係者との協働の在り方も見えてきます。
サプライチェーンリスク管理の視点から
特に近年では、自然災害や地政学的リスク、強制労働といった倫理的問題など、サプライチェーンに起因する事業中断リスクが顕在化しており、「サプライチェーン・リスク管理」の視点からもバリューチェーン全体の可視化と管理が重要性を増しています。なお、「サプライチェーン」とは、原材料の調達から製品の供給に至るまでの物流・取引ネットワークを指すのに対し、「バリューチェーン」は、企業活動の全体を通じてどのように価値を生み出しているかという構造を示します。サステナビリティの文脈では、サプライチェーンを「一部」として内包しつつも、バリューチェーン全体にわたる戦略的視点の確立が、気候変動対応や人権配慮、自然資本への責任を果たすうえで不可欠となっています。
SDGsの視点から
上述のようなマッピングのアプローチは、SDGs(持続可能な開発目標)の17目標・169ターゲットとの関係性を見る上でも有効です。企業のバリューチェーン上の活動をマッピングアプローチを通してSDGsとの関係性を見ることによって、企業の貢献領域やリスク対応を整理するうえで活用できます。たとえば以下のような項目が企業のバリューチェーン上の取り組みと密接に結びついています。
- 目標12「つくる責任 つかう責任」:製品ライフサイクル全体における資源効率や廃棄削減
- 目標13「気候変動に具体的な対策を」:Scope3排出量を含めた脱炭素戦略
- 目標8「働きがいも経済成長も」:サプライヤー国・地域での労働環境・人権配慮
- 目標15「陸の豊かさも守ろう」:森林破壊や土地利用に関わるサステナブル調達
企業は、自社の事業活動がどのSDGs目標にプラス/マイナスの影響を与えているかをマッピングし、戦略的な優先課題の特定(マテリアリティ分析)や、SDGsベースでの価値創造に繋げることが期待されています。
このように、マッピングは単なる分析手法ではなく、「どこから始めるべきか」「何を深めるべきか」を見極めるためのナビゲーションツールであり、バリューチェーンを軸にサステナビリティ戦略を設計する上で、極めて有効な第一歩といえるでしょう。これに加えて、社会面において人権・労働環境の適正さ、地域社会への影響、生物多様性の保全などの非財務的リスクも重要です。人権に関していえば、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」に基づく人権デューデリジェンスがバリューチェーンの一角として捉えるとことが必要な場面も増えています。今後はこうした非財務情報の開示が、企業の評価や信頼性に直接関わってきます。
脱炭素とグリーン調達──Scope3排出量への対応
次に、企業がサステナビリティをバリューチェーン全体で戦略的に進めるため主局面の1つ、脱炭素とグリーン調達に焦点を当てて、解説していきます。脱炭素は、企業が2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標に対応するための最重要テーマです。Scope1(自社活動)、Scope2(購入電力)に加え、Scope3(取引先や物流、使用・廃棄による間接排出)の管理が不可欠です。実際、多くの業種ではScope3が排出の大半を占めるため、真の脱炭素はバリューチェーン全体の変革なしには達成できません。
この点で、サステナブル調達(Sustainable Procurement)の考え方が重要になります。これは、価格や納期だけでなく、環境や人権、倫理に配慮した基準で仕入先を選定・管理するアプローチです。ISO20400などの国際指針に沿い、企業の調達方針に統合することで、脱炭素と倫理的責任を両立させることが可能になります。
グリーン製品(下記5.参照)の開発も、Scope3対策の重要な一環です。製品のライフサイクル全体を通じて環境負荷を最小化する「エコデザイン」や、「ライフサイクルアセスメント(LCA)」の活用が加速しています。再生材の使用や省エネ性能の高い設計は、消費者や調達先からの選好にもつながり、差別化の源泉となります。
このように、Scope3削減の鍵は、取引先や顧客との連携にあります。企業単独では達成しえないため、バリューチェーン全体での協働とインセンティブ設計が、経営の実効力を左右します。
人権デューデリジェンスとCSDDD──欧州規制のインパクト
サステナビリティをバリューチェーン全体で戦略的に進めるためのもう一つの主局面として、ESGの「S(社会)」における最重要テーマ、「人権デューデリジェンス(HRDD)」があります。これは、企業が自社およびサプライチェーンにおける人権リスクを把握し、予防・是正策を講じる責任ある企業行動を指します。
この取り組みは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」に端を発し、OECDガイドライン、ILO条約などとも整合する国際的潮流です。これまでは任意的な取り組みと見なされていましたが、近年では法制化が進んでいます。その代表が、EUにおける「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」です。この指令は、一定規模以上の企業に対し、サプライチェーン全体における人権・環境リスクの調査、是正、開示を義務付けるものです。違反企業には罰則が科される可能性があり、取締役にも責任が課される点が大きな特徴です。
この規制はEU域内企業だけでなく、EU市場に一定の売上規模で関与する非EU企業にも適用されるため、日本企業にも直接影響します。すでにドイツでは「サプライチェーンデューデリジェンス法」が施行済みであり、各国法制化の動きは連動しています。
経営者にとっては、単なるコンプライアンス対応ではなく、取引先の選定や調達方針、契約条件の見直し、苦情処理メカニズム(グリーバンスメカニズム)構築といった、実務的な対応が急務となります。
企業戦略と連結したバリューチェーンマネジメント
上記で述べたことを踏まえ、バリューチェーン全体にわたってサステナビリティを実装するためには、企業戦略と連結したバリューチェーンマネジメントが不可欠です。そのマネジメントの鍵は、サステナビリティを一部門の管理業務ではなく、経営・購買・商品開発・営業といった中核業務の判断軸に内在化させることにあります。それには、企業全体のガバナンス体制の見直しも求められます。
責任ある調達ガイドライン
そうした見直しの実務的ツールのひとつになり得るのが、「責任ある調達ガイドライン」です。これは、ISO20400(持続可能な調達のための国際ガイダンス)やOECD多国籍企業行動指針、国連「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」などを参照し、企業が自社の調達方針においてサステナビリティリスクや人権・環境配慮の原則を明示するものです。
このガイドラインは、グローバル企業を中心に策定が進んでおり、今や上場企業や大手企業においては策定・運用が一般化しつつあります。しかし、形骸化を避け、実効力のあるガイドラインとするには、単なるルールの提示にとどまらず、サプライヤーとの双方向の対話や能力構築支援といった運用面での工夫が求められます。
つまり、「責任ある調達ガイドライン」は、企業による一方的な要求事項のリストではなく、バリューチェーンにおける透明性・説明責任を高める共通フレームワークとして捉え直す必要があります。経営戦略の中核に据え、調達部門やサプライヤーと連携しながら、サステナビリティ統合を実質的に推進するための実装基盤として位置づけることが重要です。
グリーン製品・ネイチャーポジティブ
さらに、「グリーン製品」や「ネイチャーポジティブ」といった概念も、戦略に立脚するバリューチェーンマネジメントと密接に関係します。グリーン製品の開発は、設計段階からの環境配慮、原材料の選定、製造過程のエネルギー効率、流通の最適化、さらには使用後の再利用やリサイクルに至るまで、バリューチェーンの各段階における継続的な改善を求めます。単なる技術開発ではなく、全体最適としてのサステナブルなバリューチェーン設計が問われるのです。
一方、ネイチャーポジティブとは、自然資本の損失を抑えるだけでなく、生物多様性を回復し、自然との共生的関係を構築することを意味します。これは特に原材料調達や土地利用を伴う業種において重要性が高く、原産地での森林破壊回避、持続可能な農業・林業、また水資源管理などにおける企業の介入が問われます。ネイチャーポジティブなアプローチは、単なるCSR的な活動ではなく、調達先や土地管理の選定基準、製品開発時の自然影響評価など、バリューチェーン戦略と一体で設計される必要があります。
このように、グリーン製品・ネイチャーポジティブ・責任ある調達ガイドラインのいずれもが、バリューチェーンを貫く戦略の中でこそ、その意義と実効性を発揮します。このようなバリューチェーンマネジメントを促進することで、企業はサステナビリティ情報開示など単なる規制順守を超えた、真のサステナビリティ競争力を確立できるのです。
戦略的視点からみたバリューチェーンマネジメントは、単なるオペレーショナルな最適化ではなく、企業が中長期的にどのような価値を、どのように、誰と共につくるかを設計する行為そのものです。これは単に「環境配慮しているか」「リスクに備えているか」ではなく、未来に向けて自社の存在意義(パーパス)をどのように実装していくのかという問いにも直結します。
本稿が、企業におけるサステナビリティ経営の深化と実践に向けた一助となれば幸いです。





支援.png)
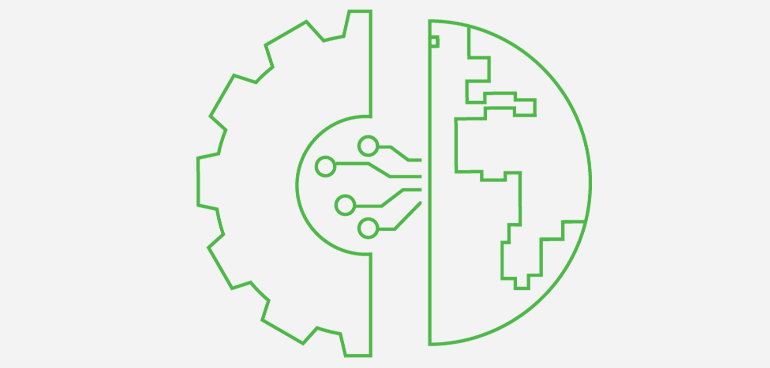


のポイント:投資判断と事業運営における重要要素-300x200.jpg)
