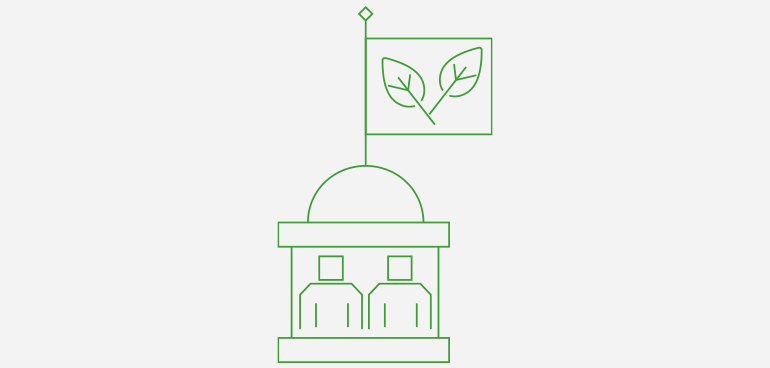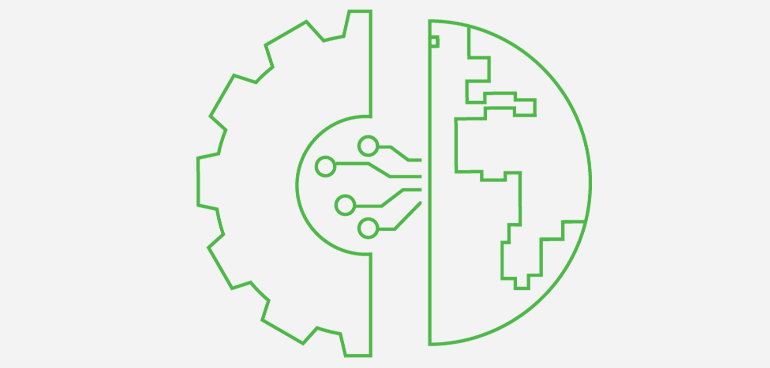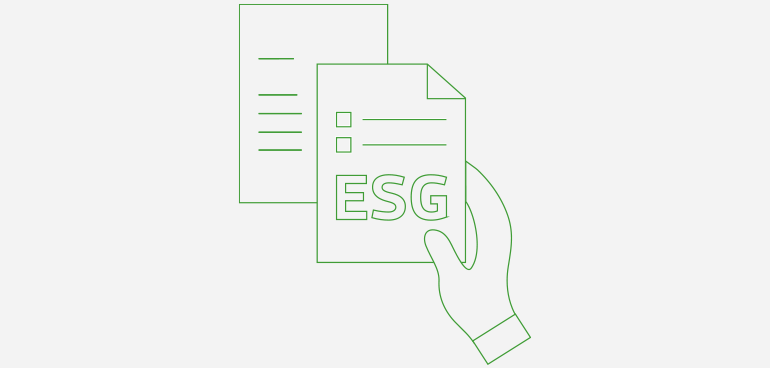TNFD提言の理解と実践:その5・指標とツール
2025年7月1日
本コラムTNFDシリーズでは、その1~その4まで執筆してきましたが、全体的に見てとれるように、TCFDが気候領域に焦点を当てているのに対し、TNFDは気候領域のみならず自然圏全般を対象にし、また人間社会、特に様々なステークホルダーとの関係性も重視しているなど、膨大な領域を俯瞰的にカバーしています。そのためTNFDの実践には特に、複雑なシステムを統合的に捉える力が要求され、TNFDを実践していく上では、できる限りそうした複雑性を克服していくための「指標とツール」は欠かせません。そこで本コラムでは、TNFDを実践していく上でどのような指標やツールが主に存在するのか、という観点から解説したいと思います。
指標
TNFDにおいて「指標」には、「開示指標」と「測定指標」があります。実務面でみると、測定 → 特定 → 開示という流れがあり、下記のような仕分けを描いて、指標を捉える必要があります。
- 測定段階:物理リスクや移行リスクを科学的に定量化し、経営判断の材料にする。
- 開示段階:そこから重要な情報を抽出して、投資家などに比較可能な形で報告する。
まず下記では、便宜上、TNFD開示指標を概説したあと(詳細については、TNFD報告書の別紙1および別紙2を参照ください)、本コラムでは、実践的側面から、測定指標に重点を置いて、関連のツールへの理解を深めていきます。
(1)開示指標
TNFD が提言する開示指標は、企業の業種や事業の地理的特性に応じて指標を使い分けられるように、以下の2種類を設けています。
① 中核開示指標
- すべての企業・金融機関に推奨される基本指標
- 比較可能性を担保
- 例:
- GHG排出量(Scope 1, 2, 3)
- 土地使用の変化(ha単位)
- 自社施設の近隣にある重要生態系の数
- 自然関連の財務的影響額(定量評価)
② 補完的指標
- 業種や状況に応じて追加使用
- 例:農業、林業、水産業、鉱業などに特化した指標
- 化学肥料の使用量(kg/ha)
- 捕獲魚種数、漁獲量の推移
- 植林面積と生物多様性回復率
(2)「測定指標」
TNFD報告書によると、企業報告のための既存の自然関連の指標と測定指標に関する最初の調査では、「①すでに3,000 以上の独自の測定指標が使用されていること、②類似の指標に対して異なる定義が使われていること、③対象とする自然関連課題に一貫性がなく、対象範囲も不均一であること、④マイナスのインパクト要因に焦点が当てられていること、⑤データのギャップや投資家にとっての意思決定の有用性について懸念があること」が報告されています。このような測定指標の現状にあっても、社内の現状を把握し、社内分析し、経営判断する上では欠かせないのが、測定指標です。測定指標のための主なツール(下記2.参照)、それらを補完する代表的ツール(下記3.参照)中心に、幾つかその特徴を見ていくことにします。
測定指標のための主なツール
TNFDの文脈でよく活用される知識データベースとしての2つのツール「ENCORE」と「IBAT」の概要、特徴を先ず見ておきましょう。
(1)ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure)
https://www.encorenature.org/en
【概要】「産業セクター×自然資本要素」の関係性を定性的・構造的に把握するためのツール
(提供主体)UNEP FI, Global Canopy, Natural Capital Finance Alliance(NCFA)等
(対象)銀行・保険・投資機関など金融機関向けに設計
(機能)セクター、サブ産業で絞り込み、生産プロセスごとに自然にどの程度依存しインパクトを与えているかを3つの切り口から確認できる。さらに、セクター、サブ産業、生産プロセスごとに自然に影響を及ぼす要因を把握できる。また、マテリアリティ(重要度)について、Very high, High, Medium, Low, Very lowの5段階で表示。
(形式)オンラインWebツール(地図+マトリクス)
- 主な使い方(TNFD文脈)
- LEAPアプローチの「Locate(自然への依存・影響の特定)」で使用:例えば業種(例:コーヒー製造業)を選ぶと、水や気候などの自然資本要素への依存度を可視化
- LEAPアプローチの「Evaluate」で使用:事業ごとの物理的リスク(生態系劣化、水ストレスなど)への脆弱性評価が可能
(2)IBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)
https://www.ibat-alliance.org/
【概要】IBATは、特定地域・プロジェクトが生物多様性に与える影響や、保全地域との重複状況を評価するための地理情報ツールです。
(提供主体)国連環境計画・世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC), 国際自然保護連合(IUCN), BirdLife International, Conservation International など
(対象)グローバル企業・金融機関・環境アセスメント実施者
(機能)対象地点から直径50km範囲内のIUCNレッドリスト、保護区、生物多様性の保全上重要な地域の概要を一覧で確認可能。対象地点周辺の種に対する潜在的リスクの確認が可能
(形式)有料プラットフォーム(一部無料利用可能):有料プランでは、GISデータのダウンロードやレポート形式での情報入手がプロジェクトの場所が、重要生物多様性地域(KBA)などに該当するかを評価
主な使い方(TNFD文脈)
LEAPの「Locate」「Evaluate」の両方で活用:サプライチェーンの事業拠点や採掘地点などを登録 → 周囲の保護地域、絶滅危惧種分布等との重なりを評価
補完または応用ツール
(1)「IPR FPS + Nature」
https://www.unpri.org/inevitable-policy-response/ipr-forecast-policy-scenario–nature/10966.article
概要:IPR(Initiative for Responsible Investment)が発行する「IPR FPS + Nature」とは、これまでの気候中心のシナリオに自然関連リスク(例:生物多様性喪失や土地劣化)を加えていることを特徴とし、投資家向けとして初の自然と気候を統合したシナリオツールとなっています。リスク評価における重要なギャップを埋めるものです。また金融業界にとって、自然と気候の両方の要素がもたらす影響を評価するための初の統合的なツールとしても位置付けられます。
たとえば、提供されている文書として次のようなものがあります。
(シナリオ)
「IPR 2023 Forecast Policy Scenario」 (FPS)
(ポリシー予測)
- 「IPR FPS 2023 Summary Report」 「IPR 2023 Policy Forecast」 「IPR FPS 2023 Detailed Energy Results」「 IPR FPS 2023 Detailed Land Use and Nature Results」「IPR 2023 Bioenergy Report」
(オープンアクセスデータベース)
- 「IPR FPS 2023 Value Drivers」
- 「IPR Scenario Explorer」
具体例:「IPR FPS + Nature」のツールを使った具体例として、金融機関や投資家が自然および気候に関連するリスク・機会を可視化し、投資戦略やポートフォリオリスク(投資家が保有する資産全体に対して影響を及ぼす可能性のあるリスク)の見直しに活用する、といった使い方がなされている事例が見られます。
例:ポートフォリオ全体のネイチャーリスク評価
ある金融機関がFPS + Natureを使って以下を行う:
- 自社ポートフォリオ中、自然関連リスクの高い業種(例:農業、林業、鉱業)を特定。
- 2030年〜2050年の間で自然関連政策の導入と技術革新による収益影響を予測。
- 必要に応じて投資先のエンゲージメント強化や資産の再配分を実施。
(2)WBCSDの 「Climate Scenario Catalogue」ツール:
https://climatescenariocatalogue.org/
概要:WBCSD(World Business Council for Sustainable Development」/「持続可能な開発のための世界経済人会議」)が発行するこのツールは、食・農業・森林セクターに特化した初の定量的シナリオ分析ツールとして位置づけられています。下記に示すように23の商品および18の地域にわたる事業、土地利用および環境要因に関するデータが提供されており、豊富な対象変数が特徴的です(下記リスト参照)。このツールはTCFD準拠で開発されましたが、現在はTNFDへの活用も広がっています。
地域
世界18地域(例:日本・韓国、ブラジル、欧州、USAなど) 。
商品
23種の作物・畜産・林産品(例:大豆、牛肉、パルス、木材など) archive.wbcsd.org+3wbcsd.org+3wbcsd.org+3。
アウトプット
生産量、市場規模、価格、収量成長、温室効果ガス排出等を2040–50年まで予測 wbcsd.org+1climatescenariocatalogue.org+1。
また実務的観点から特徴を挙げると次の点が挙げられます。
- オンライン上で地域・商品・変数を選ぶと、各シナリオの将来推移がグラフと数値で表示・比較でき、CSV形式でダウンロード可能 wbcsd.org+6climatescenariocatalogue.org+6sustainablejapan.jp+6。
- シナリオ分析の手法、業務応用(戦略、公開・コミュニケーション)などを解説 climatescenariocatalogue.org+11wbcsd.org+11wbcsd.org+11。
- MAgPIEモデルなど分析手法と限界、ドライバーや変数設計を詳細に説明 wbcsd.org。
具体例:TNFDでは以下のような実践例や適用可能性を見てとることができます。
LEAPアプローチの“Locate”・“Evaluate”フェーズに活用
TNFDは「LEAP(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)」という分析プロセスを採用していますが(詳細は、本TNFDシリーズ・その1参照)、このツールは下記のようにして活用されます。
| LEAP段階 | 活用方法 | ツールの活用内容 |
|---|---|---|
| Locate(依存・影響の特定) | 地域×作物ごとに将来変化を確認し、自然への依存度が高い事業領域を特定 | 「大豆の収量が30%減少」→ 自社事業は自然依存度が高いと特定 |
| Evaluate(リスク機会の評価) | 生産量や価格の変化からビジネスリスクを定量的に試算 | 炭素価格増加・収益への影響を価格シナリオから試算可能 |
土地利用や農業由来排出リスク評価に利用
- ある関連企業は本ツールを使って土地利用や農業由来排出リスク評価を開始。定量アウトプットをTNFDで開示。
地図ベースの自然関連インパクト評価の補完ツールとして
- TNFDでは前述のようにENCOREやIBATなどの地図ベース自然リスクツールが主流ですが、Scenario Catalogue はその将来シナリオ版の定量評価ツールとして補完的に使えます。
- 例:ENCOREで森林依存を特定 → Scenario Catalogueで2050年の森林セクター価格/排出量影響を試算 → TNFD開示文脈に具体的データを追加
その他適用可能性
- 内部理解と教育:ツールを活用しシナリオ分析の基礎を経営・事業部門に展開し “What if?(もしこうだったら?)” 分析で将来像を共有 。
- 定量分析との連携:地域・商品別の生産量や価格、価格上昇・排出量の変化などの数値を可視化し、具体的な影響を把握 。
- 戦略・開示への統合 :各種シナリオを使った戦略シナリオ設計により、移行リスクや投資戦略を強化。これまでにもTCFD、ISSB、SEC 対応にも寄与。
- サプライチェーン全体の巻き込み:一次サプライヤーに対し、排出削減や自然リスク対応を促すエンゲージメント手段に。
代表的なステークホルダー評価ツール
上記2~3で焦点を当てた自然圏の側面を重視したツールだけでなく、より人間社会、特にステークホルダーとの連携を深めていく上での、ステークホルダーの側面を評価するツールも、冒頭で述べたようなTNFDの性質上も重要になると考えられます。その側面から代表的なツールをここに紹介します。
(1) ENCORE(上記2.(1)と同様)
- 産業活動と自然資本の関係性(依存・影響)を明示する中で
- 特定の産業が自然資本に依存する度合いを見、人間活動の影響を可視化
- バリューチェーン上のステークホルダーのリスクも可視化
(2)ARIES for SEEA (Artificial Intelligence for Environment & Sustainability for System of Environmental Economic Accounting)による自然資本会計向けの地理空間ツール
https://seea.un.org/content/about-seea
- 空間データを活用して、特定地域に住む人々が享受している生態系サービスを定量化
- ステークホルダーがどの生態系にどれだけ依存しているかを評価
- 例:森林に依存する先住民、漁場に依存する沿岸コミュニティ
(3)SBTN(Science Based Targets Network)によるステークホルダー関与ガイダンス (”Stakeholder Engagement Guidance”)
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
- 自然と人間の相互関係におけるステークホルダーを分類・評価するフレームワークを提供
- 以下のような視点が含まれます:
- 誰が自然資源に依存しているか?
- 自社の事業がどの人々に影響を与えているか?
- その関係性は公正か、逆に脆弱な人々にしわ寄せが行っていないか?
ここで特集した指標とツールをTNFDの実践において参考にし社内で学習を深めていただければ幸いです。