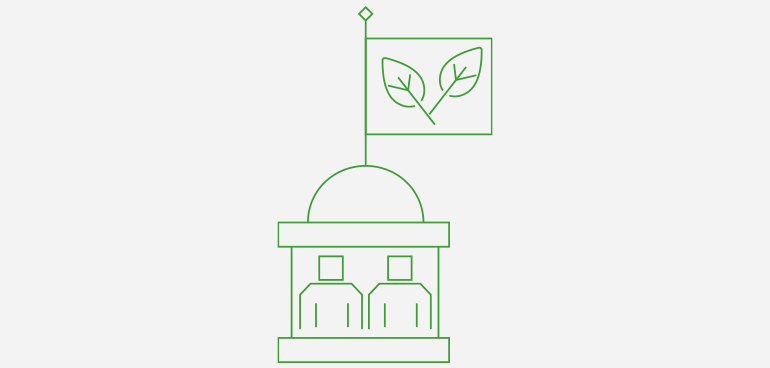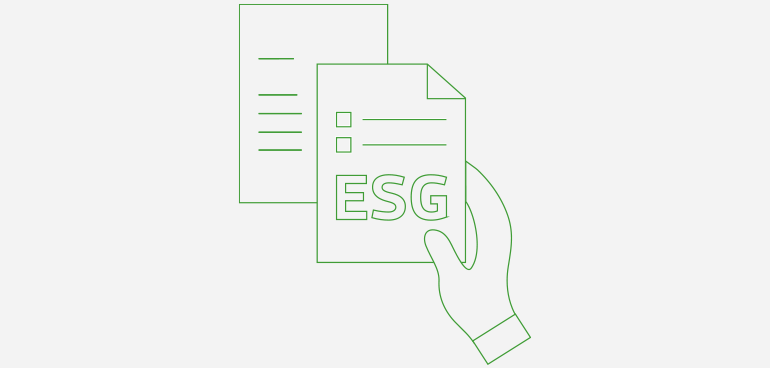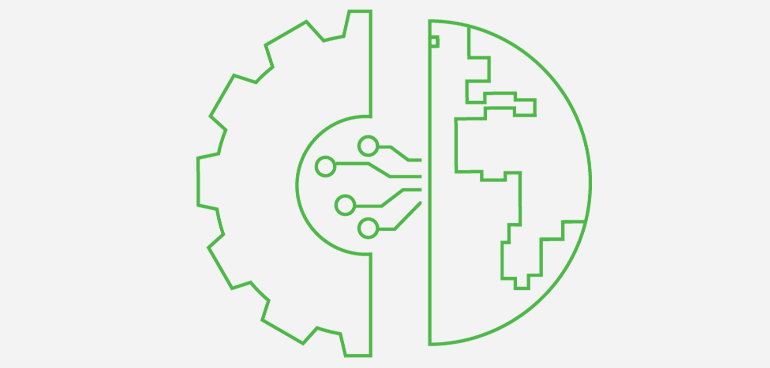EU CSRDへの対応について:日本企業の文脈で読み解く
2025年7月11日
はじめに:CSRDの特徴
近年、企業の持続可能性に対する社会的要請が高まる中、欧州連合(EU)はその対応を制度として具体化する動きを加速させています。その象徴とも言えるのが、2023年に発効した「企業持続可能性報告指令(CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive)」です。これは、従来の非財務情報開示指令(NFRD)を大きく刷新し、企業に対しサステナビリティに関する情報をより網羅的・詳細に、かつ信頼性ある形で開示することを求めるものです。
一言でいいますとCSRDは、金融・環境・社会・ガバナンスを含むサステナビリティ情報を統一的に構造化された形式で開示する法的枠組みです。重要なのは、CSRDには単に「開示せよ」という文言だけでなく、「どの形式・どの信頼性で開示すべきか」まで明示されている点です。
開示内容は「European Sustainability Reporting Standards(ESRS)(欧州サステナビリティ報告基準)に則ることが義務付けられており、また提出形式や保証水準についても規定されています。こうした点は、TCFDやTNFDと大きく異なる特徴として、理解しておく必要があるでしょう。
CSRDの背景には、EUが掲げる「グリーンディール」や「サステナブル・ファイナンス戦略」といった政策目標があります。気候変動や人権、資源循環などの課題に対応するためには、これからの時代は、「環境や社会への影響が少ない企業」に投資が集まり、そうでない企業にはお金が流れにくくなるような仕組みが必要です。そのために、非財務的な影響を見える化しよう、というのが制度設計の背景です。
簡素化の動き
一方、2025年初頭以降、制度の合理化に向けた動きが現在進みつつあります。ポイントのみここで示します。
- 欧州委員会(EU)は2025年2月に「Omnibus簡素化パッケージ」を発表し、CSRDのみならず、タクソノミー規則(グリーンな経済活動の分類規準のこと。EUが定めたグリーン定義を踏まえ、自社の経済活動のグリーン割合を、売上、設備投資、収益的支出について開示が求められる)、企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)を含む報告義務を一体化して、企業全体で25%、中小企業で35%の報告負担削減を目指す方針を明らかに。これに基づき、企業の対象基準や報告項目、報告開始時期などが見直されつつある。
- スケジュールについては、これまでに開始していない企業について基本的に開始は、2年間延期の予定(詳細は2.1を参照)。
- 対象企業も、2025年に提案された見直し案では、EU域内企業につき「従業員1,000人以上かつ売上5,000万ユーロ、または資産2,500万ユーロ以上」とする方向で調整中(詳細は2.2を参照)。
- また、2025年6月20日付でEFRAG(欧州財務報告諮問グループ)は、CSRDが依拠するESRSの簡素化に関する進捗状況を報告。これによると、主要改革措置によって報告負担を50%以上削減することを目指すと報告(詳細は2.5を参照)。
こうした簡素化に伴う変更は念頭にいれつつ、その簡素化の実施によって対象から外れ得る企業にとっても、「対応不要」とは限らず、今後CSRD的な開示への期待は高まると見ておく必要があるでしょう。また欧州の金融機関や投資家は、今後もESRSを参照する可能性が高く、「直接義務はないが、開示要請は来るかもしれない」という影響の波及についても、念頭に置入れておく必要があると考えられます。
以下では、CSRDのスケジュールや概要とともに、その要点や背景、さらに日本企業が置かれている文脈からの影響と対応の方向性について、最新動向もふまえて読み解いてまいります。
CSRDのスケジュールと概要
2.1 スケジュール
CSRDの適用対象となる企業は、段階的に拡大していく予定でしたが、2025年7月現在、見直しが進められており、制度自体が柔軟に調整されつつあります。現時点の見込みを反映して、そのスケジュール概要を下記のように示します。
| 適用年度 | 対象企業区分 | 適用基準(改定案) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | NFRD対象企業(EU上場大企業) | 従業員500人以上など(旧NFRD基準) | CSRDが最初に適用されたグループ |
| 2025年度 | ― | ― | 適用対象の拡大予定だったが、見直しにより延期 |
| 2026年度 | ― | ― | Wave 2(EU大企業)開始予定だったが、2028年度に延期 |
| 2027年度 | ― | ― | Wave 3(上場SME)開始予定だったが、2029年度に延期 |
| 2028年度 | EU域内の新定義に該当する大企業 | 従業員1,000人以上かつ売上5,000万ユーロ以上または資産2,500万ユーロ以上 | 旧Wave 2とWave 3の一部がここに統合される形 |
| 2028年度 | 非EU企業(日本企業等)でEU域内売上が1.5億ユーロ超 | ※追加要件:EU域内に子会社または支店あり | 見直し案ではこの対象も絞り込み検討中 |
| 2029年度 | EU域内の上場中小企業(SME) | SME向け基準(LSME/ESRS)適用予定 | 強制ではなく、段階的・選択的適用の議論も |
こうした動きは、制度の過度な複雑さや負担の重さに対する産業界からの声に応えたものと言えるでしょう。同時に、報告内容の核となる欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)も簡素化が議論されています(2.5参照)。また中小企業へのトリクルダウン負担(中大企業がCSRD/ESRS対応でサプライチェーン全体に開示要請をかけた結果、間接的に中小企業に過度な情報収集負担が降りかかる現象)を軽減する改訂案が、2025年中に公表される予定です。
2.2 CSRD制度簡素化の動き
上記1.で触れたようにCSRDを含むEUのサステナビリティ報告制度は、開始からわずか1〜2年で大きな修正の動きを見せています。その中心にあるのが2025年2月に公表された「Omnibus簡素化パッケージ」です。
この簡素化の背景には、以下のような要因があります。
- 急激な対応コストの高騰:中堅企業では、報告対応に数千万円規模の費用がかかるケースも見られ、社内体制や外部委託先の不足が課題に。
- 開示項目の膨大さ:ESRSでは12分野300項目超の開示が必要とされており、企業実務が追いつかないという声が多数上がっている。
- 欧州経済の減速と規制疲れへの配慮:インフレや地政学リスクの影響で、企業活動全般の回復が進まない中、規制強化が負担となることへの懸念が高まっている。
こうした背景から、欧州委員会は以下の見直しを打ち出しました。
- 適用対象の絞り込み(従業員数や売上・資産基準を引き上げ)
- 中小企業向けの簡易基準(SME ESRS)の策定推進
- 保証要件についても「限定的保証」から「合理的保証」への移行は段階的に検討
この動きは、CSRDが制度疲労に陥る前に、現実的な調整を加える「制度持続性の確保」でもあります。日本企業にとっても、過度な負担を回避しつつも、準備の段階に入っていくプロセスと捉えることもできます。
とはいえ、ESRSの基本構造は維持されており、企業に求められる情報開示は依然として広範です。CSRDに基づく開示義務は、従来の財務情報にとどまらず、サステナビリティに関する非財務情報を定量・定性の両面から明確に記述することが求められます。
次に、その開示義務に関連して、CSRD開示項目の中核と、保証規定と開示方法について、解説します。
2.3 CSRDの概要1:開示項目の中核
開示項目として中核を成すのが、次の5つの主要領域です。
- 気候変動、生物多様性、資源循環
- 人的資本と社会関係資本
- ガバナンスと内部統制
- ビジネスモデルと戦略、リスク管理との整合性
- 財務的影響評価と非財務指標の統合
これらの領域において、企業は「ダブルマテリアリティ」(①企業が環境・人に与える影響と、②サステナビリティ課題が企業に与える影響の両面を重視)の視点に基づき、財務への影響(リスク・機会)と、社会・環境へのインパクトの両面から報告を行います。ダブルマテリアリティはTNFDなど他のフレームワークにも通底する考え方ですが、CSRDでは法的義務として明文化されている点が特徴的です。
たとえば、気候変動分野では、温室効果ガス排出量(Scope1~3)やネットゼロ戦略、自然災害による物理的リスクの想定などに加え、脱炭素社会への移行に伴う事業転換可能性などが問われます。生物多様性では、TNFDとの整合を図りつつ、影響を受ける自然資本の特定、生態系への依存度、生物多様性保全への投資等が示される必要があります。
資源循環では、再生可能資源の使用割合や廃棄物削減努力、水使用の効率化など、循環型経済に貢献する取り組みの開示が求められます。
人的資本については、従業員の多様性、賃金の平等性、従業員満足度、スキル開発制度、職場の安全衛生など、人的資本マネジメントそのものが問われます。また、社会関係資本として、地域社会との関係、顧客対応、サプライチェーンでの人権尊重などの姿勢も評価対象になります。
さらに、ガバナンス面では、取締役会の構成や専門性、持続可能性に関する監督体制、報酬制度とESG目標との整合、倫理規範の徹底状況など、組織の透明性と説明責任の強化が強調されます。
2.4 CSRDの概要2:保証規定と提出形式
CSRDの特徴的な点として、上記に関わる開示項目に関わる情報は、単なる自主的な記述ではなく、信頼性の確保が制度として義務付けられており、報告書には第三者による「限定的保証(limited assurance)」の取得が必要です。これは、企業が記載した情報について、外部の保証者が「重大な虚偽が存在しないと合理的に信じられる」という水準で保証するものです。
なお、CSRD第34条および付属文書には、将来的に合理的保証(reasonable assurance)、つまり、より高い精度と網羅性を要求される保証水準への移行を検討する旨が明記されており、保証のためのインフラ整備や基準策定が進められていることにも、留意が必要です。
また、CSRDでは、サステナビリティ報告書の提出形式にもデジタル対応が求められており、XHTML形式での作成と、ESEF(欧州単一電子フォーマット)に基づくXBRLタグ付けが必須となります。これにより、報告書は機械可読性を備え、投資家や当局が自動的に比較・分析できるデータ基盤の一部として活用されます。
2.5 ESRSの改訂の進捗
ESRSの改訂の議論は今(2025年7月現在)まさに進んでいるところです。直近では、2025年6月20日に EFRAG(欧州財務報告アドバイザリーグループ)が欧州委員会へ、「ESRS改訂の進捗報告書」を提出しました。
EFRAGはその報告書の中で、2025年10月末までに委員会へ改訂案を提出予定であること、また、必須データポイントを50%以上削減する計画であると明記しています。目立つ変更点には以下が含まれます。
- ダブルマテリアリティ評価の簡素化:ビジネスモデルのトップダウン評価をベースに据え、過剰な詳細評価を省略可能に。
- 開示文書の構造化:冗長なナラティブ(文説明)を整理し、要点に集約した概要や別添による補完手法を導入。
- 必須/任意の明確化:必須開示か参考的ガイダンスかを明示し、基準の理解・適用が容易になるよう改善。
- 実務負担軽減措置:推定値の使用可・サプライチェーン情報の負担緩和・機密情報の取り扱い緩和などを選択肢に。
- 国際基準との互換性強化:ISSB基準との整合性を高め、グローバル・クオリティを保証。
日本企業への影響と対応方針
CSRDおよびESRS基準の大幅な見直しの動きはありますが、日本企業であっても、EU域内に子会社や営業拠点を持つ企業、あるいはEUの資本市場で取引されている企業は特に、将来的にCSRDの対象企業として直接的な開示義務を負う可能性があります。さらに、サプライチェーンの一部としてEU企業と取引をしている場合、間接的な情報提供の要請を受けることも増えてくるでしょう。
上記1.で示唆したように、CSRDが特徴的なのは、従来の「自主的・任意的な開示」ではなく、「構造化された義務的開示」が求められる点です。その上で、開示内容に信頼性を持たせるために、保証付きでの報告、かつデジタル形式での提出が求められるため、情報の収集・分析・文書化・保証対応まで、一貫した体制整備が必要となります。
こうした対応のため、すでに一部の先進企業では、TCFD、TNFD、ISSBなどの各種フレームワークと整合をとりながら、社内体制の見直しや情報基盤の整備が進められています。特にISSBは、財務に関連するサステナビリティ情報の国際的統一を目的とするもので、CSRDと補完関係にあります。ISSBに対応済みであれば、CSRD対応にも一定の下地があるといえます。
とはいえ、CSRD独自の特性として、「ダブルマテリアリティ」の法的義務化や保証付きの報告、XHTML形式での提出といった点は、他の枠組みにはないハードルです。この意味で、ISSB・TCFD・TNFD等に準拠した報告書を既に作成している企業であっても、CSRDは「もう一段深い開示と対応」が求められる制度であることを理解しておく必要があります。
総じて、CSRDは日本企業にとって対応負担の大きい制度であると同時に、自社の持続可能性戦略を世界基準で再定義する機会でもあります。すべてを一度に整備することは難しくとも、まずはギャップ分析やマテリアリティ評価など、段階的な対応を進めることが現実的かつ戦略的な第一歩となるでしょう。
まとめ
近年日本国内ではCSRDへの注目度が高まり、多くの企業がESRSに基づいた情報整理や、内部統制体制の整備に取り組み始めてきましたが、CSRD/ESRSの大幅な見直しを踏まえると、今後は「自社は報告対象外になった」とする企業や、「ISSBやTCFDの対応で十分」とする見方が広がることにより、CSRDへの関心が一部で落ち着く可能性もあります。
とはいえ、サステナビリティ情報開示の要請は今後も強まると予想され、CSRDはその一環として位置づけられ続けるでしょう。特に、投資家や金融機関からの開示要請、顧客企業からのサプライチェーン調達基準への対応などを考慮すると、「報告義務がない=対応不要」とは言えないと思います。むしろ、CSRDに代表される高度な情報開示フレームワークへの理解と、他制度(ISSB、TNFD等)との整合性を踏まえた対応が、中長期的な競争優位性を左右するといえるでしょう。
つまり、日本企業にとってのCSRD対応は、単なる規制遵守の枠を超え、サステナビリティ経営の本質に迫るものとして捉えることが重要です。直接の法的義務が緩和される局面であっても、対応の手を緩めるのではなく、自社の影響力や市場との関係を踏まえた「賢い備え」が、今後ますます問われることになると考えられます。
こうした解説が、CSRDを含むサステナビリティ基準への戦略的な企業対応に資すれば幸いです。