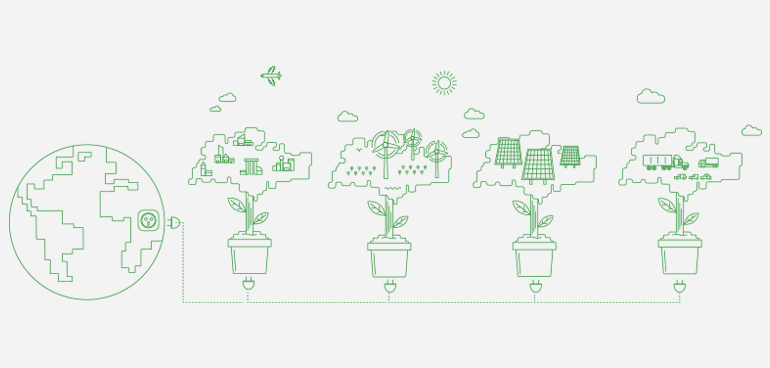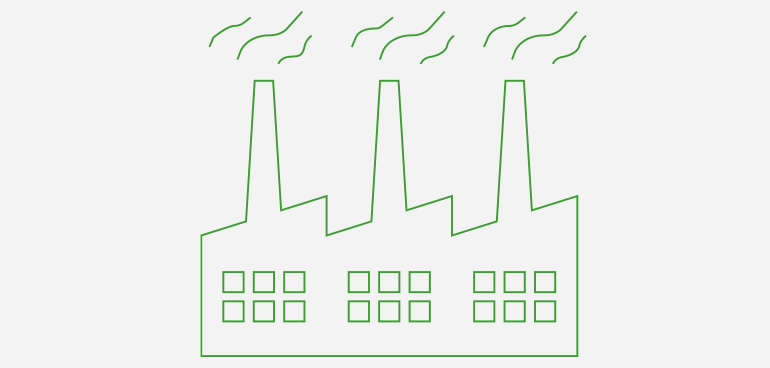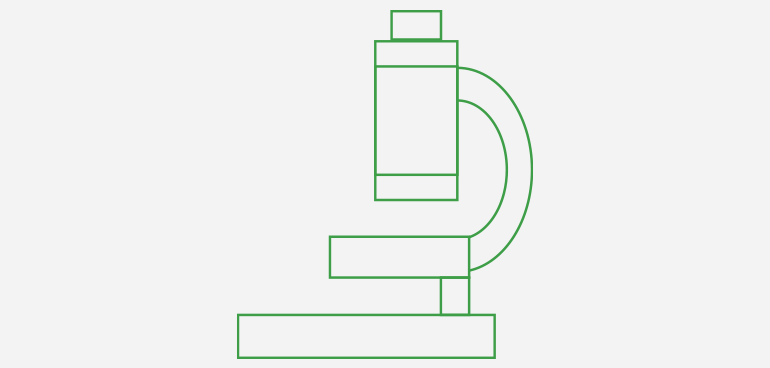日本の不動産業界におけるESGの課題と実務的対応策
2025年11月24日
日本の不動産業界のESGへの取り組みの現況
不動産は世界のエネルギー消費やCO₂排出において大きな割合を占めており、ESG対応は事業継続と競争力に直結する重要なテーマとなっています。近年では、ESG対応を進めた不動産が、資金調達コストの低減や社会的信頼の向上、賃料水準の維持・向上、空室率の低下といったプラスの効果をもたらすことが認識されており、機関投資家もGRESBをはじめとする各種認証の取得状況を重視する傾向が強まっています。
一方で、横断的な課題として、ESG投資が長期的な価値創出を志向する一方で短期的な収益とのトレードオフが経営判断を難しくしていること、また災害対応やBCP設計に関する評価指標が統一されておらず、保険料や投資判断に十分反映されにくいことなどが挙げられます。
本稿では、こうした全体状況を踏まえつつ、日本の不動産業界が直面している現状とさらなる課題をESGの観点から整理し、今後期待される対策について検討します。
環境(E)の現況と課題
環境面では、再生可能エネルギーの導入や高断熱・高気密化によるエネルギー効率の向上、木材利用の促進や循環型建材の活用などを通じて、脱炭素と資源循環型の建築・運営が進められています。
しかし、代表的な課題として初期投資コストの高さが挙げられます。特に老朽ストックや中小規模の物件では、投資回収期間の見通しが立てにくく、賃料への転嫁にも限界があることから、必要性を認識しながらも実行段階に踏み切れないケースが少なくありません。
もう一つの大きな論点が、GHGスコープ3の把握です。テナントが個別に契約している電力や、専有部でのエネルギー使用まで含めて定量化することは容易ではありません。データ提供に対するテナント側の負担感や業種ごとの意識差も重なり、算定範囲や精度にはばらつきが生じやすいのが実情です。さらに、建材や施工といった上流の排出まで対象を広げると、どこまで詳細に追跡すべきか判断に迷う場面が増えています。
社会(S)の現況と課題
社会面では、地域再生に資する複合施設開発や、働き方改革に対応した柔軟なオフィス設計、災害対応力の高いレジリエントな建物づくりが求められています。
一方で、日本の不動産業界は、こうした良質な取り組みが十分に伝わっていないという課題を抱えています。環境配慮やウェルビーイングを意識した設計(自然光や緑地、コミュニティスペース、防災機能など)を取り入れても、多くの居住者やテナントは依然として、賃料や駅からの距離、専有面積といった分かりやすい条件を重視して物件を選ぶのが実情です。その結果、ESGや健康・快適性に配慮した設計の価値が十分に評価されず、オーナー側は追加コストの妥当性や投資回収の筋道を示しにくくなります。
また、地域との共生という観点からも、設計段階から社会的価値を織り込むことは容易ではありません。医療・福祉機能の誘致、子育て支援、雇用創出、災害時の受け入れ拠点といった役割を、一つのエリアやビルの中でどのように配置するかを検討するには、行政、医療・福祉事業者、企業、住民など多様なステークホルダーとの調整が欠かせません。投資家にとっては短期的な利回りとのバランスも課題となり、地域にもたらされる長期的な便益が、経済性の評価にどのように反映されるのかが見えにくい場面もあります。
ガバナンス(G)現況と課題
ガバナンス面では、ESGレポートやGRESBへの対応を含む情報開示の充実、SPC(特別目的会社)を活用したリスク分散と管理強化、そしてガバナンス体制の整備を通じて、投資家やステークホルダーに対する説明責任と信頼性の向上が図られています。
一方で、情報開示や評価の基準が過度に多様化していることが大きな課題となっています。複数の指標や認証が併存するなかで、どれを優先的に採用し、どの水準を目標とすべきかについて社内合意を形成することは容易ではありません。上場会社や機関投資家を強く意識する企業ほど、多様な指標への対応を迫られやすく、その結果、評価対応そのものが目的化し、投資家やテナント、地域にとって何が本当に有益な情報なのかが見えにくくなるおそれもあります。
あわせて、ESGデータの収集・管理にかかる負荷の高さも看過できません。建物単位だけでなく、街区やエリア単位でGHG排出量やエネルギー利用状況、賃貸契約や運営スキームの状況などを継続的に把握しようとすれば、現場・本社の双方で相応の人的リソースとシステム投資が必要となります。
ESG課題への対応策、そして未来への展望
不動産業界では、これまで提示してきた取り組みと課題の積み重ねの上に、いま着実な変革が起きつつあります。建物が都市や社会、環境へ与えるインパクトの大きさを踏まえれば、各企業の持続的なESG推進努力が、地域やサプライチェーン全体のサステナビリティの実現に直結することは明白です。
実際、金融スキームや各種補助制度による初期投資負担の軽減、グリーンリースや省エネ契約条項、自治体・国策との連携、ESG情報の「見える化」といった現場主導の前向きな取り組みが、徐々にですが全国的に広がっています。
たとえば環境面では、ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)やZEB(ネットゼロエネルギービル)基準を満たすため、断熱性強化や高効率設備の導入など、多層的な技術革新が進んでいます(1)。これに対してはリフォームにも活用できる補助金制度の拡充もあり、事業者・消費者ともに導入のハードルが次第に下がってきました。
社会面においては、建物の環境性能や健康・防災機能、地域コミュニティへのメリットをデータや具体事例で可視化・訴求する流れが強まっています(2)。これにより、テナントや入居者は「目に見える」価値で物件を評価しやすくなり、投資家にとっても高性能物件への資金流入が起こっています。特に日本では、安定した資産運用や価値保全を重視する投資家が多いため、ESG指標をもとにしたデータ比較・選別が進むと考えられます。また、こうしたデータ開示は、マーケット全体の透明性向上と、長期志向の投資行動の促進にも寄与します。
ガバナンス面でも、GRESB・CASBEE・LEEDなどグローバルな評価指標と自社戦略との整合性をはかり、政府の脱炭素方針やGXリーグの要件とも連動したデータガバナンス体制を確立しつつあります。開示情報の標準化やデータ収集・管理プロセスの機能強化によって、単なる評価対応に終始せず、ESGデータをファイナンスや投資、開発、プロパティマネジメントの戦略判断に直結させる動きも活発化しています。
このように、不動産業界はESG実装を単なる社会的責任にとどめず、経済合理性や中長期的な事業価値創出と両立させる新たな段階に入っています。今後のビジョンとしては、ESGへの取組を「コスト」ではなく、成長や競争力の源泉と捉えて深化させていくことが重要です。政策・業界標準・テクノロジーを三位一体で活用しつつ、投資家・テナント・地域住民と共創する仕組みを拡げ、事業活動全体の価値向上と地域社会の持続的発展に寄与する姿勢が求められます。
様々な課題は依然として存在しますが、不動産業界が業界横断で学び合い・連携しつつ、現場での好事例や新しい知見を素早く取り入れることで、「サステナビリティを起点とした成長モデル」へと転換できる可能性は十分にあります。都市・地域インフラの担い手として、不動産業界が引き続きESG経営を進化させ、より良い未来社会の実現に貢献していくことが期待されます。
参考文献
(1)「ZEH」とは?リフォームで活用できる補助金の要件やメリットを解説|サポート行政書士法人 | サポート行政書士法人
(2)Residential rising: Unlocking sustainability and asset performance in a unique sector – GRESB