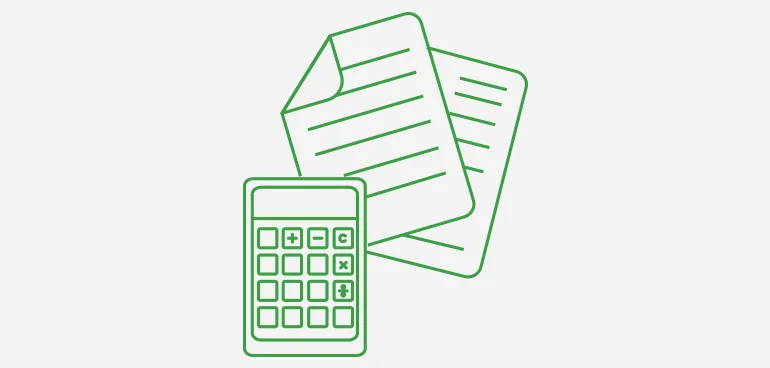今後の税制における論点 ~ギグエコノミーの広がりを踏まえて~
2025年5月21日
はじめに
令和7年度の税制改正大綱では、いわゆる「103万円の壁」に関する所得税の見直しが盛り込まれました。これにより、給与所得控除の上限額が引き上げられることとなりましたが、その一方で社会保険料の負担が増える可能性も指摘されています。結果として、必ずしも手取り収入が増えるとは限らない点に注意が必要です。
税制の見直しは、所得の再分配や課税の公平性を保つために、社会や経済の変化に応じて進められてきました。しかし近年、多様な働き方が急速に広がる中で、現在の税制がこうした現実に十分対応しきれていないとの指摘もあります。本稿では、こうした背景を踏まえ、「ギグエコノミー」と呼ばれる新たな就労形態と、それに伴う所得税制度上の課題について考察します。
現行の所得税制度における利点と課題
ここでは、ギグエコノミーと特に関係が深い「所得税制度」について取り上げます。詳しく見ていく前に、現在の日本の所得税制度が持つ主な特徴を、基礎知識として整理しておきましょう。
表 所得税の特徴
| 徴収方法 | 所得に対して課税される。会社員は天引きの形で徴収され、個人事業主の場合は売上先が源泉徴収する又は確定申告時に納付する。 |
|---|---|
| 長所 | 累進課税制度をとっているため、高所得者の税負担が重くなり公平性が高い。 |
| 短所 | 所得が上がるほど税負担が増えるため、労働意欲を減退させやすい。 |
このように、現行制度には利点と課題の両面が存在しており、社会の変化に応じて税制も柔軟に見直していくことが求められます。
ギグエコノミーと現行税制のギャップ
前の節でも述べたとおり、税制は労働構造の変化や経済状況に応じて見直されるべきですが、現実にはその対応が十分に追いついていない側面もあります。なかでも特に課題として指摘されているのが、ギグエコノミーに対する課税のあり方です。ギグエコノミーとは、インターネットなどを介して個人が単発・短期の仕事を受注する新しい就労形態およびその経済活動を指し、こうした働き方を選ぶ人々は「ギグワーカー」と呼ばれます。たとえば、Uber Eatsの配達業務や、クラウドソーシングサービスを通じて受注する仕事などがギグエコノミーに該当します。この働き方の大きな特徴は、企業に雇われるのではなく、自分の裁量で時間や場所を選びながら、スキルや知識を活かして業務に取り組める点にあります。フリーランスや副業の形で広がりを見せる一方で、現行の税制や社会保障制度とは整合しにくい部分があり、制度的なズレが課題として指摘されています。次の項では、その具体的な内容について見ていきましょう。
ギグエコノミーと税制における主な課題
ギグエコノミーに関連する所得税の取り扱いには、いくつかの制度的な問題が指摘されています。
① 所得の把握が難しいこと
ギグワーカーは複数のプラットフォームを通じて収入を得ることが一般的であり、その結果、所得が分散しやすくなっています。このような状況では、税務当局がそれぞれの収入を正確かつ網羅的に把握することが難しくなるとされています。特に、現金でのやり取りや、証拠が追跡しづらい海外経由の取引が含まれる場合には、その困難さは一層増します。
② 納税意識および遵守率の低さ
会社員であれば、所得税や住民税、社会保険料といった負担は給与から天引きされるため、納税を特別に意識せずとも処理が完了します。一方で、ギグワーカーの場合は、これらの税金や保険料を自ら計算・納付しなければならず、その分、納税漏れや遅延が生じやすい傾向にあります。これは前述の所得把握の難しさとも関係していますが、特に税務に関する知識が乏しい場合、確定申告の誤りなどによるリスクも高くなります。
③ 税負担の公平性と控除方式の違い
現在の税制では、会社員の給与所得には概算控除として、収入に応じた一定額の給与所得控除が自動的に適用され、個別に経費を申告することはできません。一方で、ギグワーカーなどの事業所得や雑所得については、必要経費の控除が認められており、業務に必要な支出を経費として具体的に申告することが可能です。このような控除方式の違いが、税負担の公平性という点で課題とされることがあります。また、正確には税ではないものの、実質的な手取りに大きく関わる社会保険料についても留意が必要です。会社員の場合、保険料は雇用主と労働者が折半で負担する仕組みですが、ギグワーカーはその全額を自身で負担する必要があります。こうした負担構造の違いも踏まえると、現行制度が税や社会保障の面で必ずしも公平とは言えないのではないか、という指摘がなされています。
おわりに
前述のような課題を解消するため、今後はより手軽に申告できる制度の整備が進められると見られています。その実現には、マイナポータルの活用が鍵を握ると考えられますが、インフラや運用体制の整備には時間を要するため、すぐに導入されるものではないかもしれません。それでも将来的には、給与所得者と事業所得者の間にある制度上の隔たりが縮まり、申告手続きの簡素化によって、申告漏れの防止にもつながることが期待されます。