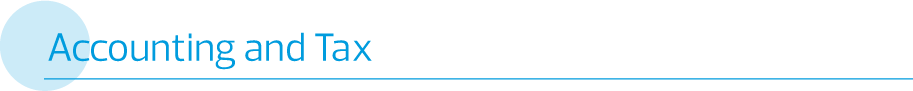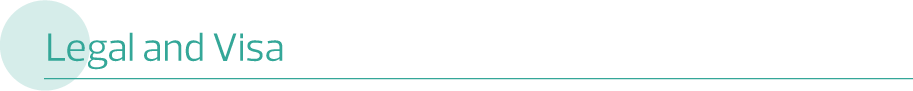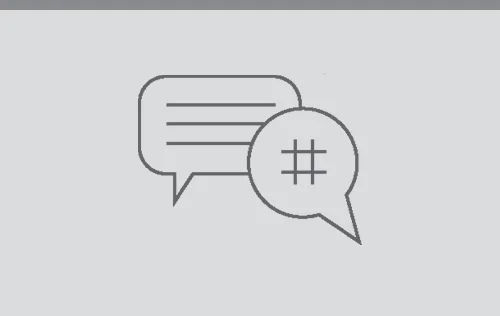RSM汐留パートナーズ・ニュースレター 2025年7月号
2025年7月7日
役員報酬設計のポイント・熱中症対策強化と企業の対応・永住資格取消しの概要
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。今月のニュースレターでは、税理士法人より「役員報酬設計のポイント」、社会保険労務士法人より「熱中症対策強化と企業の対応」、行政書士法人より「永住資格取消しの概要」をお届けします。
役員報酬設計では、事前確定届出給与の届出と株式報酬の取扱いにおける留意点、熱中症対策では2025年施行の義務化対応、永住資格取消しでは改正入管法の新ルールと実務上の注意点をそれぞれ解説しています。今月のニュースレターもぜひお役立てください。
はじめに
6月は多くの企業で株主総会が開催され、上場企業では報酬委員会制度や開示義務の影響から、役員報酬の設計に対する関心が高まっています。中でも「事前確定届出給与」は、法人税法上の損金算入を確保する上で重要な制度です。届出には期限があるため、株主総会後の7月に対応が求められる企業も少なくありません。今回は、株式報酬制度を含めた事前確定届出給与のポイントを整理します。
事前確定届出給与の概要と注意点
法人税法上、役員報酬は原則として損金不算入ですが、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当すれば損金算入が可能です。事前確定届出給与を適用するには、株主総会や取締役会で支給額・支給時期を決定し、①株主総会等の決議日から1ヶ月以内と②会計期間開始日から4ヶ月以内のいずれか早い日までに所轄税務署へ届出書を提出する必要があります。届出内容と異なる支給(支給額の変更、支給日のずれ、一部支給など)は、原則として損金不算入となるため、正確な管理が求められます。
株式報酬と事前確定給与
近年は金銭報酬に加え、株式報酬制度を導入する企業が増えています。以下では、各制度の概要と、事前確定届出給与としての損金算入可否について整理します。
RS(譲渡制限付株式)
RSは、譲渡制限付き株式を役員等に交付する制度です。付与時に株式数と支給日が確定し、業績条件がない場合には、時価×株数で合理的に価額が見積もれるため、事前確定届出給与としての届出が可能です。一方、業績未達時に株式が没収される設計では業績連動給与として扱われます。
RSU(譲渡制限付株式ユニット)
RSUは、一定期間経過後に無償で株式が交付される権利です。株式数が見積可能で、業績条件がなければ、事前確定届出給与の対象となりますが、業績により付与数が変動する「PSU(パフォーマンス・シェア・ユニット)」は業績連動給与として扱われます。
株式交付信託(J-ESOP等)
J-ESOPは、自社株式を信託に拠出し、一定条件を満たした役員等に株式を交付する制度です。在任中に付与数が確定し、業績条件がない設計であれば、事前確定届出給与の対象となりますが、退任時給付や業績連動設計の場合は対象外となります。
税制非適格ストックオプション(SO)
非適格SOは、税制上の適格要件を満たさないストックオプションです。行使条件が固定され、権利付与時点で予約権数や行使価格が合理的に算定できる場合には、事前確定届出給与の対象となります。
おわりに
昨今、役員報酬の透明性確保やインセンティブ強化の観点から、株式報酬の導入が進んでいます。事前確定届出給与の適用には、税務上の要件に沿った報酬設計が求められます。届出期限や支給実績とのズレによるリスクを避けるためにも、関係部門が連携し、実行可能な設計・運用を行うことが重要です。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
はじめに
夏季の気温上昇が年々深刻化する中、熱中症による死亡災害は2年連続で30人前後と深刻な状況が続いており、職場における熱中症対策の重要性はますます高まっています。こうした背景を受け、労働安全衛生規則の改正により、2025年6月1日から「職場における熱中症対策の強化について」が施行されました。今回はその概要と、企業として求められる対応について整理します。
対象となる作業と義務化の概要
今回の改正により対象となるのは、「WBGT28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、もしくは1日4時間を超えて実施される作業」とされています。また、熱中症のおそれがある労働者を早期に把握、その状況に応じて迅速かつ適切に対処し、重篤化を防止するため、以下の事項が事業者に義務付けられました。①体制整備②手順作成③関係者への周知
特に屋外作業や高温環境下での作業が多い建設業、運送業、製造業などでは、対象作業が発生する可能性が高く、現場の実態に即した対策の整備が求められます。
WBGT値の測定と対応の具体例
WBGT値(暑さ指数)は、気温、湿度、輻射熱を総合的に評価した暑熱環境の指標です。対象となる事業場では、作業現場のWBGT値を定期的に測定し、その値に応じて作業時間の調整や休憩の確保、服装の見直しなどの対応が必要です。たとえば、WBGT値が28℃を超える場合は、こまめな休憩や作業時間の短縮が求められます。なお、測定機器による実測が困難な場合には、熱中症予防情報サイト等を活用して値を把握することも可能です。
教育・訓練の重要性
熱中症は予防可能な災害です。しかし、その実効性を高めるには、現場で働く従業員一人ひとりがリスクを正しく理解し、適切に行動することが重要です。このため、定期的な安全衛生教育において熱中症予防に関する内容を取り上げることが推奨されています。特に新入社員や高齢者などリスクの高い層への配慮が求められます。以下の事項についての事前教育が望まれます。①熱中症の症状②予防方法③緊急時の救急処置④過去の発生事例
おわりに
熱中症対策は、労働者の健康を守るだけでなく、業務の継続性や生産性の確保にも直結する重要な取り組みです。今回の義務化を機に、自社の対策状況を見直し、必要な体制整備や従業員への意識啓発を進めていくことが、今後の企業経営においても大きな意味を持つといえるでしょう。
はじめに
2024年6月時点で日本に在留する永住者数は902,203人で日本に在留する外国人3,588,956人に対し約25%を占めております。日本に在留する外国人の4人に1人は永住者ということになります。しかし、令和6年6月14日に改正された出入国管理及び難民認定法により在留資格の取消しが新設されまし た。今回はその内容について説明したいと思います。
「取消しとなる事由」
改正後は以下の事項が取消しされうる事項となります。
- 入管法上の義務違反
- 故意に公租公課の支払いをしないこと
- 特定の刑罰法令違反
入管上の義務違反
入管法が規定する永住者が遵守すべき義務で、退去強制事由として規定されている義務ではないが、義務の遵守が罰則により担保されているものについて、正当な理由なく履行しないことをいいます。 永住許可制度の適正化は、適正な出入国在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な者を対象とするものであり、大多数の永住者を対象とするものではありません。 そのため、例えば、うっかり、在留カードを携帯しなかった場合や在留カードの有効期間の更新申請をしなかった場合に、在留資格を取り消すことは想定していません。
故意に公租公課の支払いをしないこと
「公租公課」とは、租税のほか、社会保険料などの公的負担金のことをいいます。そして、「故意に公租公課の支払をしないこと」とは、支払義務があることを認識しているにもかかわらず、あえて支払をしないことをいい、例えば、支払うべき公租公課があることを知っており、支払能力があるにもかかわらず、公租公課の支払をしない場合などを想定しています。他方で、病気や失業など、本人に帰責性があるとは認めがたく、やむを得ず公租公課の支払ができないような場合は、在留資格を取り消すことは想定していません。取消事由に該当するとしても、取消しなどするかどうかは、不払に至った経緯や督促等に対する永住者の対応状況など個別具体的な事情に応じて判断することとなります。
特定の刑罰法令違反
ここで規定する刑罰法令違反は、具体的には、刑法の窃盗、詐欺、恐喝、殺人の罪などや自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の危険運転致死傷など、一定の重大な刑罰法令違反に限られており、いずれも故意犯を対象としています。したがって、交通事故を起こして過失運転致死傷の罪で処罰された場合は、本号の対象とはなりません。また、道路交通法は、取消事由として規定された刑罰法令には含まれていませんから、道路交通法違反により処罰された場合は、そもそも対象となりませんし、処罰の内容も拘禁刑に処せられたことが要件となっていますから、罰金刑に処せられた場合も、対象とはなりません。もっとも、永住者であっても、1年を超える実刑に処せられた場合は、罪名等にかかわらず、退去強制事由に該当して退去強制される場合があります。
その他注意事項
前述の内容は出入国在留管理庁が発する永住許可制度の適正化Q&Aを抜粋したものです。詳細については当Q&Aをご参照ください。その他、本制度に関してご質問がある場合はお気軽に弊社にお問い合わせください。