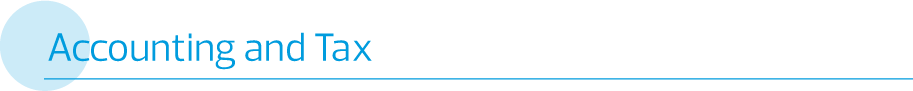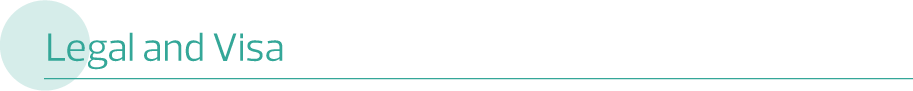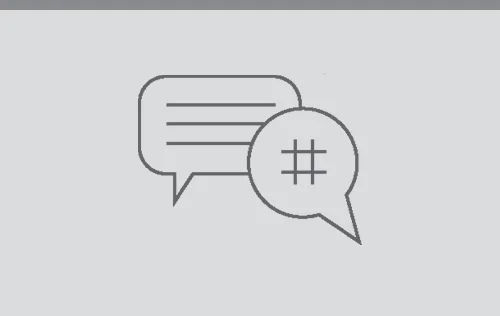RSM汐留パートナーズ・ニュースレター 2025年8月号
2025年8月1日
路線価上昇と相続・贈与、育児・介護休業法の追加改正、新株予約権発行の実務対応
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。今月のニュースレターでは、税理士法人より「路線価上昇と相続・贈与」、社会保険労務士法人より「育児・介護休業法の追加改正」、司法書士法人より「新株予約権発行の実務対応」をお届けします。
地価上昇を踏まえた相続・贈与における制度選択、10月施行の改正育児・介護休業法への対応、さらに新株予約権発行に関する会社法上の特例制度の活用ポイントなど、実務に直結するトピックを分かりやすくまとめています。今月のニュースレターもぜひお役立てください。
はじめに
毎年7月1日、国税庁は全国の主要道路に面した土地の価格である「路線価」を公表します。路線価は相続税・贈与税の課税価格算定に用いられる重要な指標であり、近年の地価上昇により税負担への影響も増しています。今回は、最新の路線価動向と、相続・贈与時に留意すべき制度について整理します。
路線価の概要
路線価は、毎年1月1日時点の地価を基に国税庁が評価し、実勢価格(公示地価)の約80%を目安に設定されます。これにより、全国で一律の基準に基づく土地評価が可能となり、相続税・贈与税の課税標準に用いられます。路線価は毎年7月1日に公表され、原則として翌年1月1日までの評価に適用されます。
路線価のトレンドと傾向
全国平均の動向
2025年の全国平均路線価は前年比2.7%の上昇と、4年連続のプラスとなりました。上昇率は2024年(2.3%)、2023年(1.5%)と比べても拡大し、現行調査方式(2010年以降)で最大となっています。
地域別の傾向
東京都では2025年に8.1%上昇(前年5.3%)と加速しており、大阪市や名古屋市、福岡市など中核都市でも堅調な上昇となっています。一方、人口減や経済停滞が続く地域では、横ばい又は下落傾向であり、地域間で二極化が進行しています。
相続時精算課税制度
60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する際に選択でき、累計2,500万円までが非課税、超過分には一律20%の贈与税が課されます。2024年以降、年110万円までの基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は申告不要かつ相続財産への加算も不要です。この制度は一度選択すると暦年課税に戻れず、「時価の固定」と「税の前払い」という特徴があるため、地価動向や資産内容を踏まえた判断が重要です。即ち、将来値上がりが見込まれる資産には有利ですが、値下がりした場合は課税負担が重くなる可能性もあります。
また、暦年課税では相続前7年以内の贈与が相続税に加算されるため、贈与計画全体の見直しも求められます。
小規模宅地等の特例
被相続人の居住用・事業用宅地について一定要件を満たせば相続税評価額を大幅減額できる制度で、主な適用区分は以下の通りです。
| 種類 | 限度面積と減額率 | 要件等 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡まで80%減額 | 配偶者や同居の子が継続居住することが原則 |
| 特定居住用宅地等・ 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡まで80%減額 | 被相続人の事業用土地が対象 |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで50%減額 | アパート・駐車場等の賃貸用土地が対象 |
但し、適用要件は複雑で、共有名義・二世帯住宅、「家なき子特例」など例外も多く、事前確認が不可欠です。特例適用後に土地を売却・転用した場合は遡及取消となる場合もあるため、慎重な運用が求められます。
おわりに
路線価の上昇により、相続・贈与にかかる税負担や制度選択の重要性が一層高まっています。特例や制度の適用には慎重な検討が必要であり、早めの対策が将来の円滑な資産承継につながります。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
ます。特例や制度の適用には慎重な検討が必要であり、早めの対策が将来の円滑な資産承継につながります。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
はじめに
育児と仕事の両立支援をさらに推進するため、育児・介護休業法が改正されました。本年4月1日の改正施行に続き、10月1日にも新たな改正内容が施行されます。今回は、10月施行分の改正に向けて、企業として対応が求められる具体的な実務上のポイントをご紹介します。
柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
今回の改正により、事業主は柔軟な働き方を可能とするための制度を整備することが義務付けられました。対象は、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者です。企業は、当該労働者が選択できるよう、以下の5つの措置のうち2つ以上を講じる必要があります。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制または時差出勤制度)
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置・運営等
- 新たな休暇制度(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度の整備
また、これらの措置を講じるにあたっては、施行日前に、事業所単位で過半数労働組合または労働者の過半数代表者から意見を聴取することが必要です。意見聴取の記録は、書面やメールなど記録が残る方法で確実に保管することが推奨されます。
なお、各措置の詳細については、厚生労働省が公表している以下のQ&Aをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf
個別の意向聴取と配慮等の義務化
これまで、労働者から本人または配偶者の妊娠・出産等について申出があった場合には、育児休業等の制度に関する個別周知と意向確認が義務付けられていました。改正後はこれに加え、就業条件等に関する個別の意向聴取が義務化され、聴取した意向に対して企業側の配慮が求められることになります。
意見聴取の実施時期としては、以下のタイミングが想定されています。
- 本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があったとき
- 子が3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間
- 育児休業後に労働者から申出があったとき(復職時など)
また、前述の柔軟な働き方を実現するための措置が事業主に義務付けられることに伴い、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、講じた措置の内容について個別周知、意向確認、意向聴取および配慮を行うことも新たに義務化されます。これらの対応も、子が3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間に行う必要があります。
おわりに
今回の法改正は、育児と仕事の両立をより実効的に支援するための重要一歩です。企業には、制度整備だけでなく、従業員一人ひとりと丁寧に向き合う姿勢が求められます。これを機に、自社の育児支援制度全体を見直し、誰もが安心して働ける職場環境の構築を目指しましょう。
はじめに
公開会社ではない株式会社が新株予約権の発行をするときは、その都度、会社法第238条第1項に基づき、株主総会の決議によって募集事項を定めます。この募集事項の決定は、会社法第239条第1項に基づき、株主総会の決議によって取締役会(取締役会設置会社とします)に委任することができますので、この方法を利用すると、一定の制限の下、取締役会の決議により機動的に新株予約権の発行ができるようになります。特に、数ヶ月内に複数回に分けて新株予約権を発行する場合は便利です。
1年以内という有効期限
募集事項の委任に基づく取締役会決議は、割当日が当該委任に係る株主総会決議の日から一年以内の日である新株予約権についてのみその効力を有するものとされています。
種類株主総会の要否を確認
種類株式発行会社が新株予約権の募集事項の決定又はその委任をするときは、定款に別段の定めのない限り、当該新株予約権の目的である種類の株式に係る種類株主総会が必要となります。普通株式、A種類株式、B種類株式を発行している株式会社が普通株式を目的とする新株予約権を発行するときは、株主総会の決議に加え、普通株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議も求められます。た だし、この場合において普通株式を有する株主が存在しない場合や、定款に会社法第238条第4項の種類株主総会の決議を要しない旨を定めている場合は、当該種類株主総会の決議は不要です。
募集事項の委任の内容
新株予約権の募集事項を取締役会へ委任するときは、株主総会の決議によって、会社法第239条第1項に掲げる事項を定めます。当該事項には新株予約権の内容が含まれますので、例えば無償ストックオプションのケースにおいては、取締役会で決めることができる募集事項は新株予約権の割当日及び数(ただし、上限は株主総会で定められる)くらいとなります。行使に際して出資される財産の価 額や取得条項、行使期間や(定める場合は)行使条件等は新株予約権の内容として株主総会で定めるため、取締役会で自由に定めることができるわけではありません。なお、募集事項を取締役会へ委任する場合における株主総会で定める行使期間は、2025年10月1日から2030年9月30日までといった定め方だけではなく、「割当日から5年」や「付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日まで」といった定め方も可能とされています。
新株予約権の機動的な発行に関する制度
2024年9月から、会社法の特例として、産業競争力強化法において「募集新株予約権の機動的な発行」に関する制度が創設されました。この制度を利用すると、株主総会の決議によって取締役会へ募集事項を委任する場合において、その有効期間が1年ではなく設立から15年までとなり、権利行使価額・行使期間もその都度取締役会で定めることができるというメリットがあります。一方で、経 済産業大臣及び法務大臣の確認を受ける必要がある、割当日の2週間前までに株主に募集事項を通知する、一定の場合には株主総会の決議が求められるといった注意すべき点もありますので、この制度を利用するときはメリット・デメリットのどちらも理解した上で利用することをお勧めします。