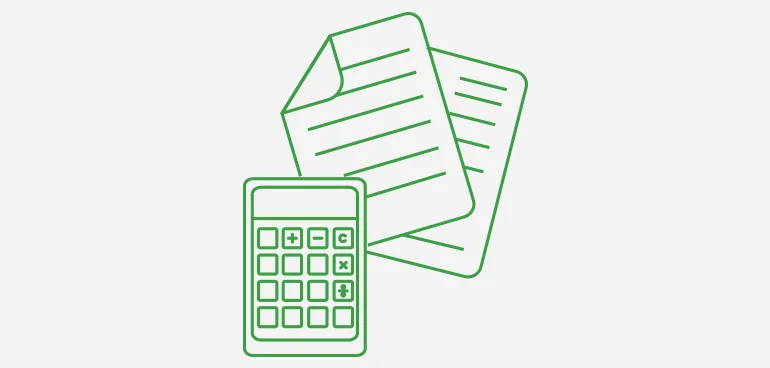税制改正を踏まえた固定資産関連優遇制度のポイント
2025年10月10日
はじめに
先般の参議院選挙では、消費税や社会保険料の負担軽減が主要な政策課題の一つとして取り上げられました。こうした政策は、消費者の負担を和らげるだけでなく、消費税の引き下げによる企業の設備投資促進や、社会保険料負担の軽減による企業コストの圧縮を通じて、最終的には給与の引上げにつながると主張されていました。中小企業にとっては、税制のわずかな変更であっても経営に大きな影響を与える可能性があるため、今後の動向を注視する必要があります。もっとも、税制は市場動向や政治情勢の変化に左右されやすく、先行きを見通すのは容易ではありません。一方で、現時点でも中小企業が活用できる各種税制優遇制度は整備されており、特に固定資産や設備投資に関連する税制優遇措置の中には、効果が大きいにもかかわらず十分に活用されていないものがあるのが実情です。本コラムでは、中小企業が現行税制の枠内で活用可能な固定資産関連の税制優遇措置をご紹介します。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例と適用範囲
この特例措置はこれまでの税制改正で繰り返し延長されてきており、令和6年度の改正により令和8年3月31日まで適用期間が延長されています。内容は、原則、従業員数500人以下で青色申告書を提出する中小企業者等(一定の所得制限あり)が、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その取得価額に相当する金額を損金として算入できるというもので、年間の限度額は300万円とされています。
限度額が「30万円未満」とされていますが、取得価額が10万円未満の資産は消耗品と同じ扱いで取得年度に全額損金算入できるため、実質的には10万円以上30万円未満の資産の合計額が対象となります。例えば、28万円の資産を11個、合計308万円を購入した場合、10個分の280万円まで適用を受けられます。限度額まで償却不足額はありますが、残りはこの適用を受けられないことになります。
また、30万円未満かどうかの判定は、企業が会計処理を税込方式で行っているか税抜方式で行っているかによって異なり、金額は1単位ごとに判定します。例えば、免税事業者の場合は税込処理しか認められていないため、税込金額で30万円未満かどうかを判定します。さらに1単位の判定は、「通常一単位として取引されるその単位」とされていますが、その具体的な内容は必ずしも明確ではありません。
国税庁の情報によれば、例えば以下のような例が挙げられています。
- 応接セット:椅子とテーブルが一組となって機能するため、「1組」として判定
- カーテン:1部屋全体で機能することから、「1部屋分」を1単位として判定
このように、資産の機能性や関連性を踏まえて、1式または1組として判断することが求められます。単体で見れば30万円未満であっても、セットや一式での取引が一般的な場合には、合算して判定する必要がある点に留意しましょう。
さらに、所有権移転外リース取引に該当するリース資産も特例の対象となるため、この点についても再度検討してみることが望ましいでしょう。
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の比較と活用ポイント
中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制は、いずれも主に青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者等を対象とする優遇税制で、名称や制度内容が似ているため混同されがちですが、実際にはいくつかの相違点があります。主な違いを整理すると、次の通りです。
| 中小企業投資促進税制 | 中小企業経営強化税制 | |
|---|---|---|
| 節税メリット | 以下から選択 ①特別償却:取得資産の基準取得価額の30%を償却費として計上可能 ②税額控除:基準取得価額の7%(資本金3,000万円以下が対象)を法人税から控除可能 | 以下から選択 ①即時償却:取得価額の全額を償却費として計上可能 ②税額控除:取得価額の10%(資本金3,000万円以下が対象 )または7%(資本金3,000万円超1億円以下が対象 )を法人税から控除可能 |
| 対象資産 | 特定機械装置等 (対象資産は比較的限定される) ・器具備品、建物付属設備等は対象外 | 特定経営力向上設備等 (対象資産は広い) ・一定の器具備品、建物付属設備等も対象 |
| 運用手続 | 確定申告時の申告のみ | 「経営力向上計画」の事前認定が必要。A~D類型に応じて、工業会等の証明 |
中小企業経営強化税制は取得年度における節税効果がより大きい一方で、追加の手続が必要となります。また、いずれの制度も「税額控除限度超過額の1年繰越」が認められているだけでなく、減価償却による優遇を選択する場合、両制度には「特別償却」と「即時償却」という違いはありますが、いずれも償却不足額を翌期以降に繰り越せるという点は共通しています。取得年度に償却限度額まで減価償却費を計上せず、翌事業年度に残りの枠を用いて計上することが可能になるため、活用の幅が広く、実務上の利便性が高い制度といえます。
中古資産の耐用年数
近年は、中古の固定資産を購入して活用するケースが増加傾向にあります。中古資産を購入した場合も、新品の資産と同様に国税庁が公表している耐用年数表に基づき法定耐用年数を適用している例が多く見られます。ただし、中古資産といっても状態や経過年数には幅があるため、税法でも法定耐用年数だけではなく、事業において使用を開始した時点から見積もられる使用可能期間を耐用年数として採用することも認められています。本来であれば、各資産の実態に応じて耐用年数を個別に設定することが望ましいと考えられますが、実務上ではその判断が困難な場合が大半を占めます。そのため、簡便法により算定した耐用年数を適用可能とする制度が設けられています。
簡便法による耐用年数は以下のように算定します。
① 法定耐用年数を既に全て経過した資産
残存耐用年数 = 法定耐用年数 × 20%
② 法定耐用年数の一部を経過している資産
残存耐用年数 = (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%
①のケースでは減価償却率に大きな差異が生じやすいため、中古資産を購入した際は必ずご検討されることをお勧めします。
ただし、中古資産を事業で使用するために多額の資本的支出を行い、その金額が仮に新品を取得するとした場合の価額(再取得価額)の50%相当額を超える場合には、使用可能期間の見積りや簡便法で算定することは認められず、法定耐用年数を用いる必要があります。言い換えると、再取得価額の50%を超える資本的支出が行われた中古資産は、実質的に新品に近い水準で使用可能と判断されるため、法定耐用年数の適用が求められます。
おわりに
本コラムでは、中小企業を対象とした固定資産関連の税制優遇措置の一部を取り上げました。実際に各制度を適用する際には、制度ごとに対象法人の要件や適用条件など、詳細な規定が設けられています。そのため、制度の活用にあたっては慎重な判断が求められます。ぜひ、税理士等の専門家と十分に協議のうえ、貴社にとって最適な選択をしていただければ幸いです。