新リース会計基準と税務、被扶養者認定要件の改正、経営・管理ビザ要件の厳格化
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。今月のニュースレターでは、税理士法人より「新リース会計基準と税務」、社会保険労務士法人より「被扶養者認定要件の改正」、行政書士法人より「経営・管理ビザ要件の厳格化」をお届けします。
新リース会計基準の導入に伴う税務上の影響、健康保険の被扶養者認定基準引き上げによる実務対応、そして「経営・管理」ビザの取得・更新における要件強化など、制度改正や実務対応に関わる重要なポイントを分かりやすくまとめています。今月のニュースレターもぜひお役立てください。
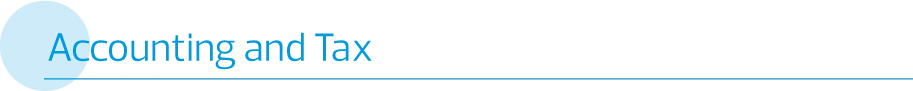
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は2024年9月13日、国際的整合性の確保を目的として、新リース会計基準(企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等)を公表しました。適用は2027年4月1日以後開始の連結会計年度・事業年度の期首からで、2025年4月1日以後開始分から早期適用も可能です。これを受け、国税庁は2025年6月30日に改正法人税基本通達等を公表しました。今回は、新会計基準と改正通達の概要を、会計と税務の一致・不一致の観点から整理します。
新リース会計基準の概要
新基準では、借手の会計処理におけるファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類を廃止し、短期・少額のものを除き、すべてオンバランス処理(使用権資産・リース負債の計上)とします。「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約またはその一部分」をリースと定義し、特定資産の有無と使用支配権の移転の有無で識別します。従来リース外であった不動産賃貸借契約や役務提供契約も実質リースとして判定される場合があります。契約にリース構成部分と非構成部分がある場合は、独立価格比率で按分します。リース期間は、解約不能期間に加え、延長・解約オプションの合理的行使見込み期間を含めます。損益計算書には減価償却費と利息相当額を計上します。
改正法人税基本通達の概要
改正通達では、新リース会計基準に基づく借手の会計処理を法人税でも原則認めつつ、区分は従来通りとしています。主なポイントは以下の通りです。
| 論点 | ポイント |
|---|---|
| 資産の賃貸借の範囲明確化 | 民北条の賃貸借に関わらず、「資産使用権の一定期間の移転」も含むことを明示。新会計基準でリースとして識別される実質リースも対象。 |
| リース構成部分と非構成部分の区分 | リース構成部分は減価償却規定やリース取引規定を、非構成部分は賃貸借費用規定を適用適用。 |
| リース期間の取扱い | 所有権移転外リースの償却期間は、会計上のリース期間(解約不能期間+合理的行使見込み期間)を用いることを新設。原則、税会一致。 |
| 超過リース期間定額法の導入(経過措置) | 2027年4月1日より前に契約した所有権移転外リースについて、残価保証額を含め備忘価額1円まで償却可能。適用には届出が必要。 |
主な税務調整
新基準では原則すべてオンバランスとなる一方、税務では従来通りオペレーティング・リース取引を賃貸借処理とするため、税会不一致が生じます。会計では使用権資産の減価償却費と利息法による利息相当額(初期多額傾向)を計上し、税務では債務確定分のリース料のみ損金算入するため、期間差が発生します。調整方法は、①総額法(会計費用を加算・留保し、税務損金を減算・留保する方法)と②純額法(差額のみを加減算する方法)の2通りです。国税庁は総額法を例示していますが、純額法も認められており、会計・税務処理の流れに応じて適切に申告調整を行う必要があります。
おわりに
新リース会計基準の導入は、会計処理だけでなく法人税申告にも大きな影響を与えます。特にオペレーティング・リース取引における税会不一致とその申告調整は、実務上の重要な論点です。契約の洗い出し、リースの識別、リース構成部分と非構成部分の区分、リース期間の決定、会計と税務の乖離に応じた正確な税務調整まで、多岐にわたる対応が求められます。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

健康保険の被扶養者認定要件の変更について
2025年10月1日より、健康保険の被扶養者認定要件が一部改正されます。今回の改正は、2025年度の税制改正による「特定扶養控除」の要件見直しに合わせ、社会保険制度との整合性を図ることを目的としています。特に19歳以上23歳未満の被扶養者に関する認定に大きな影響がありますので、その概要をお知らせします。
制度改正のポイント
対象となるのは、「被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者」です。これまで扶養認定の基準は年間収入130万円未満でしたが、改正後は150万円未満に引き上げられます。年齢の判定は従来どおり、その年の12月31日時点で行います。例えば2025年12月31日時点で20歳の方は、年間収入が150万円未満であれば扶養認定されます。
また、認定日が2025年9月30日以前であれば従来の基準(130万円未満)が適用されます。遡及認定の場合も同様で、認定日が改正前であれば新基準は適用されません。したがって、扶養追加の申請時期によって基準が異なる点にご注意ください。なお、年間収入が150万円未満かどうかの判定は従来どおり、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
留意点
- 配偶者については従来どおり「年間収入130万円未満」が基準であり、改正の対象外です。
- 障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害がある方は、引き続き「年間収入180万円未満」で認定されます。
- 学生であることは要件ではなく、あくまでも年齢で判断されます
- 「年収の壁・支援強化パッケージ」により、一定の場合には基準額を超えても事業主証明により扶養認定が継続できる場合があります。
参考リンク:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
実務への影響
今回の見直しは、学生アルバイトや短時間勤務の若年層を扶養に入れているケースに特に影響すると考えられます。収入基準の引き上げにより、これまで扶養から外れていた方が認定されやすくなる一方で、認定日によって基準が異なるため、手続上の確認が煩雑になる可能性があります。従業員への案内や社内の確認体制の整備が重要となるでしょう。
おわりに
今回の改正により、若い世代が働きながら扶養に入れる範囲が広がります。一方で、認定基準が二段階に分かれるため、運用上の判断にはこれまで以上に注意が必要です。制度改正を正しく理解し、スムーズな手続きに備えておくことが求められます。
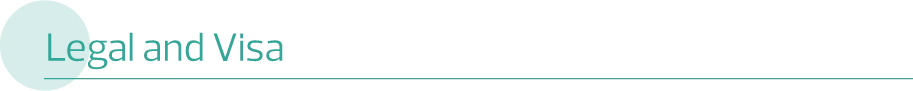
はじめに
2025年8月26日、パブリックコメントで『「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について』が発せられました。現在のところパブリックコメントの段階ですが、施行予定日が2025年10月中旬となっており、期限が迫っております。今回はパブリックコメントの内容の詳細を紹介したいと思います。
基準省令の改正について
①申請する事業の規模について
【現在】
以下のいずれかに該当すること。
- ア その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
- イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
- ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること。
【改正後】
以下のいずれにも該当すること。
- ア 常勤の職員の数について1人以上従事すること
- イ 資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること
②経営に従事する者の学歴又は職歴に関する基準の創設
- ア 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
- イ (申請人が事業の経営に従事しようとする場合においても、)事業の経営又は管理について3年以上の経験(特定活動の在留資格(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。
提出書類の改正について
「経営・管理」に係る在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請等をする際の提出する書類について以下のとおり改正するとされております。
①事業計画書に専門家の評価が必要になる
事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならないことを定めるとされております。専門的な知識を有する者が具体的にどのような人物をさすかまだ確認できておりませんが公認会計士や中小企業診断士などが想定されます。なお、現行では事業計画書の提出が必要とされているのはカテゴリー3とカテゴリー4の会社となっております。
②事業の規模に係る提出資料について
【現在】
以下のいずれかを提出する。
- ア 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人以上である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
- イ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
- ウ その他事業の規模を明らかにする資料
【改正後】
以下のいずれも提出する。
- ア 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
- イ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
③学歴または職歴を証する文書の提出
改正後は事業の経営または管理に従事するいずれの場合にも学位を有することを証する文書または職歴その他の経歴を証する文書を提出しなければなりません。
④在留期間更新許可申請時について
事業の規模に係る提出資料について以下のように改正されました。
【現在】
以下のいずれかを提出する。
- ア 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びにその数が二人以上である場合には、当該二人の職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
- イ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
- ウ その他事業の規模を明らかにする資料
【改正後】
以下のいずれも提出する。
- ア 当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
- イ 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
その他注意事項
今回の改正により「経営・管理」の基準が非常に厳格化されました。すでに旧基準で許可を受けた方の今後の更新許可申請等についてはまだ発表はありません。新しく日本で会社を設立して「経営・管理」の在留資格を取得するには法人設立には司法書士、在留資格の取得は行政書士、事業計画書の評価は公認会計士や中小企業診断士等といった専門家の協力が今後ますます必要になります。弊社はこれら一連のサービスをワンストップで提供できる体制を整えております。何かご質問やご依頼があれば是非ご連絡いただければ幸いです。

