令和7年 年末調整の改正ポイント、カスタマーハラスメント対策の義務化、経営・管理在留資格の基準省令改正
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。
今月のニュースレターでは、税理士法人より「令和7年 年末調整の改正ポイント」、社会保険労務士法人より「カスタマーハラスメント対策の義務化」、行政書士法人より「経営・管理在留資格の基準省令改正」をお届けします。
所得税控除制度の見直しに伴う年末調整準備、カスタマーハラスメント防止義務化に向けた体制づくり、そして「経営・管理」在留資格における新基準への対応など、制度改正と実務対応の観点で押さえておきたい主要トピックをまとめています。今月のニュースレターもぜひお役立てください。
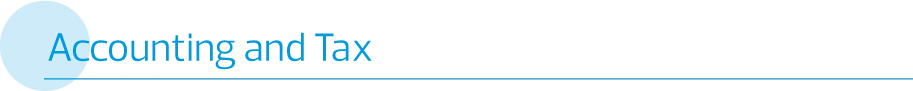
はじめに
11月に入り、年末調整の準備を進める時期となりました。年末調整は、給与所得者の1年間の所得税を確定させる重要な手続です。令和7年の年末調整は、基礎控除や給与所得控除など所得税の制度改正が大きな特徴です。制度改正を反映すべき書類や計算処理も多く、例年にも増して慎重な対応が求められます。今回は、こうした制度改正の概要と実務上の留意点を整理します。
令和7年の改正点
① 基礎控除の引き上げ
従来一律48万円であった基礎控除額が、合計所得金額132万円以下の場合は95万円となり、132万円を超える層についても令和7・8年の2年間限定で段階的な上乗せ控除が設けられます。控除拡大により課税所得が減少します。
② 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入190万円以下の者に適用されます。基礎控除額の最大95万円と合わせると、年収160万円程度までは所得税が課されない計算になります。
③ 扶養親族等の所得要件の緩和
扶養控除や配偶者控除等の判定基準が、合計所得金額48万円以下から58万円以下に引き上げられます。これにより、アルバイト収入のある学生やパート収入のある配偶者が扶養対象となるケースが増えます。
④ 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族を対象とする新たな控除制度が創設されます。対象親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入ベースで123万円超188万円以下)の場合、所得金額に応じて3万円から63万円の控除を受けられます。
これらの改正は2025年12月1日から施行され、11月までの源泉徴収事務には変更はありません。1月から11月までは従来どおりの源泉徴収を行い、12月の年末調整で新制度による精算を行う点に注意が必要です。
実務上の留意点
扶養親族等の所得要件の緩和に伴い、新たに扶養控除等の対象となる親族がいないかを確認する必要があります。該当する場合は「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受領し、適用を判定します。また、「特定親族特別控除」を適用する従業員からは、新設の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。大学生の子を持つ場合は、事前にアルバイト収入額を確認してもらうよう周知します。計算面では、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用します。さらに、国税庁が公表する「令和7年分給与所得に対する源泉徴収簿」には特定親族特別控除欄が設けられていないため、余白欄を利用するなどの対応が求められます。
おわりに
令和7年分の年末調整のポイントは、控除制度の改正対応にあります。扶養親族や特定親族の該当有無を早期に確認し、必要書類の案内・回収・計算表の更新を進めることが重要です。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

カスタマーハラスメントへの対応について
お客様対応に従事する従業員が、理不尽な言動や過度な要求を受け、心身に負担を抱えるケースが増えています。いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」は、もはや単なるクレームでは済まされない問題であり、企業としての対応が急務です。従業員の安全と尊厳を守ることは、企業の持続的成長と社会的信頼の確保に直結します。近年は法制度面でも対応強化の動きが進んでおり、本稿では企業が取るべき対応の方向性を整理します。
法制度の動向
2025年6月、労働施策総合推進法の一部改正法案が成立・公布されました。改正により、カスタマーハラスメント対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」とする新たな規定が設けられます。施行日は「公布日から1年6か月以内」の政令で定められる予定で、2026年中の施行が見込まれています。この改正のポイントは、これまで指針やガイドラインにとどまっていたカスハラ対策が、法的義務に格上げされる点です。なお、カスタマーハラスメントの主体は、「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者」とされ、顧客に限られない点にも注意が必要です。
企業への影響・留意点
制度改正を見据え、企業は早期に以下の体制整備を進めることが求められます。
1.定義・線引きの明文化
「どのような言動がカスハラに該当するか」を社内規程や就業規則に明確に定め、従業員に周知します。ガイドラインでは、顧客等の言動が「社会通念上許容される範囲を超え」「就業環境を害するもの」とされる場合に該当します。
2.相談窓口と対応体制の整備・周知
従業員が安心して相談できる窓口を設置し、相談内容の記録・報告体制を整えます。匿名相談や外部チャネルの導入も有効です。
3.調査・対応プロセスの設計
事案発生時の調査手順、被害者保護、顧客対応方針、再発防止策までを一貫して実施できるプロセスを整備明文化します。
おわりに
これまでカスハラ対策は、企業の自主的な取組みに委ねられてきましたが、2025年の法改正を契機に義務化の流れが本格化します。特に東京都・北海道・群馬県など、条例で独自の対応が進む地域では、早期の準備が欠かせません。
企業は、まず実態を把握し、規程整備→相談体制構築→対応プロセス策定の順で体制づくりを進めましょう。当社では、カスハラ対応規程の設計支援や対応フロー策定など、実務に即したサポートを行っております。ご関心のある方はお気軽にお問合せください。
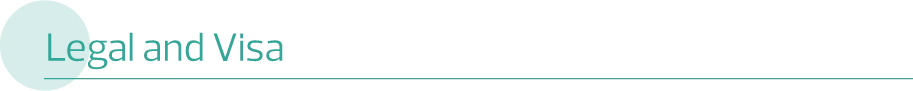
はじめに
2025年10月16日、「経営・管理」に係る基準省令(「経営・管理」の基準を定める省令)が改正され施行されました。前回のニュースレターではパブリックコメント段階であったため、その概要についてお伝えしましたが、今回はすでに「経営・管理」で在留中の方の取り扱いについてさらに細かく説明していこうと思います。
令和10年10月16日までの猶予期間
現在「経営・管理」で在留中の方で改正された新しい基準を満たしていないは令和10年10月16日までに新しい基準を満たす必要があります。ただし3年間の猶予が与えられたといって安心してはならないようです。令和10年10月16日までの在留期間更新許可申請においても経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、拒否判断を行うとされております。そのため、新基準を満たすようにロードマップを作成し計画的に増資等を行うことをおすすめいたします。
基準省令の改正のおさらい
令和10年10月16日までに満たさなければならない改正された基準は大きくわけて4点です。
①常勤職員の雇用について
- 常勤職員とはパートタイマーなどとは異なります。以下、勤務時間等待遇から見た場合をご参照ください。労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上の者。
- 入社日を起算点として、6か月間継続し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し10日以上の有給休暇が付与されること。
- 雇用保険の被保険者であり、一週間の所定労働時間が30時間以上であること(例外あり)。
上記に加え日本人、日本人の配偶者等、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、定住者の者を雇用しなければなりません。
②資本金の額等について
従前の基準である資本金500万円から新基準では3000万円に変更されました。現在3000万円の資本金の場合、2500万円の増資が必要になります。増資には単純に金銭の投資を行うほか、利益剰余金や役員貸付金を増資できることもあります。また自己所有の不動産がある方は現物出資で投資することもできますが、このような増資方法をとることが認められるかは管轄の出入国在留管理局に確認が必要です。
③日本語能力について
以下申請者又は常勤の職員がいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。相当程度に日本語については日本人、特別永住者以外であれば以下のいずれかが求められます。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
なお、当③でいう常勤職員とは①の常勤職員とは異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の表に記載されているものでも構いません。
④経歴(学歴・職歴)について
申請者が経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する必要があります以下のいずれも提出する。
現在「経営・管理」の在留資格で在留中の方も3年の猶予措置のうちに3年以上の経営経験を有することとなるので、この点は心配ありません。
その他注意事項
財務状況がよく、金銭的に余裕があるのであれば増資は乗り越えられる問題ですが、多くの経営者の頭を悩ませているのが常勤職員1名以上の雇用のようです。1人会社で頑張ってこられた外国人経営者の方も多く、自社に就職してくれる求職者とのご縁は容易には築けません。その上、常勤職員の在留資格や日本語能力等についても制限があるためより一層厳しいものになります。資本金3000万円の規模の事業売上であれば、従業員を1名以上雇用する必然性があるというのが出入国在留管理庁の考えなのだと自分なりに推測します。そうすると新基準を満たしたとしても売上規模などによって許否判断がなされることも十分に考えられます。何かご質問やご依頼があれば是非ご連絡いただければ幸いです。

