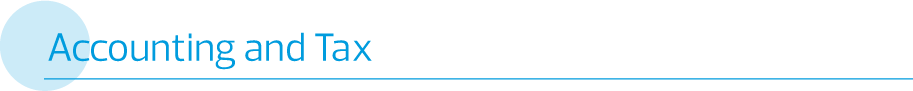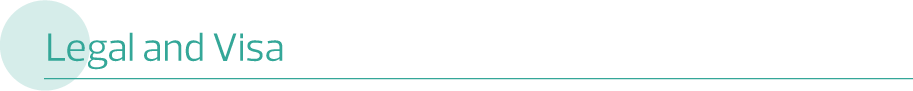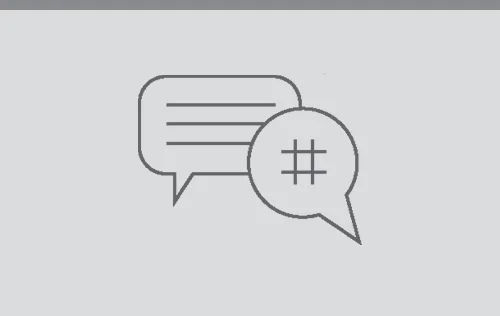RSM汐留パートナーズ・ニュースレター 2025年10月号
2025年10月3日
インボイス制度 2026年以降、2025年度最低賃金改定の対応、株主総会招集手続き
日頃よりお世話になっております。RSM汐留パートナーズです。今月のニュースレターでは、税理士法人より「インボイス制度 2026年以降」、社会保険労務士法人より「2025年度最低賃金改定の対応」、司法書士法人より「株主総会招集手続き」をお届けします。
インボイス制度の経過措置縮小に伴う実務対応、全国的に1,000円を超える最低賃金引き上げへの人事・労務対応、そして株主総会招集に関する基本手続きなど、制度改正や実務対応に関わる重要なポイントを分かりやすくまとめています。今月のニュースレターもぜひお役立てください。
はじめに
2023年10月に始まったインボイス制度は、導入から2年が経過しました。当制度は仕入税額控除の厳格化や請求書管理の煩雑化など、事業者に多くの実務負担をもたらす一方で、消費税の適正な課税関係を確保するという目的があります。現在は移行期の負担を和らげるための「経過措置」が設けられていますが、2026年10月以降はこの経過措置がさらに厳格化される過渡期を迎え、取引や契約の見直しが一層求められることになります。今回は、インボイス制度と経過措置の概要を整理し、来年以降に備えるための主な留意点を考えていきたいと思います。
インボイス制度の概要と経過措置の内容
インボイス制度では、適格請求書発行事業者として登録した課税事業者のみがインボイスを発行でき、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるためには、このインボイスを保存することが必要となります。これにより、免税事業者や未登録事業者との取引では、原則として仕入税額控除が不可となります。但し、急激な負担増の影響を避けるため、導入から6年間は「経過措置」が設けられ、控除率を段階的に縮小する仕組みが採られています。
具体的には、2023年10月から2026年9月までは仕入税額の80%、2026年10月から2029年9月までは50%を控除可能とし、2029年10月以降は控除ができなくなります。なお、経過措置を利用するには、区分記載請求書等の保存に加え「80%控除対象」「免税事業者」など、帳簿に経過措置対象である旨の記載が必要です。
来年に向けた留意点
2026年10月以降は、控除率減少による税負担増が避けられず、特に次の点が重要です。
①コスト負担増への対応
仕入税額控除が半減することで実質的なコストが増えるため、価格改定や契約条件の調整を検討する必要があります。
②取引先の整理と将来対応
2029年10月以降は控除不可となるため、取引を継続するのか、取引先に発行事業者への登録を促すのか、あるいは取引先を見直すのかの判断が必要です。免税事業者側も、売上規模や主要取引先の構成を踏まえて登録を検討するタイミングと言えます。
③経理・システム体制の整備
経過措置対象仕入には特例対象の明記が必須のため、帳簿・会計システムを点検し、正確に管理できる体制にあるか確認が必要です。
④影響試算と社内共有
控除減少分が利益や資金繰りに与える影響を試算し、社内共有して価格戦略や取引方針に反映させることが重要です。
おわりに
インボイス制度は取引の透明性や税収の適正管理を目的に導入され、経過措置はその移行負担を和らげるための仕組みです。2026年10月からは控除率が50%に縮小され、将来的には控除不可となります。こうした段階的な変化を見据え、各事業者は取引先の整理や契約内容の見直し、経理体制の強化を早めに進めることが重要です。ご不明点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
はじめに
最低賃金の改定は、物価上昇や人手不足といった経済環境を背景に、近年ますます注目を集めています。2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金は、全国平均・都道府県別いずれにおいても過去最大規模の引き上げが見込まれており、企業の人事・労務担当者にとって喫緊の課題となっています。本稿では、最新の改定状況を整理するとともに、企業が留意すべきポイントを確認します。
最新の最低賃金改定の状況
厚生労働省の中央最低賃金審議会は2025年8月に「令和7年度地域別最低賃金改定の目安」を公表しました。その内容は、全国加重平均で時給1,118円とされ、前年から63円の引き上げとなります。これは過去最大の上昇幅であり、全都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みです。
東京では1,226円、神奈川1,225円、大阪1,177円といった水準が示されており、従来900円台であった地方県もすべて1,000円台に移行します。なお、実際の発効は10月1日以降、都道府県ごとに告示を経て順次実施される予定です。これにより、最低賃金の地域間格差はやや縮小しつつ、全国的に高水準化が進むこととなります。(参考リンク:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)
企業への影響・留意点
今回の引き上げは、パート・アルバイト・契約社員を中心に人件費増加を直撃することが想定されます。とりわけ最低賃金付近で雇用している事業所では、シフトや勤務時間の組み方、固定残業代や各種手当の水準を含め、給与体系全体を再点検する必要があります。
また、全都道府県で1,000円を超えることで、これまで地域間のコスト差を背景にしてきた事業運営にも影響が及びます。人材確保や離職率への波及効果も予想されるため、単なるコスト対応にとどまらず、採用戦略や労働条件の魅力付けを含めた総合的な施策が求められます。さらに、各都道府県ごとに正式決定の時期や額が異なるため、法令遵守の観点からも決定内容を注視し、給与規程の修正やシステム対応を計画的に進めることが重要です。
おわりに
2025年度の最低賃金改定は、全ての都道府県で1,000円を超えるという大きな節目を迎えます。企業にとっては人件費負担の増大という厳しい側面がある一方で、従業員の生活安定や人材確保に資する契機ともなり得ます。企業は、自社に与える影響を早急に試算し、給与制度の見直しや採用・定着施策の再構築を進めていく必要があります。当社としても、最低賃金改定に伴う制度対応や実務面のご相談を幅広くサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
はじめに
株式会社が定款の変更、募集株式の発行、役員報酬の決定等を行うときは株主総会の決議が必要となり、株主総会を開催するための招集手続きは会社法によって定められています。株主総会の決議が後から取消・無効とならないよう、その手続きは会社法に則って行うことが求められます。ここでは、非公開会社である取締役会設置会社(株主は数名から数十名程度)が臨時株主総会を招集する手続きの概要を確認します。なお、ここでは株主による株主総会の招集の請求手続きは含まないものとします。
株主総会の招集の決定
株主総会を招集するときは、取締役会の決議によって会社法第298条第1項(株主総会の日時及び場所等)の事項を定めます。非公開会社においては、書面によって議決権を行使する(書面投票)又は電磁的方法によって議決権を行使する(電子投票)ことができることとすることを定めるケースは少なく、当日出席できない株主のために招集通知と併せて委任状を発するケースが多いでしょう。
株主総会の招集期間
株主総会を招集するときは、次に掲げる日までに株主に対してその通知を発します。
- 公開会社又は書面投票・電子投票を認める場合:2週間前まで
- 非公開会社:1週間前まで
- 取締役会非設置会社:定款で定めた日(定款に定めがなければ1週間前まで)
この招集期間は、上記2の場合、招集通知を発する日から株主総会の開催日まで中7日の期間が求められますので、株主総会の1週間前(中6日)に発したのでは期間が足りないのでご注意ください。
株主総会の招集通知の内容
株主総会の招集通知には、原則として取締役会で定めた会社法第298条第1項(株主総会の日時及び場所等)の事項を記載します。株主にWEB参加・WEB出席を認める場合は、そのテレビ会議システムのURLを記載するか、そのURLの交付を受けるための会社担当者のメールアドレスを記載するケースも増えています。
株主総会参考書類の交付
書面投票・電子投票を認める場合、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(株主総会参考書類)の交付が必要です。
株主総会の招集通知を発する方法
株式会社が取締役会設置会社である場合又は書面投票・電子投票を認める場合は、株主総会の招集の通知は書面で行います。ただし、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することも可能です。
株主総会の招集手続きの省略
株主全員の同意があるときは株主総会の招集手続きを省略することができますので、書面投票・電子投票を認める場合を除き、招集通知を発することなく株主総会を開催することも可能です。
みなし決議という方法
取締役又は株主が株主総会の目的事項を提案し、議決権を行使することができる株主全員が書面又は電磁的記録により当該提案に同意したときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすことができます。特に株主が少数の株式会社においては、頻繁に利用されています。